【運輸】京都でハイヤーでの観光業を行うマツシマモビリティサービスさまの外国人採用【成功事例】

会社名: 株式会社マツシマモビリティサービスさま
事業の紹介:
2007年に京都市内にて一般乗用旅客自動車運送事業の許可を取得し、2020年2月に株式会社マツシマホールディングスのグループ会社として誕生しました。観光・ハイヤー事業として、アルファード、ハイエースグランドキャビンを使用した貸切観光と、ベンツ、アウディ、 BMWなどの高級輸入車による貸切送迎を軸に上質なコンシェルジュサービスを提供しています。
業種:運輸
お話をしてくださった方:松本 南平(マツモト ナンペイ)さま
ーー外国人採用を進めているのは、複数言語を話せる方を雇いたいというニーズからでしょうか?
そうですね。京都は日本の中では一大観光地ですので、ご利用いただくゲストさまにも、満足していただく対応をしたいと考えています。複数の言語が使えれば、多くの情報をお客さまに伝えることができ、満足度も高まると考えています。
また日本に住まれている外国籍の方で「自分が住んでいる京都という街を旅行客さまに紹介したい」と考えている意欲ある方にも、実際に仕事を楽しんでもらえる場を提供できればと思っています。
ーー外国人採用の専門媒体をお使いになるのは、弊社が初めてですか?
はい。わたしがちょうど現在の部署に来たタイミングで、「今後の採用方針はどうしようか?」という話になり、自分がかねてから考えていたことと重なる部分が多かったので、外国人専門の求人媒体を使ってみることにしました。
背景として、日本人のドライバーのなり手が年々減っている印象があることも関係していますかね。
ーー弊社の媒体経由で入社された方は、もうお仕事にはデビューされていますか?
まずはわたしたちも参加している「Uberプレミアム」(※プレミアムで快適な車内空間を有するハイヤー車両がタクシー感覚で呼べるUberアプリのサービス)で動いてもらっています。
またそれ以外にも、京都のホテルから大阪へのホテルの送迎などを、ベテランのドライバーと一緒にやってもらうところからトレーニングを始めていますね。
ーーやはり、ゆくゆくはハイヤーでの京都観光がひとりでできる人材になってもらいたい、と考えていらっしゃいますか?

ガイダブルさん経由で雇った方は2人とも多言語ができます。張(チョウ)さんは台湾出身なので英語と中国語。ユセフさんはフランス語もできます。今後は当社としても、言語対応できる幅が広がっていくのかなと思っています。
現在(※インタビュー時は1月初旬)は業界として少し閑散期に入ってます。この期間でトレーニングをしっかりとして、4~5月の繁忙期で活躍していただければと考えています。
ーーハイヤーでの観光と外国人採用は、組み合わせとしてうまくいくとお考えですか?
いま特に需要が高いと思っていますね。英語やほかの言語を使って、京都をハイヤーでまわるというのは、やはり外国人の強みである語学力が活かせます。それに「京都を紹介したい」「車が好き」と思っている在留外国人の方にとっては、この仕事はうってつけなのではないかと思いますね。
ーー外国人採用はコスト面での魅力はありますか?
求人媒体経由で日本人を採用しようと思うと、2週間で40万円以上もかかることもあります。ガイダブルさんの外国人採用はコスト面でも助かっていますね。
ーー外国籍の方が職場に入ってみて、印象的なエピソードはありますか?
そうですね。弊社にはもとから外国籍のドライバーがいたので、比較的スムーズに受け入れられています。とくに社内の若いドライバーはウェルカムな雰囲気です。
今回雇った2人は二種免許(※人を乗せて車両を走らせるために必要な免許)を取得するところからでした。業界経験が長い人の中に入ってくることになります。経験のあるドライバーたちからは、心配する目でみられている部分も正直あるのかなと思いました。
ーーマネジメントする立場として気を遣う部分はあると思うのですが、松本さまがポイントと思っていることはありますか?
わたしとしては、会える日はひたすらコミュニケーションを取る、というのが必要なことだと思います。
わたしも海外での在住経験がありますし、前職でも海外の方と関わることが多かったので、個人的には彼らと関わっていてもストレスもフラストレーションもあまりないです。でも大事なのは「伝わるまで、伝えつづける」ところかなと思っています。
そして自分もただ言うだけではなくて、向こうにどんな表現なら伝わるかを考えつづける必要があると思います。会話では日本語をベースに伝えていますが、伝わらないときは英語にスイッチしてやっていますね。
ーー最後に外国人採用について、今後のビジョンがあれば教えていただきたいです

日本は島国なので、ほかの国を受け入れにくいところはあると思います。京都は土地柄なおさらです。そんな中で志を持って「京都を案内をしたい」と思ってくれる人を、ドライバーとしていかに増やしていくか、これを会社としても使命としてやっていければと思っています。
当社が彼らにとって、志高く仕事ができる場になれれば、という気持ちはありますね。
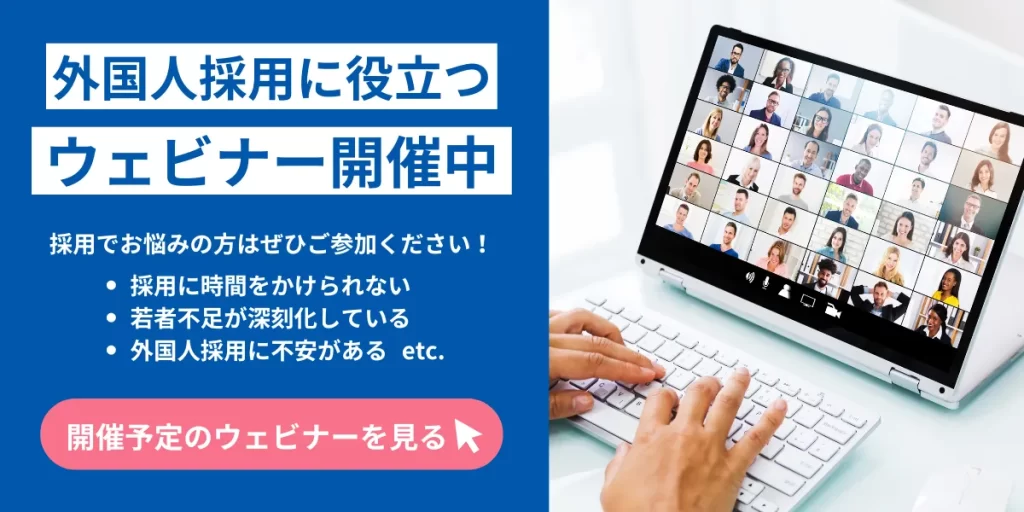
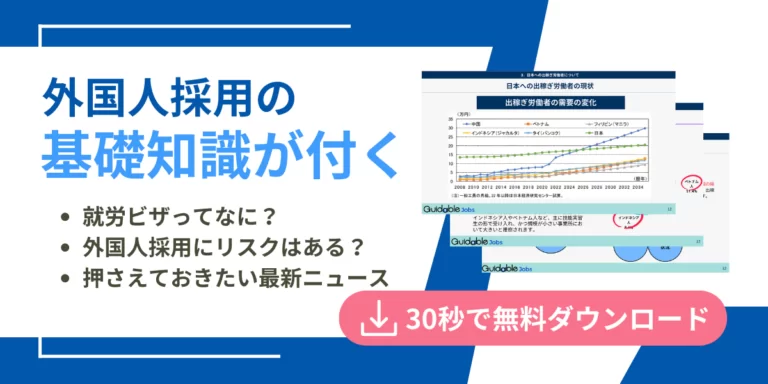










-2-780x520.png)





