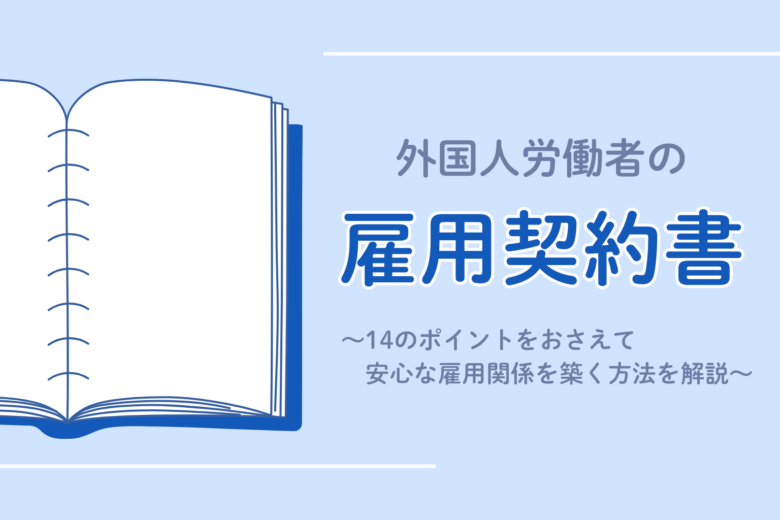日本の人手不足、なぜ起こる? 外国人材活用の前に! 「なぜ?」を知ることから始める採用の第一歩!

現在、業種や企業規模を問わず、多くの日本企業が深刻な人手不足という経営課題に直面しています。必要な人材を確保できず、事業の維持・拡大に支障をきたすケースも少なくありません。
このような状況下で、国内の労働市場だけでなく、外国人材の採用を視野に入れる、あるいはすでに取り組んでいる企業の採用担当者の皆様も多いことでしょう。
しかし、効果的な採用戦略、特に外国人材の活用を考える上では、まず「なぜ日本国内でこれほど人手不足が深刻化しているのか」という根本的な原因を深く理解することが不可欠です。国内の労働市場が抱える構造的な問題を把握することで、より的確な人材確保策を見出すための土台となります。
この記事では、日本国内の人手不足という現象に着目し、その背景にある避けて通れない4つの主要な原因について、公的なデータや情報をもとに、分かりやすく解説していきます。
目次
少子高齢化:避けられない労働人口の減少

日本の総人口は長期的な減少傾向にあり、特に生産活動の中心となる15歳から64歳の「生産年齢人口」の減少が顕著です。総務省統計局の人口推計によると、2024年10月1日現在の日本の総人口は1億2399万人で前年に比べ59万人の減少、生産年齢人口は7328万人で前年に比べ38万人の減少となっています。
少子高齢化が進むことで、労働市場への新規参入者が減少し、同時に高齢化によって労働市場から退出する人が増加します。この人口構造の変化が、労働力の供給を構造的に減少させ、人手不足の最も根本的な原因の一つとなっています。
参照:総務省統計局「人口推計(2024年(令和6年)10月1日現在)」
人材のミスマッチ:アンバランスな需給

労働人口の総数が減少する一方で、企業が求める人材と求職者が持つスキルや希望条件との間にずれが生じる「ミスマッチ」も、人手不足を深刻化させる要因です。求人があるにも関わらず就職できない「構造的失業」が存在し 、これが慢性的な人手不足につながっていると分析されています。
具体例として、企業側は製造業や建設業などで伝統技術や専門技術の継承者を求めている一方で、若者を中心とする求職者側は、いわゆる「3K(汚い・危険・きつい)」のイメージがある仕事を敬遠する傾向があること があげられます。
また、介護やサービス業など人手不足が深刻な業界がある一方で、一般事務などでは人材が余剰気味であるといった、業界間・職種間での需要と供給の偏りも顕著です 。医療・福祉分野のように、資格を持つ人材は市場に存在するものの、求職者が求める雇用条件(特に賃金)を企業が提示できずに人手不足が慢性化しているケース も指摘されています。
このようなミスマッチは、働き手の価値観の変化と密接に関連しています。働きがいやワークライフバランス、自己成長などを重視する新しい価値観を持つ働き手が増える中で、旧来型の労働条件や働き方しか提供できない企業や、製造、建設、運輸、介護などの労働負荷が高いと認識されている産業は、人材獲得競争において不利な状況に置かれやすくなっています。
つまり、単にスキルを持つ人材がいないだけでなく、提示される条件の下で働くことを望む人材が不足しているという、構造的な問題が浮き彫りになります。
参照:厚生労働省「一般職業紹介状況」、同省「労働経済の分析」
「2025年の崖」も目前:団塊世代の大量退職による影響
長らく日本の社会経済活動の中核を担ってきた「団塊の世代」が、現在、75歳以上の後期高齢者となる時期を迎えています。これは「2025年問題」とも呼ばれ、医療や介護といった社会保障制度への影響が注目される一方で、労働市場においても極めて深刻な課題をもたらしています。
まず、経験豊富な労働力が市場から本格的に退出することによる、労働力人口のさらなる減少があげられます。既に進行している少子高齢化による労働力供給の基盤縮小に、この世代の大量退職が追い打ちをかける形となり、多くの産業分野で人手不足感を一層強める大きな要因となっています。労働市場から経験豊かな層が抜けることは、単なる頭数の減少以上のインパクトを持ちます。
より深刻なのは、彼らが長年にわたる就業経験を通じて培ってきた、各分野における高度な専門知識、熟練した技能、そして言葉やマニュアルだけでは伝えきれない「暗黙知」とも言える貴重なノウハウが一挙に失われるリスクです。これらの知識や技術は、企業の競争力の源泉であり、製品やサービスの質を支える重要な基盤です。
特に、計画的な技術継承プログラムや、知識・ノウハウを形式知として組織内に蓄積・共有する取り組みが十分に進んでいない場合、団塊世代の退職は、企業の生産性低下や、場合によっては事業継続そのものに対する直接的な脅威となりかねません。
さらに、組織運営の観点からも影響は看過できません。団塊世代の多くは、企業組織の中で部長、課長といった管理職や、現場を率いるリーダーとしての重責を担ってきました。そのため、この一斉退職は、組織の中間管理職層やリーダー層に大きな空白を生じさせ、組織全体の意思決定スピードの低下や、部門間の連携不足、あるいは若手・中堅社員への指導体制の弱体化などを招く可能性があります。
次世代の経営幹部や管理職、リーダー候補の育成が計画的に進められてこなかった企業にとっては、組織運営の安定性を揺るがしかねない、マネジメント機能の低下という課題にも直面することになります。
このように、団塊世代の大量退職は、労働力の「量」的な減少に加え、企業が長年蓄積してきた技術・ノウハウといった「質」的な資産の喪失、そして組織運営を担う「人材」の不足という、複合的かつ深刻な影響を日本企業にもたらしており、人手不足問題をより一層根深いものにしている大きな要因と言えるでしょう。
参照:内閣府「高齢社会白書」
外国人材活用の壁:言語・文化・制度面の課題
国内の労働力確保が難しくなる中で、外国人材の活用に期待が寄せられています。実際に、日本で働く外国人労働者の数は増加傾向にあります。厚生労働省の発表によると、令和5年10月末時点での外国人労働者数は約204万人に達し、過去最高を更新しました。
しかし、外国人材の受け入れと活用には、依然としていくつかの壁が存在します。具体的には、コミュニケーションの基盤となる言語の習得支援、異なる文化や慣習への相互理解と適応、複雑な在留資格制度や手続きへの対応などがあげられます。また、低賃金の労働力を求めている企業の中には、このような手続きにかかる費用などを懸念し、受け入れ体制を十分に整えない企業も多くあります。
これらの課題への対応が不十分な場合、外国人材が定着し、その能力を十分に発揮することが難しくなり、結果として人手不足を解決できない可能性があります。
参照:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和5年10月末現在)」
おわりに
本記事では、日本の人手不足を引き起こしている主な原因として、「少子高齢化による労働人口の減少」「人材の偏在とミスマッチ」「団塊世代の大量退職」「外国人材活用の壁」の4点を解説しました。
これらの要因は、一朝一夕に解決できるものではなく、日本の社会構造に根差した根深い課題です。外国人材の採用を含め、今後の企業の採用戦略を検討する際には、これらの背景を正確に理解しておくことが極めて重要となります。
人手不足の原因を正しく認識し、自社の状況と照らし合わせることで、より現実的で効果的な対策への第一歩を踏み出すことができるでしょう。
外国人の採用・受け入れでお悩みならGuidable Jobsへ
外国人材の受け入れ準備や採用活動そのものに関して、「自社の要件に合う優秀な特定技能人材をどこで見つければよいか」「採用後の複雑な諸手続きや定着支援をどのように進めるべきか」といった具体的な課題に直面されている企業様もいらっしゃると思います。
Guidable株式会社では、日本最大級の外国人向け求人媒体「Guidable Jobs」の運営を通じ、様々な業界のニーズに合致する外国人材の採用活動を支援しております。
優秀な外国人材の採用にご関心をお持ちでしたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。









-14-780x520.png)

-3-1-780x520.jpg)
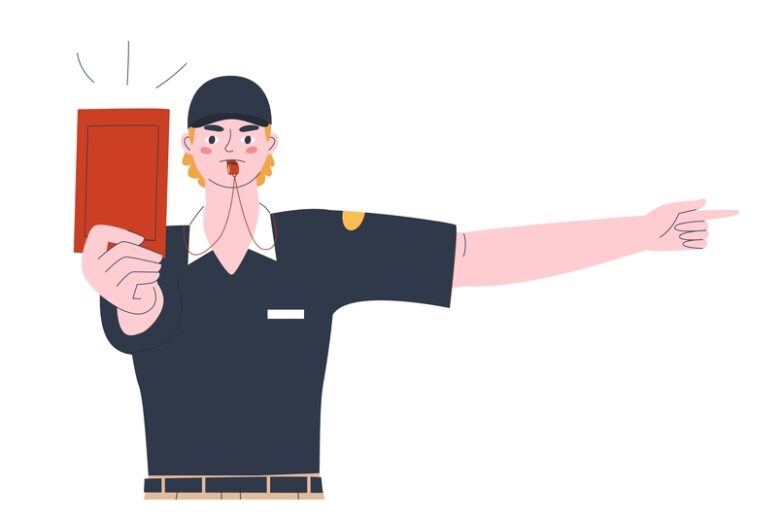



-2-780x520.png)



-2-780x520.jpg)