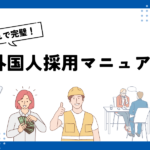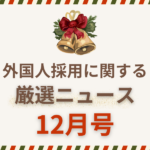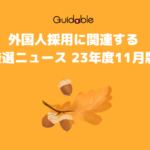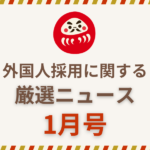外国人従業員のモチベーションを確保するには? 長時間労働、評価システムの曖昧さに気をつけることが重要!

外国人従業員にとって文化が異なる日本の就業環境は特殊な場であり、きちんと説明して理解してもらわなければ、モチベーションを保つのが難しくなりがち。労働に対する価値観や勤務時間も国ごとに異なるため、日本の勤務スタイルをムリに当てはめるとトラブルの原因になりかねません。
この記事では外国人のモチベーションを低下させる原因や、やる気を維持するために必要なことを解説いたします。仕事開始時にはモチベーションが高い外国の方に、継続的に働いてもらえる環境を構築したい方にとって役立つ情報を提供いたします。
目次
外国人従業員のモチベーションが上がらない?

暮らしてきた背景や文化が日本人とは異なる外国人労働者にとって、日本の就業環境は特殊なもので、説明のないまま勤務をつづけていると、モチベーションの低下につながる可能性もあります。出身国ごとに国民性が違うことへの理解や、歩みよる気持ちを持つことが大切です。
モチベが上がらない原因は?
勉強でも仕事でも「いい成果」を修めるためには欠かせない「モチベーション」。
しかしアイデンティティーが異なる外国人労働者にとって、日本ならではの就業環境を理解するのは難しいようです。日本国際化推進協会が独自で調査した「日本における就職の不満」に関するアンケート結果をもとに、モチベーションを阻害する原因をまとめました。
<モチベーションを阻害する原因>
- 長時間労働
- 評価システムの不透明さ
- 昇進の遅さ
- 日本人ならではのコミュニケーションの難しさ
とくに深刻なのが「長時間労働」。
なんと7割近くもの外国人が、長時間労働に対して不満を感じていることが明らかになりました。
2023年の日本の労働生産性はOECD(経済協力開発機構;ヨーロッパ諸国を中心に先進国が加盟している国際機関)に加盟する38カ国の中で、30位と低水準です。
過去をみてみると、1998年から20年間ほどは20位を前後していましたが、2019年からは26位になり、4年がさらに経過して30位にまで下がっています。
世界的にみても国家として長時間労働をする傾向が伺えます。
では中国とならび、外国人労働者としての受け入れが多いベトナムの労働規則はどうなっているのでしょうか? ベトナムでは1日の労働時間を8時間とする点は日本と同じです。しかし残業に関しての規則と習慣には、両国には大きな違いがあります。
ベトナムでは労働法上1日の残業時間は、通常勤務時間の50%を超えてはいけないと定められています。実際に既定時間を超えて残業をすることはまれです。
ベトナム人は残業を好まないため、日本の勤務スタイルにムリにあてはめるのはよくないでしょう。
外国人労働者にとっては、慣れない異国で勤務することは非常に難しい側面もあります。何の説明もなしに日本特有の就業環境で働くことは、精神的・肉体的にもストレスとなるでしょう。
労働時間を短くするような取り組みが、非常に重要になります。
日本人とは文化が違う! を前提に

コミュニケーション方法と価値観の違いから、せっかく採用した外国人労働者のモチベーションが下がってしまい、頭を悩ませている採用担当者は多いようです。
外国人労働者のモチベーションを保ち、長く就業してもらうには、文化の違いを前提に接すること、日本の就労意識を押しつけないことが非常に大切です。
そこで現在日本国内で就業している外国人の割合が高い国を中心に、国民性による傾向の違いをまとめました。
外国人労働者の内訳は中国とベトナムで約半数で、フィリピン、ブラジルがつづいて多いです。
確率的にこうした出身国の外国人が応募してくる可能性が高くなりますので、国民性を把握すると採用や教育をスムーズに行えます。
<各国の国民性>
- 中国 ・・・ 合理主義
- ベトナム ・・・ 仕事に比べて個人や家族を大切にする
- フィリピン ・・・ 外国への出稼ぎの傾向が強い
- ブラジル ・・・ 賃金をもっとも重視
日本人の人事に関しても、適材適所に人材を配置するのと同じように、外国人労働者も適正に合う職種に配置する方がいいでしょう。
ただ国民性というものも、あくまでひとつの傾向に過ぎません。それぞれの雇われた方の人間性や得意なこと不得意なことに合わせて、柔軟に配置を変えていくことが急な離職を防止する方法かもしれません。
▼こちらの記事もおすすめ
外国人従業員もモチベーションはこう確保する!

外国人労働者にそのままモチベーションを維持して就労しつづけてもらうためには、日本の「評価システムへの理解」と「なんでも話せる相談相手」が欠かせません。
以下に、外国人が順調にキャリアアップするためのポイントをまとめました。
キャリア計画をシェアしよう
キャリアアップ志向が強い外国人にとって、ただやみくもに目の前の仕事をこなすことは本意ではないでしょう。目標を見失わないように、入社後のキャリアプランをイメージしやすい職種に採用することはモチベーションを維持する上で効果的です。
また一見すると単純作業で無意味に思える仕事でも、下積みとして必要な作業であることや、その後のキャリアプランにどうつながるかは説明してあげましょう。そうすれば漠然とした不安や迷いは解消し、定めたゴールに向かって正しく進むことができるようになります。
評価方法をしっかり説明
自分が会社から期待されていることや、仕事に対しての自身の「評価」について、外国人は日本人以上に関心を持つようです。「正当な評価がなされているのか」「昇給や昇格はあるのか」ということも含んでいるのでしょう。
しかしわかりづらい評価制度だと、外国人社員のモチベーションを低下させてしまいます。
また日本語が不得意な外国人の場合には、評価内容が伝わっていないこともあります。認識のズレを防ぐために、日本語がうまい外国人労働者を抜擢し、あいだを取り持ってもらうなどの対策は有用です。
評価が不透明であるとモチベーションの低下だけでなく、早期退職の原因にもなりかねないので、評価方法とその内容はしっかりと説明しましょう。
コミュニケーションを活発に
外国人が異国で働くことは、わたしたちが想像している以上に大きな不安とストレスを感じるものです。たとえばベトナム人には、枕や毛布を持参してお昼休憩に仮眠を取る習慣がありますが(いい習慣ですよね!)、日本にはそのような習慣を持つ企業は多くありません。
環境になじめず、だれにも相談できないまま、ひとりで悩みを抱え込んでいる可能性もあります。そのため仕事やプライベートの悩みを話せる「相談相手」を作れるように、コミュニケーションを活発にする取り組みをしましょう。
具体的にはSNSを活用して出身国同士のコミュニティを作ることや、日本人社員と外国人労働者の交流会を定期的に設けるなど、積極的なアクションをすることが大切です。
メンターは上司以外で探す
「メンター制度」とは、直属の上司ではなく年齢の近い年上の先輩社員や、社歴が近い先輩社員が若手社員をサポートする制度。新入社員は身近な存在ができて、ささいなことでも相談しやすくなり、会社への居心地がよくなります。
慣れない環境で孤立しかねない外国人労働者にとって、メンター制度は大いに活用すべきものでしょう。仕事に関わらず困っていることはないか、こまめにサポートしてあげられるといいですね。職場に理解者がいてくれることはこころの支えであり、がんばろうというモチベーション向上にもいい影響を与えてくれます。
外国人従業員のモチベーションは確保できそうですか?

日本で就労する外国人にとって、「不透明な評価システム」や「昇進が遅いこと」は不満を感じる要因となります。優秀な外国人を雇用して、高いモチベーションを維持して仕事に取り組んでもらうためには就労環境を整えることが重要です。
コミュニケーションを活発にして気軽に相談できる場所を作りましょう。文化が違うことを理解して、おたがいに歩み寄る姿勢が大切です。