【2025年最新】特定技能 定期報告の完全ガイド|年1回制の変更点・書類の書き方も解説

特定技能の外国人を受け入れている企業や支援機関にとって、定期報告は必ず行わなければならない手続きのひとつです。
この記事では、定期報告のしくみや必要な書類の例、初心者がまちがえやすいポイントについて、できるだけわかりやすく紹介します。それぞれの書類にどんな特徴があるのか、提出するときに気をつけたいことなどもくわしくまとめました。
はじめて定期報告に取り組む方も、社内の流れを見直したい方も、内容を確認する際の参考にしてみてください。
特定技能外国人の「定期報告」とは?
特定技能外国人の働き方や生活状況を国に伝える制度は届出制度と総称されます。これは、外国人が安心して働き生活できているかを確認し、その立場が守られることを目的としています。この届出は、受け入れ企業と登録支援機関に義務付けられています。
届出には、事由発生の都度行う随時届出と、定期的に行う定期届出があります。
このうち定期届出は、継続的な受け入れ体制や支援計画に関する定期的な提出義務全体を指します。そして、その核心となるのが定期報告です。定期報告では年に一度、外国人の雇用状況や支援の実施内容などをまとめて国に提出し、制度の適正な運用を証明します。
報告を怠ったり、虚偽の内容を提出したりすると、企業や機関が罰則を受ける可能性があります。そのため、決まりを守り正しく対応することが、信頼される体制づくりに不可欠です。
定期報告はいつ・誰が・どうやって出す?

定期報告は、提出のタイミング・担当者・方法があらかじめ決まっています。まずは提出時期の流れを確認しましょう。
報告のタイミング:四半期制 → 年1回制へ
これまで定期報告は、3か月ごと(四半期ごと)に行うルールでした。しかし、2025年4月からは年1回制へ変更されました。以下のスケジュールで移行します。
| 区分 | 対象期間 | 提出期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 最後の四半期報告(従来制度) | 2025年1月1日〜2025年3月31日 | 2025年4月1日〜2025年4月15日 | これが「四半期ごとの報告制度」での最終回。 |
| 新制度(年1回制)初回 | 2025年4月1日〜2026年3月31日 | 2026年4月1日〜2026年5月31日 | この1年間分をまとめて1回で提出します。 |
| 以降の毎年の報告 | 毎年4月1日〜翌年3月31日 | 翌年度の4月1日〜5月31日 | 毎年このサイクルで提出します。 |
(参照:法務省 出入国在留管理庁「特定技能に関する定期報告」)
年1回制への移行による主なメリット
これまでの四半期ごとの提出では、事務作業の負担が大きく、内容の重複も多く発生していました。年1回制への移行により、
- 報告書作成の頻度が減り、企業側の負担軽減につながる
- 報告内容を年度単位で整理でき、より正確な管理・分析が可能になる
- 行政側でも処理の効率化とデジタル化が進む
といった効果が期待されています。
企業・登録支援機関それぞれが届出書類を作成する
提出する書類の内容は異なりますが、どちらも会社ごとにまとめて出すという点は共通しています。
企業が提出する主な書類(特定技能所属機関)
- 【必須】受入れ・活動状況に係る届出書(様式第3-6号)
- 【必須】特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(様式第3-6号別紙)
- 【必須】賃金台帳の写し(特定技能外国人および比較対象の日本人のもの)
- 【通貨払いの場合】報酬支払証明書(様式第5-7号)
- 【自社で支援している場合】支援実施状況に係る届出書(様式第3-7号)
- 【自社で支援している場合】1号特定技能外国人支援対象者名簿(様式第3-7号別紙)
- 相談記録書(様式第5-4号)
- 定期面談報告書(様式第5-5号・5-6号)
- 転職支援実施報告書(様式第5-12号)
- 支援未実施に係る理由書(様式第5-13号)
- 提出が遅れた場合や特別な事情がある場合の理由書(任意様式)
登録支援機関が提出する書類(全面委託を受けている場合)
- 【必須】支援実施状況に係る届出書(様式第4-3号)
- 【必須】1号特定技能外国人支援対象者名簿(様式第4-3号別紙)
- 相談記録書(様式第5-4号)
- 定期面談報告書(様式第5-5号・5-6号)
- 転職支援実施報告書(様式第5-12号)
- 支援未実施に係る理由書(様式第5-13号)
- 提出が遅れた場合や特別な事情がある場合の理由書(任意様式)
地方出入国在留管理局へ提出する
報告書類の提出先は、本店の住所(個人事業主の場合は住民票の住所)を管轄している地方出入国在留管理局です。提出方法は3つあり、①窓口への持参、②郵送、③電子届出システムのいずれかを選びます。
電子届出を使うには、事前に「利用者ID」を取っておく必要があります。郵送よりも確認や返送が早く、送った書類の状況もオンラインでチェックできるため、忙しい人には便利です。
郵送の場合は「簡易書留」や「配達記録郵便」を使って、いつ送ったかが証明できる形にしておきましょう。
企業が用意する必須書類の書き方・注意点
定期報告では、企業(特定技能所属機関)は定められた様式に従って書類を作成・提出しなければなりません。使用する様式や記入方法には細かいルールがあります。
出入国在留管理庁では、運用改善の一環として 様式の簡素化・オンライン提出化 を進める方針が示されており、実際に参考様式の一部改正も行われています
ただし、2025年10月時点では すべての最終型の様式や記入例が公表されていないものもあり、従来の参考様式も引き続き参照される案内が残っています。
したがって、2025年度(2025年4月~2026年3月分)の報告 では、現行の参考様式をもとに記入・作成するのが妥当です。記入ミスや記載漏れがあると、提出書類が受理されなかったり、修正を求められたりすることもあります。
次項では、記入時に注意すべき主なポイントを確認していきましょう。
受入れ・活動状況に係る届出書(様式第3-6号)

★1 届出書は事業所単位ではなく、法人全体で1部だけをまとめて提出する形式です。
★2 複数の特定産業分野に該当する場合は、それぞれを分けずに1つの届出書に記入する決まりです。
★3 法人は登記簿上の本店所在地を、個人事業主は住民票に記載された住所を記入する必要があります。
★4 現金などの通貨で賃金を支払っている場合は報酬支払証明書を添付し、賃金台帳には金額や勤務時間が明確にわかる資料を用意する必要があります。

★5 比較対象とする日本人の賃金台帳も提出し、対象者に変更があった場合は説明書(1-4号)も一緒に提出する必要があります。
★6 特定技能外国人の人数はすべて合算し、該当者がいない場合は「0」と記載する決まりです。
★7 在籍者数は届出対象期間の最終日時点で実際に勤務している人のみをカウントするルールです。
★8 届出期間中に実際に就労を開始した人数を記載し、まだ働いていない人は含めないようにします。
★9 退職者については自己都合と会社都合を区別して記載し、非自発的離職があった場合は労働者名簿を添付する必要があります。
★10 行方がわからない人がいる場合は人数を明記し、あわせて届出書(3-4号または3-1号)も提出する必要があります。
★11 同じ業務に従事している日本人は、説明書に記載があるかどうかにかかわらず、すべて含める決まりです。
★12 特定技能外国人と違う職種(総務、人事、経理など)に就いている社員の人数を記載する必要があります。
★13 保険の手続きが未完了の人がいる場合は、理由書を添付し、チェック欄に印を付けてください。

★14 労働災害が発生していた場合は内容を理由書に記載し、法律違反があればその点も報告する必要があります。
★15 支援計画にかかった費用については、委託料や教材代などの実費を記載します。
★16 届出期間中に退職した1号特定技能外国人も、支援費用の対象人数に含める必要があります。
★17 受入れ準備にかかった費用には、本人が負担した金額も含め、人数と金額の両方を明記します。
★18 行政からの指導や適格性に関する指摘があった場合は、その内容を理由書にまとめて提出する必要があります。

★19 届出書には、内容に責任を持つ役職者の氏名を必ず記載します。
★20 届出書の作成を実際に行った人が署名し、印刷や社判のみでの提出は認められていません。
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況(様式第3-6号別紙)

★1 届出書は事業所単位ではなく、法人全体で1部作成・提出する形式です。
★2 活動場所や業務内容に変更があった場合は「変更あり」にチェックし、契約変更届出書も提出する必要があります。
★3 派遣先の記載は、農業・漁業分野で派遣労働を行うケースに限って記載する決まりです。
★4 活動日数は、実際に働いた日数を月ごとに記載し、勤務がなかった月は取消線で表記します。
★5 報酬欄には、各月に実際に支払った金額(支払日ベース)を記入します。
★6 支給総額には、基本給や手当などの控除前の合計額を記載する必要があります。
★7 差引支給額には、各種控除を差し引いた後に本人が受け取った手取り額を記入します。
★8 法定控除額には、所得税・住民税・社会保険料・雇用保険料などをすべて記載してください。
★9 比較対象者の有無を選択し、変更があった場合は報酬に関する説明書(1-4号)を作成・添付する必要があります。
★10 記載欄が足りない場合は、必要に応じてシートを追加・編集して問題ありません。
賃金台帳の写し
特定技能の外国人と、日本人の比較対象となる人(または同じ仕事をしている人)の賃金台帳を提出します。内容には、基本給、残業代、引かれる金額、最終的な手取りなどがはっきりわかるようにしておきましょう。
もし比較対象の日本人がすでに退職している場合は、その人の後に入った人の賃金台帳にくわえて、報酬に関する説明書(1-4号)も出さなければなりません。
報酬支払証明書(様式第5-7号)

銀行振込ではなく、現金などの通貨で給料を手渡ししている場合には、この証明書が必要です。給料をきちんと渡したことを証明するために、外国人本人に署名や押印をしてもらいます。
書く内容は、支払った日付、金額などです。外国人一人につき1枚ずつ作成してください。署名や印鑑の記入を忘れないように気をつけましょう。
支援実施状況に係る届出書(様式第3-7号)

★1 企業が自ら支援を実施している場合は、この届出書(3-7号)を提出し、すべてを委託している場合は提出不要です。
★2 所在地は、法人の場合は登記簿上の本店、個人事業主の場合は住民票記載の住所を記入する必要があります。
★3 その四半期中に1日でも受け入れた1号特定技能外国人は、名簿(3-7号別紙)に記載します。
★4 予定された支援について、「すべて実施」または「一部未実施」から該当するものを選択してください。
★5 届出書には、内容に責任を持つ役職者の氏名を記載します。
★6 実際に届出書を作成した担当者が署名し、印字や社判だけでは認められていません。
1号特定技能外国人支援対象者名簿(様式第3-7号別紙)

★1 在留カード番号は、届出時点で本人が所持している最新のものを記入します。
★2 支援が未実施だった場合は該当欄にチェックを入れ、理由書(5-13号)を添付してください。また、面談で問題があった場合は「問題あり」にチェックし、報告書(5-5号・5-6号)も添付する必要があります。
※ここで紹介したもの以外に、提出が必要な書類が出てくる場合もあります。くわしい情報は、出入国在留管理庁の公式案内ページを確認しておくと安心です。
定期報告のコツとチェックするポイント
報告手続きで特に注意したい、見落としがちな4つのポイントを簡潔にまとめました。
- 退職者も報告の対象 対象期間中にたとえ1日でも在籍していたなら、すでに退職した人でも報告が必要です。「在籍していた事実」が重要と覚えておきましょう。
- 在留資格が変わった人も対象 期間の途中で在留資格が「特定技能」から別のものに変わった場合でも、特定技能として在籍していた期間分は報告の対象になります。
- まだ働いていない人は対象外 雇用契約を結んでいても、まだ来日していない、あるいは特定技能の在留資格に切り替わっていない段階では、定期報告の対象にはなりません。
- 電子届出は事前のID登録が必須 便利な電子届出システムですが、利用するには事前のID登録が必要です。提出間際で慌てないよう、早めに手続きを済ませておきましょう。
よくある質問(Q&A)

最後に、定期報告について担当者の方が抱えやすい疑問にお答えします。不安な点や分からないことがあっても、基本的な考え方を知っておけば落ち着いて対応できます。
Q1. はじめての定期報告で、何から手をつけて良いか分かりません。
A1. まずは、この記事のチェックリストを参考に「提出期限」と「自社に必要な書類」を確認することから始めましょう。特に、支援を自社で行っているか、給与は手渡しかどうかで書類が変わります。 一つ一つの書類の役割を理解し、焦らずに準備を進めることが大切です。もし不明な点があれば、管轄の出入国在留管理局のWebサイトを確認したり、問い合わせたりすることもできます。早めに準備を始めれば、落ち着いて対応できますのでご安心ください。
Q2. もし書類に不備があったり、提出が少し遅れたりしたら、罰則がありますか?
A2. 書類に不備があった場合は、出入国在留管理局から修正や再提出の指示がありますので、その指示に従って対応すれば問題ありません。万が一、提出が期限を過ぎてしまった場合は、正直に遅れた理由を記した書類(理由書)を添えて、できるだけ速やかに提出しましょう。 意図的に報告を怠るなど悪質なケースでなければ、すぐに厳しい罰則が科されることは稀です。
Q3. 比較対象となる同じ業務の日本人がいない場合、どうすれば良いですか?
A3. 同じ業務を行う日本人がいない場合は、特定技能外国人の給与額が妥当であることを説明する資料(例:会社の賃金規程など)を代わりに提出します。なぜその給与額になったのか、客観的な基準を示すことができれば大丈夫です。外国人だからという理由で不当に低い報酬になっていないことを示すのが目的ですので、その点が説明できれば問題ありません。
Q4. なぜすでに退職した外国人のことまで報告する必要があるのですか?
A4. これは、外国人が貴社に在籍していた期間中、きちんとルールに則った雇用環境が提供されていたかを確認するためのものです。退職後であっても、企業には在籍中の状況を国に報告する義務があります。これは、外国人労働者を守り、制度全体の信頼性を保つための大切な手続きです。
まとめ
特定技能の定期報告、提出前のうっかりミスを防ぐための最終確認リストです。忙しい担当者の方も、これだけで重要ポイントをチェックできます。
- 報告タイミング:2025年4月以降の対象期間からは「年1回」の提出です。自社の提出対象期間を確認しましたか?
- 提出先:本社の住所を管轄する「地方出入国在留管理局」で合っていますか?
- 提出方法:「窓口持参」「郵送」「電子届出」のどれにするか決めていますか?
- 電子届出の準備:電子届出システムを利用する場合、事前の「利用者ID」登録は完了していますか?
- 郵送の準備:郵送する場合、「簡易書留」や「配達記録郵便」など、記録が残る方法で送る準備はできていますか?
- 法人単位での作成:届出書は事業所ごとではなく、「法人全体で1部」にまとめていますか?
- 賃金台帳の内容:特定技能外国人と比較対象の日本人の賃金台帳を添付しましたか? 金額や勤務時間が明確にわかるものですか?
- 人数のカウント:在籍者数(期間最終日時点)、新規就労者数、退職者数、行方不明者数を正しく記載しましたか?
- 支援費用の記載:支援にかかった実費を正しく記載しましたか?
- 署名:届出書には、責任を持つ役職者の氏名と、作成担当者の自筆署がありますか?(PCでの印字や社判のみは認められません)
定期報告は、制度を守るための義務であると同時に、外国人材が安心して働ける環境をつくるための大切な仕組みです。
2026年度からは、書類の様式が簡単になる見直しも予定されています。新しい情報をこまめに確認しながら、社内でのルール整備や業務の仕組み化を進めていきましょう。
制度対応だけで終わらせない、外国人材活用の次の一歩を考えよう
特定技能の定期報告をきっかけに、外国人材の雇用や支援体制を見直す企業が増えています。制度に合った対応はもちろん大切ですが、それだけで現場の課題がすべて解決するとは限りません。
日々のコミュニケーションや定着支援など、実務では迷いやすい場面が多くあります。
そんなときに役立つのが『在留資格ガイド』です。制度の全体像から各在留資格のちがい、採用時の注意点まで、必要な情報をわかりやすくまとめています。
特定技能以外の選択肢も視野に入れたい方や、新たに外国人採用を担当することになった方は、今のうちに押さえておくと安心です。



-26-780x520.png)
-21-780x520.png)
-780x520.png)
-19-780x520.jpg)
-8-780x520.png)
-2-780x520.png)


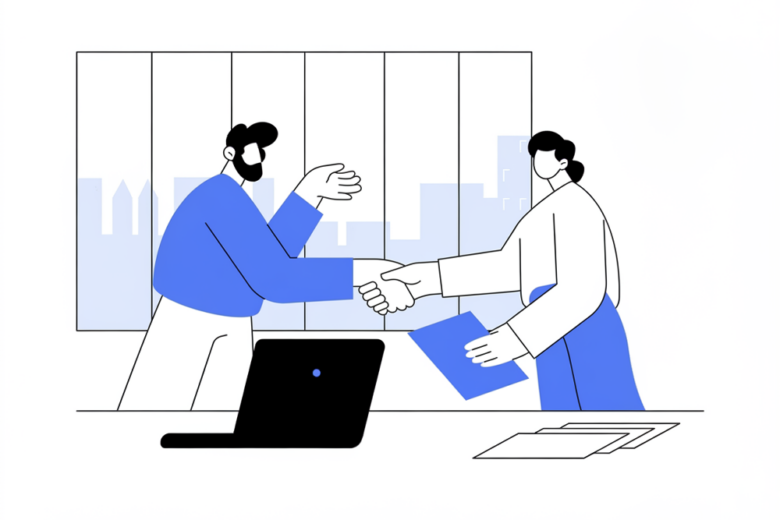




-2-780x520.png)



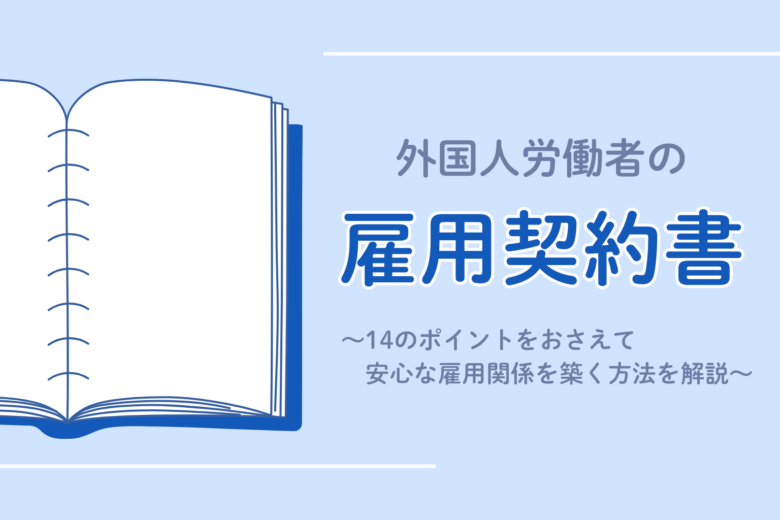
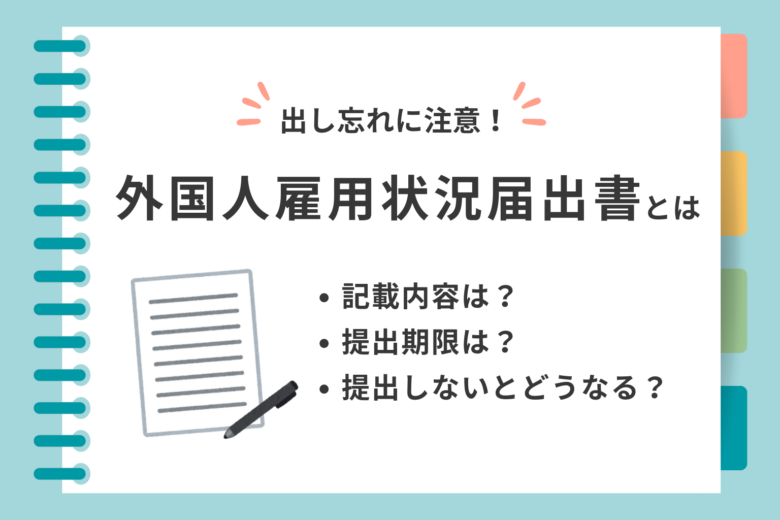
-3-780x520.png)

