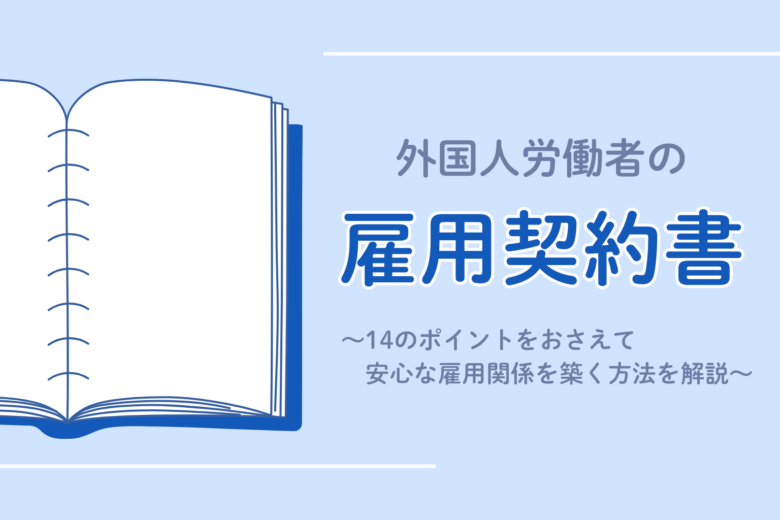日本の人手不足の今後をデータをもとに解説!外国人材を活用する方法は?

企業の人材確保は、現代日本の重要な経営課題の一つです。特に、少子高齢化が進む日本では、将来的な労働力不足が深刻化すると予測されており、多くの企業の採用担当者様が強い関心を寄せられています。
本記事では、統計データにもとづき、予測される日本の人手不足の未来を解説し、その解決策としての外国人採用の必要性について考えていきます。
日本の人口推移

すすむ少子高齢化
NIPSSRの最新推計(令和5年推計、2023年公表)によれば、日本の総人口は長期的な減少の局面に入っており、2020年の1億2,615万人から、2056年には1億人を下回り、2070年には8,700万人まで減少すると見込まれています。これは、今後50年間で日本の人口規模が約3割縮小することを意味します。
この人口減少の根本的な要因は、低い出生率にあります。合計特殊出生率は、過去最低水準を更新し続け、2002年には1.32となりました。
最新の推計では、短期的には新型コロナウイルス感染症拡大の影響等もあり1.2台で推移した後、緩やかに回復しましたが、2070年時点でも1.36程度にとどまると予測されています。これは、人口維持に必要とされる水準を大幅に下回ります。過去の推計と比較しても、出生率の見通しは下方修正されており、少子化の流れに歯止めがかかっていない状況がうかがえます。
一方で、平均寿命は緩やかながら延伸を続け、2070年には男性が85.89歳、女性は91.94歳に達すると見込まれており、これが人口の高齢化を一層進める要因となっています。
縮小する生産年齢人口
労働力の中核である生産年齢人口(15~64歳)の減少は、総人口の減少以上に深刻です。2020年に7,509万人であった生産年齢人口は、2070年には4,535万人へと、約4割も減少すると推計されています。これは、経済活動の担い手が大幅に減少することを直接的に意味します。
同時に、高齢化は急速に進行します。65歳以上人口(老年人口)の総人口に占める割合は、2020年の28.6%から一貫して上昇を続け、2070年には38.7%に達する見込みです。日本の高齢化のスピードは国際的に見ても極めて速く、老年人口比率が7%から14%に達するのに要した期間はわずか24年であり、これはフランスやスウェーデンなどと比べて突出しています 。
この高齢者依存率の上昇は、社会保障制度の持続可能性や、現役世代の経済的負担、そして労働市場における世代間のバランスに大きな影響を与えます。
参照:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」
外国人材の流入拡大

最新のNIPSSR推計(令和5年推計)を読み解く上で注意すべき点は、国際人口移動、特に外国人人口の流入に関する仮定の変更です。
前回の平成29年における推計では、外国人の年間純流入数を約7万人程度と仮定していたのに対し、令和5年推計では、近年の実績(コロナ禍前)を反映し、年間約16万4千人程度の純流入が続くと仮定しています。
この外国人流入数の仮定の大幅な上方修正は、推計結果に大きな影響を与えています。
具体的には、合計特殊出生率の将来見通しが前回推計よりも低い水準に下方修正されたにもかかわらず、総人口の将来推計値は前回推計よりも多くなっています。これは、出生率低下による人口減少効果を、外国人流入増の効果が上回ったことを意味します。
この事実は、日本の将来人口、ひいては労働力供給の見通しが、外国人流入の動向に以前にも増して大きく依存するようになったことを示唆しています。推計が示す「人口減少の若干の緩和」は、あくまでも年間16万人超という、過去と比較して高い水準の外国人純流入が今後数十年にわたって継続するという仮定にもとづいています。
この仮定の実現は、日本政府の今後の外国人受け入れ政策、国内外の経済状況、国際的な人の移動を取り巻く環境など、多くの不確実な要因に左右されます。したがって、この推計結果を解釈する際には、その前提となる外国人流入の仮定の妥当性や実現可能性について、慎重な検討が必要となります。
もし仮定通りの流入が実現しなければ、実際の人口減少や労働力不足は、推計値よりもさらに深刻化する可能性があります。
参照:国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」
外国人材の活用

国内労働力の減少を補うため、外国人材の受け入れは重要な政策となっています。政府の基本方針は、専門的・技術的分野の人材は積極的に受け入れる一方、いわゆる単純労働分野については、国内人材の確保や生産性向上努力を優先し、慎重に判断するというものです 。
この方針の下、2019年4月に導入されたのが在留資格「特定技能」です。これは、特に人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的としています。
特定技能には、最長5年間滞在可能な「1号」と、熟練した技能を持ち在留期間の更新や家族帯同が可能な「2号」があります。政府は、2024年度からの5年間で、特定技能1号の受け入れ見込み数を最大82万人と、従来目標から大幅に引き上げる方針を示しています。
特定技能在留資格を持つ外国人数は増加しており、特に飲食料品製造業、製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)、農業、介護分野などで受け入れが進んでいます。しかし、制度全体の受け入れ実績は当初の見込みを下回っており、特に「2号」の取得者は依然として極めて少ないです。
制度の複雑さ、受け入れ企業側の体制整備、外国人労働者の権利保護や生活支援、日本語能力の要件、送り出し国との調整など、運用上の課題も指摘されています。また、特定技能制度の前段階とも位置づけられる技能実習制度については、人権侵害などの問題点が指摘され、「育成就労」制度への見直しが進められています。
外国人材の円滑な受け入れと共生社会の実現には、制度運用面の改善に加え、社会全体の理解と支援体制の強化が不可欠です。
参照:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」
おわりに
本記事では、公的なデータをもとに、日本の人手不足の深刻な未来予測について解説しました。生産年齢人口の減少は避けられない事実であり、多くの企業にとって人材確保は今後さらに厳しい課題となるでしょう。
このような状況下で、企業が持続的に成長していくためには、従来の採用戦略を見直し、多様な人材活用策を検討することが不可欠です。特に、増加傾向にある外国人材の活用は、人手不足解消の有力な選択肢の一つとして、積極的に検討すべきテーマと言えます。
未来を見据え、早期に人材戦略を構築し、外国人採用を含む多様なアプローチを視野に入れることが、今後の企業経営において極めて重要になるでしょう。
外国人の採用・受け入れでお悩みならGuidable Jobsへ
外国人材の受け入れ準備や採用活動そのものに関して、「自社の要件に合う優秀な特定技能人材をどこで見つければよいか」「採用後の複雑な諸手続きや定着支援をどのように進めるべきか」といった具体的な課題に直面されている企業様もいらっしゃると思います。
Guidable株式会社では、日本最大級の外国人向け求人媒体「Guidable Jobs」の運営を通じ、様々な業界のニーズに合致する外国人材の採用活動を支援しております。
優秀な外国人材の採用にご関心をお持ちでしたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。




-11-1-780x520.png)
-6-780x520.png)
-10-1-780x520.png)
-4-780x520.png)



-2-780x520.png)



-2-780x520.jpg)