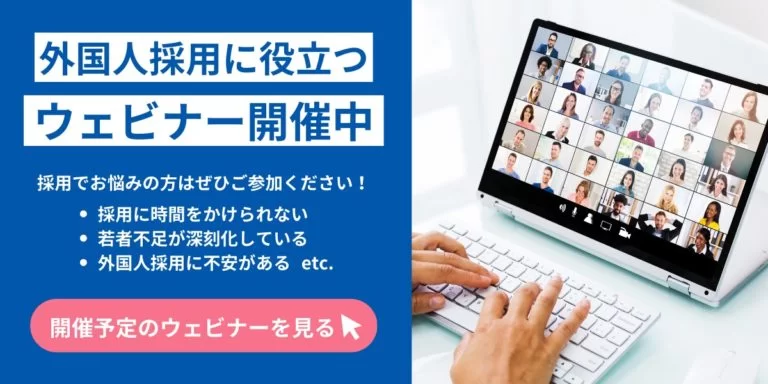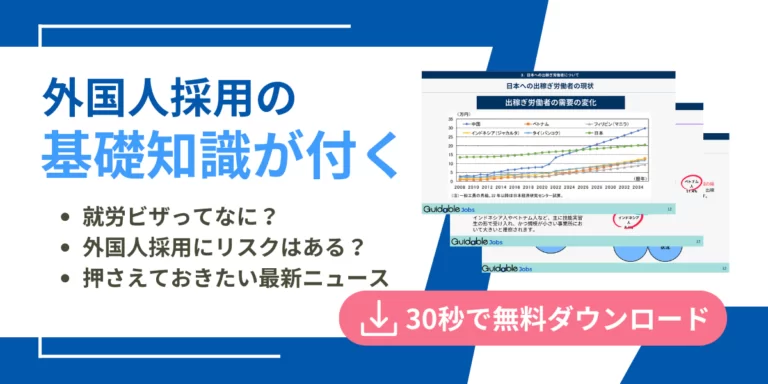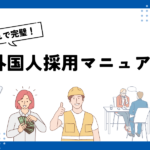外国人と日本人にかかる税金の違い|どの税金に違いがあるのか、租税条約で軽減・免税ができるのか具体例を用いて解説!

外国人労働者を雇用したり、外国人と一緒に働くことは珍しくない時代になりました。
日本政府も外国人雇用の増加に向けて積極的に取り組んでいるため、受け入れを検討している企業は少なくありません。
外国人の雇用を検討している方の中には「通常の税制だけでもややこしいのに、外国人に対する税制を学ぶなんて大変すぎる…」と考えている人もいるかもしれません。
本記事では「労働者にかかる税金」について、日本人と外国人の違いを解説します。
目次
代表的な税制は、日本人と外国人で違いがあるの?
私たちに身近な税金を一覧表にまとめました。
| 税金の種類 | 日本人 | 外国人(居住者) | 外国人(非居住者) |
| 所得税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(一律20.42%) |
| 住民税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 非課税 |
| 固定資産税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| 不動産取得税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| 相続税 | 課税 | 課税(条件あり) | 課税(条件あり) |
| 贈与税 | 課税 | 課税(条件あり) | 課税(条件あり) |
| 消費税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| 酒税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| たばこ税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
外国人に対する税制について、まず覚えたいのは所得税や住民税、相続税などの直接税は日本人と異なる部分があるということです。
その反面、消費税や酒税などの間接税は基本的に日本で暮らす全ての人が平等に支払うことになっています。
また、上の表では「居住者」「非居住者」に分けていますが「居住者」とは国内に住所がある人、または現在まで継続して1年以上日本に居住している人を指します。
「非居住者」は、来日から1年間以内かつ雇用契約が1年未満の外国人を指します。
「所得税」は外国人が非居住者の場合に税率が変わる

日本人は所得金額に対して「累進課税」が適用されます。
そして外国人が居住者の場合は、日本人と同様に「累進課税」が適用されます。課税対象には、国内源泉所得と国外源泉所得の両方が含まれます。
日本人と異なるのは、外国人が「非居住者」の場合です。
非居住者は国内源泉所得のみが課税対象となり、給与の支給額に対して一律20.42%の税率が適用されます。
源泉徴収のみで課税関係が完結するため、年末調整をおこなう必要はありません。
また、居住者が医療費や生命保険料などの各種控除を受けられるのに対して、非居住者の所得控除は「雑損控除」「寄附金控除」「基礎控除」の3つのみとなっています。
「住民税」は外国人が居住者になった時点で課税対象になる
所得税と同様に、日本人と外国人居住者は同じ内容で住民税が課税されます。
国籍は関係なく、ふるさと納税(寄附金控除)などを含めた各種控除が受けられます。
日本人と異なるのは、外国人が「非居住者」の場合です。非居住者は住民税がかかりません。
ただし年の途中で居住者になった場合、居住者になった日以降の所得は翌年の課税対象になります。
「固定資産税」や「不動産取得税」は外国人の居住形態にかかわらず課税対象になる

固定資産税は、日本の土地や家屋の所有者に対して課税される税金です。また、不動産取得税は日本の不動産を取得した際にかかります。
海外の土地や家屋を所有している場合や、海外の不動産を取得した場合は日本に納税する必要はなく、不動産を取得した国に納めることになります。
これらは日本人・外国人居住者・外国人非居住者すべての人が対象です。
ただし、所有する海外の不動産で家賃収入などがあった場合は「国外源泉所得」に分類されるため、日本人と外国人居住者が課税対象となります。
「相続税」や「贈与税」は関係者の居住条件で課税範囲が変わる
相続税とは、亡くなった親など(被相続者)からお金や土地などの財産を受け継いだ人(相続者)が、受け取った財産に対して課される税金です。
贈与税は、誰か(贈与者)から財産を受け取った人(受贈者)がその金額に応じて課される税金です。
日本人は財産が「日本国内の財産」「海外の財産」どちらの場合でも、基本的に受け取ったすべての財産が課税対象になります。
冒頭の一覧表に「課税(条件あり)」と記載しましたが、この条件とは関係する外国人が「一時居住者 ※」に当てはまるかどうかという点です。
相続税と贈与税には「非居住者」という区分がなく、そのかわりに「居住者」「一時居住者」の2区分で課税範囲が決められます。
※「一時居住者」とは
以下2つの条件のどちらも満たしている外国人のことを指します。
・身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)以外の在留資格を持っている
・過去15年以内に日本に住んでいた期間が合計10年以下である
相続者(または受贈者)が居住者の場合
外国人が一時的ではない居住者の場合、被相続者(または贈与者)が外国人であっても「日本国内の財産」「海外の財産」どちらも課税対象になります。
相続者(または受贈者)が一時居住者の場合
- 被相続者(または贈与者)が10年以内に日本で生活していた期間がある日本人の場合、「日本国内の財産」「海外の財産」どちらも課税対象になります
- 被相続者(または贈与者)が上記以外の場合は「日本国内の財産」のみ課税対象になります
租税条約を理解して、外国人の二重課税を回避しよう

租税条約とは、二重課税の排除や脱税を回避するために日本と海外の二国間で締結される条約です。租税条約を結んでいる国から来た外国人は、二重課税を防ぐために外国税額控除を受けることができます。
【適用例】外国人労働労働者と租税条約
具体的に、租税条約でどのような免税措置が受けられるのかを紹介します。
中国から来日した留学生へアルバイト代を支給する場合
たとえば、中国から来日した留学生が「資格外活動」で何らかのアルバイトをするとします。
この場合「日中租税協定第21条」が適用され、日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば免税とされます。
インド企業からの派遣労働者への対価を送金する場合
インドの会社にコンサルティングやソフトウェア開発などの人的役務を外注した場合などが、これに当てはまります。
通常、国内法では源泉所得税(一律20.42%)が課税されますが「日印租税条約第12条」の適用により、税率を10%に軽減できます。
そのほかにも、経済的・文化的交流の促進をはかるために工業所有権や著作権の使用料が軽減されるなど、国によって様々な内容があります。
租税条約に規定されている項目の適用を受けるには、原則として届出が必要です。
支払者(源泉徴収義務者)をとおして税務署に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があるため、外国人労働者を雇用する際は出身国と締結されている条約を確認しておきましょう。
さいごに
外国人労働者と日本人労働者に対する税制の違いを紹介しました。
初めは違いに戸惑うことがあるかもしれませんが、一度覚えれば効果的な雇用戦略や税務上のリスク軽減に役立ちます。
外国人採用はグローバルな視野を広げ、企業の成長につながる絶好のチャンスです。
ぜひ、その可能性を検討してみてください。