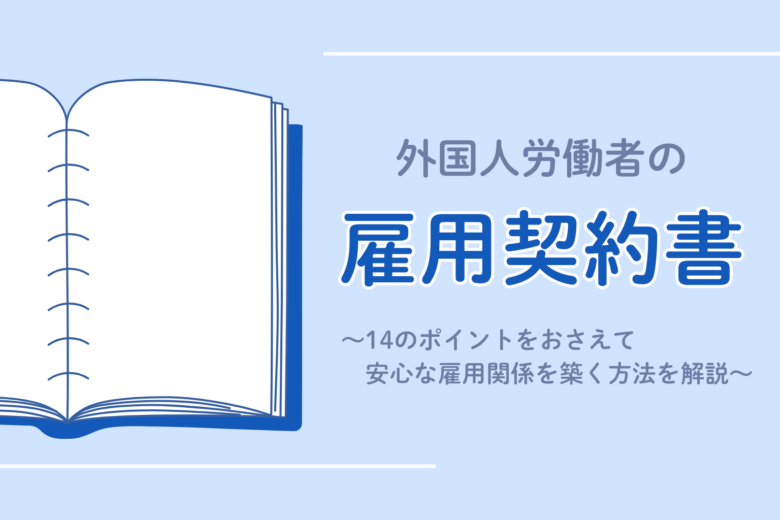高齢化社会・高齢社会・超高齢社会へ急加速する日本の課題とは? 深刻な人手不足と外国人労働者の役割をくわしく解説します

現在の日本では、65歳以上の人が全体の約3割を占めており、高齢化の進み具合は世界でもトップクラスの水準です。出生率の低下と長寿化が同時に進んだことで、医療費や介護費が増え、働き手も不足するようになりました。
その一方で、シニアの就業や外国人の受け入れが進み、労働力を補う動きも広がっています。
この記事では、日本の高齢化の現状と課題をわかりやすく整理し、外国人労働者やシニア人材の活用がどう役立つのかを紹介します。
数字で見る「高齢化」の3つの段階とは?

高齢化の進み具合には、段階ごとに名前があります。日本がどの時期にどの段階に入ったのかを見ていくと、社会の変化がよくわかります。
【高齢化社会】65歳以上が7%を超えたとき
「高齢化社会」とは、人口のうち65歳以上の人の割合が7%を超えた状態のことです。日本では1970年に高齢化率が7.1%になり、この段階に入りました。
この定義は1956年の国連の報告書に由来しています。当時は高度経済成長の真っただ中で、大家族から核家族への変化も始まっていました。働き盛りの世代9.8人で高齢者1人を支えていた時代です。
【高齢社会】14%を超えると次の段階へ
次の段階が「高齢社会」です。65歳以上の割合が14%を超えると、こう呼ばれるようになります。日本は1994年に高齢化率が14.6%となり、この段階に入りました。
寿命が延びた一方で、子どもが生まれる数は減り、1989年には合計特殊出生率が1.57まで下がりました。その結果、働く世代4.8人で高齢者1人を支えることになり、社会保障制度の見直しが求められるようになります。
【超高齢社会】21%を超えるとさらに深刻に
「超高齢社会」とは、65歳以上の人が人口の21%を超えた状態を指します。日本は2007年に21.5%となり、2023年にはすでに約29.6%まで進みました。今後は2060年ごろに40%近くに達すると予想されています。
今では働く世代2.1人で1人の高齢者を支える計算になります。日本はこのような急速な高齢化が進んだ初めての国として、世界の注目を集めています。
日本が世界最速で高齢化したのはなぜ?

高齢化はゆっくり進むと思われがちですが、日本ではとても短い期間で一気に進みました。その理由を見ていきましょう。
医療が進んだ一方で子どもが減った
日本の高齢化が急に進んだ背景には、医療が進んで寿命がのびたことと、子どもが生まれる数が減ったことがあります。1950年には平均寿命が約59歳でしたが、2023年の平均寿命は、男性が81歳、女性が87歳でした。
一方で、1人の女性が一生に産む子どもの数を示す「合計特殊出生率」は1950年には約3.65でしたが、2023年には1.2と過去最低になっています。
晩婚化や子育てにかかるお金、保育園の不足などが重なり、子どもを産み育てることがむずかしくなってきました。その結果、高齢者の割合がどんどん増え、社会のバランスがくずれ始めています。
働く世代が減る一方で、年金や医療にかかるお金が増えていくことが、今の大きな問題です。
たった数十年で2倍以上に進んだスピード
日本では、65歳以上の割合が7%から14%になるまでに24年かかりました。さらにそこから21%を超えるまで、たった13年しかかかっていません。これはフランスの115年、スウェーデンの85年と比べると、かなり早いスピードです。
そのため、医療や介護の準備が追いつかず、とくに地方では施設が足りなかったり、公共サービスを保つのがむずかしくなったりしています。
このように急激な高齢化は、社会全体の仕組みに大きな影響を与えています。
高齢化は世界中で進んでいる
高齢化は日本だけの問題ではありません。2023年のデータでは、モナコが高齢化率36.36%で1位、日本は29.56%で2位でした。プエルトリコも24%を超えています。日本は人口そのものが多いため、世界でもとくに注目される存在になっています。
さらに、中国では高齢者がすでに2億人を超えており、韓国も2025年には「超高齢社会」に入る予定です。ヨーロッパでも、イタリアやドイツ、フランスなどが高齢化率20%台後半で推移しており、医療や年金制度への負担が増えています。
どの国でも高齢化は避けられないテーマであり、制度や経済のあり方を考え直す必要がある時代が来ているといえるでしょう。
参考:GLOBAL NOTE 世界の高齢化率(高齢者人口比率) 国別ランキング・推移
超高齢社会がもたらす5つの大きな課題
高齢者が増えることで、社会にはさまざまな問題が起こり始めています。ここでは、とくに深刻とされる5つの課題を紹介します。
医療や介護の費用が増え、地域の支えにも限界がある

2025年には75歳以上の人が約2,200万人に達し、医療費は54兆円を超えると見込まれています。高齢者が増えることで、医療や介護のニーズも大きくなっています。
これに対応するため、地域ごとに支え合う「地域包括ケアシステム」の整備が進められてきましたが、人手やお金の確保が追いついていないのが現状です。
とくに地方では、病院や介護施設が足りず、公共サービスを維持することすら難しくなってきました。
働く世代が減って経済に影響が出ている
働く年齢にある人たちは、1995年に約8,700万人いましたが、2050年には約5,300万人まで減るとされています。この減少は、労働力不足や経済の停滞につながるおそれがあります。
そのため、高齢者や女性の働く場を増やすとともに、外国からの人材を受け入れる取り組みも必要とされています。
さらに、生産性の向上やデジタル技術の活用によって、少ない人数でも効率よく働ける仕組みづくりが求められています。
一人暮らしや高齢の夫婦だけの世帯が増えている

高齢者が増える中で、一人暮らしや高齢夫婦だけの世帯が急増しています。2025年には、65歳以上の人が世帯主の家庭が約1,840万世帯となり、その約7割が一人暮らしか夫婦だけの世帯になると見込まれています。
こうした変化によって、地域のつながりが弱くなり、孤立する高齢者も増えています。とくに都市部では、近所との交流が少ない人が多く、体調の異変などに周囲が気づけないケースもあるでしょう。また、介護をする側も高齢である「老老介護」が増え、家族にかかる負担も深刻になっています。
認知症の人が増え、介護の現場が対応しきれなくなる
認知症の高齢者は、2012年には約462万人でしたが、2025年には約700万人に達すると見られています。これは、65歳以上の5人に1人が認知症になるという計算です。
認知症は症状の出方が人によって違うため、専門的な知識や技術を持つ介護職員が必要になります。従来の介護では対応しきれない場面も多く、現場の負担は増える一方です。
今後は、介護人材の育成と同時に、早期発見や地域での連携も強化していく必要があるでしょう。
亡くなる人が増えて最期の過ごし方も課題になっている
2025年には、1年間で亡くなる人が約160万人になると予測されています。そのうちおよそ9割が65歳以上です。
こうした変化に対応するには、病院や自宅での看取りの体制を整えることが欠かせません。現在、都市部では緩和ケアを受けられる病棟や、自宅で看取るための支援がまだ十分とはいえない状況です。
さらに、葬儀場や火葬場、遺体を一時的に預かる施設の不足も指摘されています。高齢化がさらに進むこれからの時代に向けて、終末期に必要な準備を計画的に進めることが求められています。
人手が足りない今こそ、シニアと外国人を活かす働き方改革

日本では人口が減り続けており、働く人の数もどんどん少なくなっています。そのため、多くの企業が「人が集まらない」という悩みを抱えています。
そんな中、注目されているのが、65歳以上のシニアと外国人労働者の力をうまく活かすことです。私たちのように採用をサポートする立場でも、この2つの人材層をどう受け入れていくかが重要になっています。
働く人を増やすためには、高齢の人たちにもう一度働いてもらうことと、外国人の人たちを受け入れることの両方が大きなカギになるでしょう。
経験を活かして再び活躍するシニアの力
2023年時点で、65歳以上の人のうち約4人に1人が働いています。とくに65〜69歳では、2人に1人以上が仕事をしており、これは世界的に見ても高い水準です。
最近では「週に3日だけ働きたい」「これまでの得意分野で働きたい」といった希望を持つ人も増えており、働き方の選び方も多様になってきました。
高齢の方は、長年の経験や責任感、人とのやりとりのうまさを強みにできるため、人手が足りない業界ではとても頼りになる存在です。そうした力を活かすには、希望に合った仕事と出会えるような工夫を、企業や採用支援の側もしていく必要があります。
外国人の力で採用の可能性が広がる
外国人の働く人も年々増えていて、2024年には日本で働く外国人の数が230万人を超えました。特定技能の制度が整ってきたことで、介護・建設・飲食といった分野で外国人の採用が進んでいます。
ただし、外国人を受け入れるには、職場側も準備が必要です。言葉や文化の違いを理解し、外国人が安心して働ける環境を整えることが大切になります。
以下のような取り組みがその一例です。
やさしい日本語やマニュアルの用意
日本語に自信がない人にもわかるように、簡単な言葉で説明したり、英語や母国語にも対応できるマニュアルを用意したりすることが役立ちます。
しっかりとした研修の実施
外国人が仕事に早く慣れるためには、内容のわかりやすい研修や、段階に応じたサポートが欠かせません。
生活のサポートも忘れずに
住む場所の手配や、役所での手続きのフォローなど、日本での暮らしに不安を感じさせないようにすることも大切です。こうした支援があれば、外国人の人たちも安心して長く働き続けてくれるでしょう。
さいごに
世界中で高齢化が進んでおり、日本でもその影響が深刻になっています。なかでも、働く人の数が足りないという問題が大きくなってきました。すでに日本は「超高齢社会」と呼ばれる段階に入っており、国内だけの働き手ではこの課題を乗り越えるのは難しい状況です。
こうした中で注目されているのが、外国人労働者の存在です。海外から人材を受け入れることは、足りない労働力を補うための現実的な方法といえます。それだけでなく、さまざまな文化や経験を持つ人材が加わることで、企業の成長にもつながるでしょう。
これからの時代、外国人を採用することはますます大切になっていきます。企業は、安心して働ける環境を整えるなどの準備を進めながら、変化する社会にしっかりと対応していく必要があります。





-6-1-780x520.png)
-19-780x520.png)





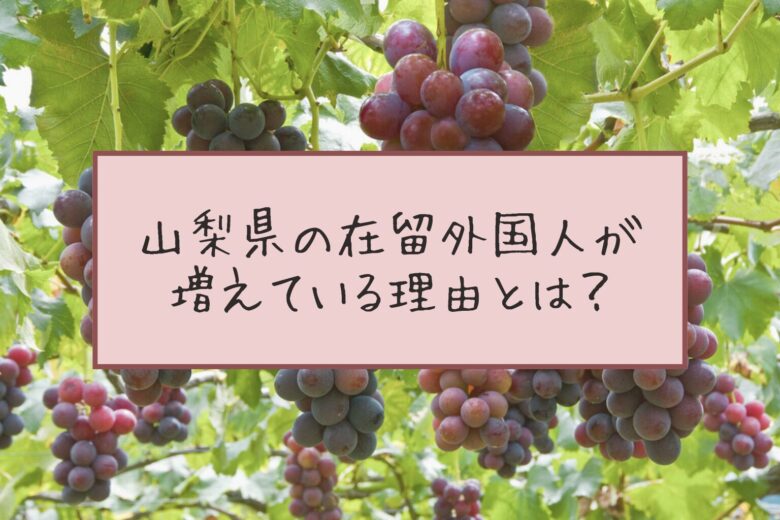



-2-780x520.png)



-2-780x520.jpg)