人材流出が止まらない? 原因の見つけ方と今日からできる防止策

「せっかく採用しても定着しない」「優秀な人ほど早く辞めてしまう」…そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
人材の流出を放置するとコストがふくらみ、現場の負担も大きくなります。そのため、原因をきちんと見つけて、早めに手を打つことが欠かせません。
この記事では、離職率のとらえ方や、社員が発しているサインの見つけ方など、人材流出の原因を探るポイントを紹介します。さらに、すぐに始められる防止策についてもまとめました。
また、採用がむずかしい地域や時間帯では、外国人の採用が有効な場合もあります。
「なぜ必要なのか」「どんな効果があるのか」を一つずつ確認しながら、止まらない離職を少しずつ落ち着かせる方向へ進めていきましょう。
目次
人材流出とは? いま何が起きているのか

人材流出とは、会社で育った従業員が別の会社に移ってしまうことを指します。
かつてのように一つの会社で長く働く人は減り、今では想定よりも早く辞めていくケースが増えました。とくに優秀な人ほど早く離れる傾向があり、経営の大きな課題になっています。
その背景には、働き方の多様化や賃上げの流れ、地方と都市の求人競争の差といった要因があります。まずは全体像をつかみ、対策の優先順位を整理していきましょう。
▼ 外国人の定着率を上げる工夫を知りたい方は こちらも参考になります ▼
社会の変化と人の流れ
働く人の価値観は「安定」だけではなく、成長や納得感へと広がっています。副業やリモートワークの普及で比較対象が増え、条件や評価があいまいな職場は敬遠されがちです。
さらに、SNSや口コミで職場の雰囲気が見えるようになり、採用だけでなく定着にも影響を与えています。こうした環境の変化が、人材流出を加速させているといえるでしょう。
終身雇用の後退と働き方の変化
長く一つの会社で勤め上げる前提は弱まり、多くの人が市場価値の向上や学び直しを意識してキャリアを選ぶようになりました。
現在は、社歴よりも成果や成長が重視されやすい時代です。評価の透明性や役割の明確さ、キャリアの見通しが欠けていると、将来への不安から早期離職につながります。
制度や運用がずれていると、それが流出の火種になりやすい点も見逃せません。
離職率の計算方法
現状を正しく知るために使われるのが「離職率」です。
離職率=(期間内の離職人数)÷(期初在籍と期中入社を踏まえた平均在籍人数)
年単位で把握するのが一般的で、新卒・中途・パートなど雇用区分ごとに出すと原因が見えやすくなります。
3年平均を出せば一時的なブレがならされ、傾向をつかみやすくなるでしょう。数値の目安を持つことで、改善の効果を実感しやすくなります。
外国人労働者の推移をまとめた記事もあるので、あわせて確認すると理解が深まります。
業界別の離職率
業界ごとに流れは異なります。サービス・小売・飲食は入れ替わりが多く、製造やインフラは比較的安定しやすい傾向です。
とはいえ、夜勤や安全負荷、繁忙期の有無など職種の特性によっても大きく左右されます。
自社が属する業界の平均と、自社の区分別データを並べて比べ、差が大きい部分から改善に取り組むのが近道です。数字は「責める材料」ではなく、課題を見つけるための道具として活用しましょう。
人材流出が止まらない原因は?

人材流出の理由は、大きく「社内の要因(内部要因)」と「社外の要因(外部要因)」に分けられます。
まずは代表的なポイントを整理しました。自分の会社にどの要因が当てはまるのかを確認してみてください。
内部要因(会社の中にある理由)
| 分類 | 主な内容 |
| 処遇・評価 | 賃金が相場より低い/昇給幅が不明確/評価の基準がわかりにくい |
| 人間関係 | 上司との相性が合わない/相談しにくい雰囲気/言語や文化の壁がある |
| キャリア | 役割が曖昧/将来像が見えにくい/教育が人に依存してしまう |
| 労働条件 | シフトの偏り/夜勤や危険作業が集中/休憩や休日の不公平 |
| 業務環境 | 紙やExcel中心で効率が悪い/情報共有が不足/古いIT環境が残っている |
内部要因は会社の制度や運用に関わる部分であり、改善できる余地が大きい領域です。
処遇や人間関係のように「社内で変えられること」が多く、気づかないうちに不満を積み上げてしまうところが特徴だといえるでしょう。
外部要因(会社の外にある理由)
| 分類 | 主な内容 |
| 賃金相場 | 近隣企業の賃上げ/入社ボーナスや高時給の求人 |
| 地域事情 | 都市部は競争が激しい/地方は応募者が少ない/通勤や家賃の負担が重い |
| 働き方 | リモートや副業の普及/自由度の高い働き方との比較 |
| 評判 | SNSや口コミで職場の雰囲気が広がる/小さな不満が外に漏れてしまう |
外部要因は市場や地域の状況に左右されるため、自社だけで完全にコントロールするのはむずかしい部分です。
ただし、賃金や制度の比較対象になりやすいため、理解しておくことが「なぜ人が辞めてしまうのか」を説明するうえで欠かせません。
人材流出で会社にどんな負担がかかる?

ここからは、人材流出が会社にどんな負担を生むのかを見ていきましょう。
お金や時間のロスにとどまらず、残った社員の働き方や会社の評判にまで広がる点に注意が必要です。
追加コストの発生
社員が退職すると、新しい人を採用するためにさまざまなお金がかかります。求人広告の掲載費や人材紹介会社への手数料、採用担当者が動く時間もその一つです。
さらに、入社した人が一人前になるまでは教育やOJTが欠かせず、その間の人件費も加わります。
つまり人材流出は「求人費+教育費+管理コスト」が同時に発生するため、会社の負担を大きくしてしまうのです。
採用単価と欠員コストの目安
もう少し具体的に考えると、負担は「採用単価」と「欠員コスト」に分けられます。
【採用単価(1人あたりの採用コスト)】
- 求人広告費
- 紹介手数料や派遣会社への費用
- 面接や調整にかかる担当者の人件費
【欠員コスト】
- 残業や応援要員にかかる追加費用
- 生産性の低下による売上減少や不良率の上昇
この2つを数字で見える化すると、人材流出が経営に与える影響をより実感しやすくなるでしょう。
業務効率の悪化
人が抜けると、その分の仕事は残った社員にのしかかります。残業や休日出勤が増えるのはもちろん、引き継ぎが不十分だと品質や安全面にも影響が出やすくなります。
さらに、辞めた人が持っていたノウハウが失われると、同じミスを繰り返すリスクも高まります。
こうした効率の低下は周囲の不満やストレスを増やし、次の人材流出を呼び込む悪循環へとつながっていくのです。
企業のイメージダウン
人材流出が続くと、外からは「長く働けない会社」という印象を持たれがちです。応募者は口コミサイトやSNSを確認するため、悪い評判が広がれば応募数は減り、採用がさらに難しくなるでしょう。
また、ハラスメントや職場環境の問題が離職理由として表に出れば、会社の社会的評価(レピュテーションリスク)にも影響します。信頼を損なうと、取引先やお客様との関係にも悪影響が及ぶおそれがあります。
今日からできる防止策(賃金・評価・育成・環境)

ここからは、人材流出を防ぐために会社がすぐに取り組める工夫を紹介します。むずかしい制度ではなく、身近な視点で4つの柱に分けて考えてみましょう。
賃金と評価の仕組みをそろえる
給与や昇給ルール、評価制度は、人材流出の大きな原因になります。とくに市場と比べて条件が不利だと、優秀な人ほど辞めやすくなるでしょう。
等級×評価×賃金テーブルの合わせ方
- 等級制度(役割の段階)と評価基準、給与テーブルを連動させる
- 「同じ評価を受けた人は、同じ基準で給与が決まる」仕組みをつくる
- 年1回だけでなく、昇給や昇格のタイミングを複数用意して納得感を高める
- 役割変更や等級アップに必要なスキルや行動を明示し、将来像を描きやすくする
評価を見える形にする
評価を数字だけで伝えると、不満が残りやすいものです。そこで、目標設定の方法(OKR)や定期的なフィードバックを取り入れると効果が出やすくなります。
- 目標は上司が一方的に決めるのではなく、社員と一緒に設定する
- 達成度を「3か月ごと」など短いサイクルで確認する
- 面談では「良かった点」と「改善点」を必ず両方伝える
- チーム内で進捗を共有できる仕組みを整えると納得感が増す
こうした積み重ねで「自分は会社にどう貢献しているのか」が見えやすくなり、離職の防止につながっていくでしょう。
育成と研修を計画的に進める
多くの人は「成長の機会がない」と感じた時に会社を辞めやすくなります。
だからこそ、入社直後のフォローから長期的な学びまで、計画的に用意しておくことが大切です。
- オンボーディング(受け入れ教育)は1か月・3か月・半年でフォローを設定する
- OJTだけでなく、オンライン研修や外部講座を組み合わせる
- キャリアのロードマップを提示し、「この会社でどのように成長できるのか」を示す
- 外国人社員には、専門研修とあわせて日本語や文化のサポートを並行する
環境をアップデートする
日常の小さな不便や古い仕組みをそのままにしておくと、それも人材流出の引き金になってしまいます。
慣れたやり方を続けるのではなく、効率よく仕事ができる環境を整えていきましょう。
- 紙とExcel中心の二重管理をやめ、クラウドツールに移行する
- 社内チャットやタスク管理ツールで連絡のスピードを上げる
外国人採用を取り入れる
人材流出を完全に防ぐのは難しいため、新しい採用ルートを持っておくことも重要です。外国人採用はそのひとつの方法といえます。
- 自社で就労が可能な在留資格を確認する
- 求人サイトや紹介会社を比較し、適切な採用ルートを選ぶ
- 入社後は日本語研修や生活支援を整え、安心して働ける環境をつくる
▼外国人採用の成功事例をまとめた資料を無料でダウンロードできます▼
導入企業の体験や実際の採用ストーリーを知りたい方におすすめです。
【データで見る転職市場】業界・地域・賃金はどう変わっている?

ここからは、人材流出と関わりの深い「転職市場の動き」をデータで見ていきましょう。
感覚に頼るのではなく、根拠を持って自社の課題を考えることが大切です。
業界で見る人の動き
転職者数や離職率は業界によって大きく異なります。直近の統計では、次のような傾向が出ています。
- 宿泊業・飲食サービス業:入職も離職も多く、人の出入りが激しい業界。離職率が30%を超える年もある
- 卸売・小売業、サービス業:パートタイム労働者の離職率が高く、安定して働いてもらうのが難しい傾向
- 製造業や電気・ガス業:比較的安定しており、流出率は低め。長期雇用を前提とした人材確保がしやすい
また、年収の水準が低めの業界は流出リスクが高くなりやすいため、待遇改善や評価制度の工夫が欠かせません。
地域による差
地域ごとの採用環境では、有効求人倍率(1人あたりの求人件数)に大きな違いがあります。2025年7月(令和7年)のデータでは、全国平均は 1.22倍 でした。
- 高い地域:福井 1.72倍、石川 1.60倍 → 地方では人手不足が続き、応募者が集まりにくい
- 低い地域:神奈川 1.04倍、兵庫 0.97倍 → 大都市圏では応募者が多いものの、企業間の競争は激しい
このように、同じ条件で求人を出しても「どの地域で採用するか」によって難易度は変わります。自社の地域特性を理解することが、採用計画を立てるうえで欠かせないポイントです。
参考:厚生労働省 一般職業紹介状況(令和7年7月分)について
人手不足が深刻な都道府県について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
最低賃金の動き
2025年度(令和7年度)の最低賃金は全国加重平均で 1,121円 となり、過去最大の66円引き上げが行われました。これにより、すべての都道府県で最低賃金が1,000円を超えることになります。
- 最高額:東京 1,226円、神奈川 1,225円
- 最低額:宮崎・沖縄など 1,000円台前半
- 特徴:地域間の差は依然として大きく、150円以上の開きがある
最低賃金の引き上げは人件費の負担増につながるだけでなく、人材流出にも直結します。
とくに地方の企業は都市部の高い水準に人材を奪われやすいため、給与以外の魅力(柔軟な働き方や成長の機会など)を示す工夫が重要になるでしょう。
転職や求職の動きが増えやすい時期
採用計画を立てるうえで、応募が増えるタイミングを知っておくことは大きなヒントになります。
総務省の労働力調査によると、転職者数は年間を通して変動があり、とくに「4月」と「10月」に増えやすいことがわかっています。
- 4月:異動や評価のタイミングに合わせて動く人が多い
- 10月:下半期のスタートに合わせた転職が増える
- 1〜3月:賞与を受け取ってから辞めるケース
- 7月:夏の賞与後に動くケース
こうした傾向を意識しておくと、求人を出す時期や条件設定に役立ちます。
採用のコツ
- 応募が増える1か月以上前から求人準備をしておく
- 仕事内容や待遇を工夫し、競合との差別化を意識する
- 自社サイトやSNSでも情報を発信し、露出を増やす
引用:総務省 労働力調査(詳細集計)2025年(令和7年)4~6月期平均
よくある質問(FAQ)

Q. 人材流出のサインはどうやって気づけますか?
A. 退職希望が出る前に「小さな変化」に目を向けることが大切です。
たとえば、欠勤や遅刻が増える、会話が減る、仕事への意欲が落ちるといった行動はよくある前兆です。さらに、口コミサイトへの投稿や社内アンケートの回答内容からも不満を察知できる場合があります。
早めに気づければ、対話やサポートを通じて離職を防げる可能性が高まります。
Q. なぜ優秀な人ほど流出しやすいのですか?
A. 成長意欲が高いため、環境が合わないとすぐに動くからです。
優秀な人材は市場価値が高く、よりよい条件や挑戦できる環境を求めて転職しやすい傾向があります。
逆にいえば、評価の透明性を高めたり、キャリアパスを明確に示したりすることで、定着率を上げる余地があるでしょう。
Q. 人材流出によるコストはどれくらいかかりますか?
A. 採用費だけでなく、生産性や評判への影響を含めると数百万円規模になることもあります。
欠員補充にかかる広告費や紹介料、引き継ぎの停滞による業務効率の低下などが代表例です。さらに「人が定着しない会社」というイメージが広がれば、採用力の低下にもつながります。
数字では見えにくい部分が多いものの、経営に直結する重要な課題といえるでしょう。
Q. 防止策はまず何から始めればいいですか?
A. 賃金・評価・働きやすさの3点を見直すことが第一歩です。
相場に見合った給与かどうか、成果をきちんと伝えられる仕組みがあるか、そして日常の働きやすさを改善できているか。この3つをそろえるだけでも流出リスクは大きく下げられます。
制度改定が難しい場合でも、定期面談や感謝の言葉を伝えるなど、小さな工夫から始めることが効果的です。
Q. 外国人の採用は人材流出防止につながりますか?
A. 人材の多様化は、流出リスクを下げる一つの方法です。
国内だけでは人材を確保しにくい状況もあるため、外国人採用を検討する企業は増えています。文化や言語の壁はあるものの、支援体制を整えれば長期的に定着しやすい人材となるでしょう。
求人チャネルを広げること自体が、人材流出で減った人数を補う有効な手段になります。
さいごに
人材流出は、どんな職場でも起こり得るものです。だからこそ「測る」「気づく」「直す」の流れを回し、少しずつでも改善を重ねていくことが大切になります。
賃金や評価を整え、安心して働ける土台を築いていきましょう。
採用の幅を広げる意味でも外国人採用は有効な方法です。
言葉のサポートや就労ルールを押さえれば、戦力として活躍できるまでの時間も短縮できます。まずはできることから一歩を踏み出してみませんか?
人材流出を防ぎたいけれど、外国人採用にも迷いを抱く担当者の方へ
ガイダブルジョブスでは、外国人採用の基礎を整理できる『在留資格ガイド』をご用意しています。特定技能制度のしくみ、外国人留学生の働き方、複数の就労ビザの違いに加え、不法就労のリスクと罰則まで幅広く解説しました。
外国人採用に踏み出したいけれど、情報が散らばっていて不安…という方におすすめです。最新動向を知っておくことで、人材流出を防ぐ判断力にもつながります。ぜひチェックしてみてください。






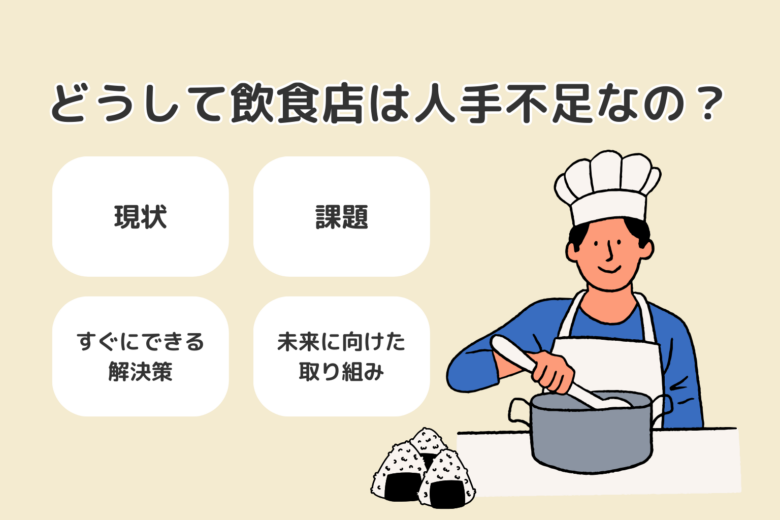


-7-780x520.png)






-2-780x520.png)



-2-780x520.jpg)

-3-780x520.png)

