【2026年版】外国人採用の助成金申請ガイド|申請手順や注意点をわかりやすく
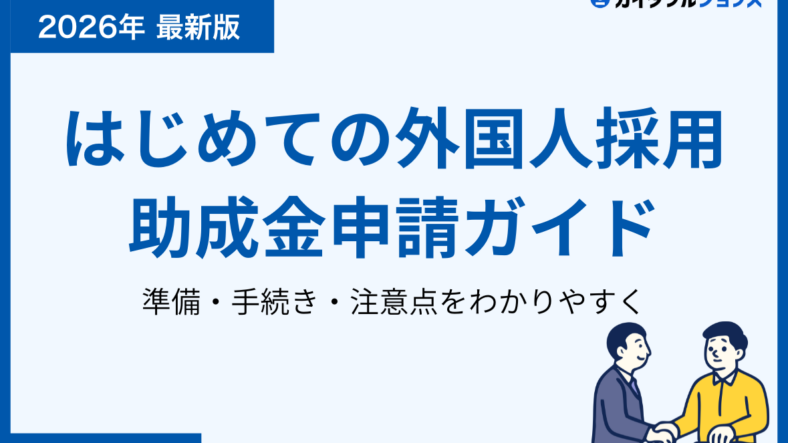
日本では深刻な人手不足が続く中、外国人材の採用を後押しする助成金・補助金制度が今、企業から注目を集めています。
採用や育成にかかるコストを抑えながら、職場環境の整備や定着支援までサポートできるのが大きな魅力です。
一方で、「手続きが難しそう」「最新情報を追いきれない」と感じる担当者も多いのが現実。
ですが、正しく知れば助成金は採用コストを抑えて人材を確保するチャンスになります。
本記事では、2025年最新の外国人雇用助成金の中から、実際に多くの企業が活用している「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を例に、申請の流れから書類作成のポイントまで、実践的に解説します。
💡 こんな方におすすめ
✓ 外国人採用を検討している人事・経営者
✓ 助成金申請の具体的な手順を知りたい担当者
✓ 採用コストを抑えたい中小企業の決裁者
目次
第1章:2025年版 外国人雇用で活用できる主要助成金3選
まず、外国人労働者の採用・定着に活用できる代表的な助成金を3つご紹介します。
①人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
【助成内容】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成率 | 1/2(生産性要件を満たせば2/3) |
| 上限額 | 57万円(生産性要件達成時:72万円) |
【主な対象経費】
✓ 通訳費用、翻訳機器の導入費用
✓ 社内マニュアルの多言語化費用
✓ 外国人労働者の相談体制構築費用
✓ 就業規則等の多言語化費用
【対象となる在留資格】
雇用保険被保険者となる外国人労働者(「外交」「公用」「特別永住者」を除く)
💡 この助成金がおすすめな企業
✓ 外国人材の受け入れ環境をこれから整備したい
✓ 多言語対応の社内体制を構築したい
✓ 初めて外国人雇用助成金を申請する
②キャリアアップ助成金(正社員化コース)
【対象】有期雇用労働者等を正規雇用に転換した事業主
【助成内容】
| 転換パターン | 助成額(中小企業) |
|---|---|
| 有期 → 正規 | 80万円 / 1人あたり |
| 無期 → 正規 | 40万円 / 1人あたり |
※重点支援対象者の場合。それ以外は1期のみで40万円/20万円
【外国人労働者への適用】
適法に就労できる在留資格を持ち、雇用保険に加入している労働者が対象。ただし、技能実習生など帰国を前提とする在留資格は対象外。特定技能外国人や専門的・技術的分野の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)を持つ外国人労働者は対象となります。
③地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)
【対象】 雇用機会が特に不足している地域等で、事業所の設置・整備を行い、地域求職者等を雇用する事業主
【助成内容】
設置・整備費用と増加した労働者数に応じて 48万円〜800万円
【外国人労働者への適用】
地域の求職者として、適法に就労可能な在留資格を持つ外国人労働者も対象となり得ます。
参照元:厚生労働省「地域雇用開発助成金」
④その他の助成金・補助金制度について
上記以外にも、都道府県や市区町村が独自に設けている外国人雇用関連の補助金制度があります。
詳しい助成金一覧については、以下の記事をご覧ください。
第2章:助成金申請前の準備 ― 成功のための3つのチェックポイント
助成金申請をスムーズに進めるために、事前に確認すべき重要なポイントを解説します。
ポイント1. 自社の課題と助成金の目的を明確にする
助成金は「採用コストを抑える手段」ではなく、「外国人労働者が活躍できる環境を整備するための支援制度」です。
まず、自社が抱える課題を明確にしましょう。
| ⚠️ よくある課題例 |
| • 外国人労働者とのコミュニケーションに課題がある |
| • 社内マニュアルや規程が日本語のみで、外国人労働者が理解しにくい |
| • 外国人労働者の定着率が低い |
| • 相談窓口や支援体制が整っていない |
これらの課題を解決する手段として助成金を活用することで、申請の説得力が高まり、採択率も向上します。
ポイント2. 対象となる外国人労働者の在留資格を確認する
助成金ごとに、対象となる在留資格の条件が異なります。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の場合
適切な助成金を選んだら、申請書類を作成します。これは審査の根幹となるとても重要なプロセスです。
| 項目 | 内容 |
| 対象となる外国人 | 雇用保険の被保険者となる外国人労働者 |
| 対象外 | 「外交」「公用」「特別永住者」 |
| 主な対象在留資格 | 技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務 など |
確認方法
- 外国人労働者の在留カードを確認
- 在留資格欄に記載されている資格名をチェック
- 助成金の対象資格と照合
参照元:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労 環境整備助成コース)ガイドブック」
ポイント3. 社内体制を整える
助成金申請から受給までには、複数の部署との連携が必要です。
体制整備のポイント:
✓ 申請担当者を明確にする(人事部、総務部など)
✓ 経理担当者と連携し、経費の証拠書類を確実に保管
✓ 事業部門の責任者と計画内容をすり合わせ
✓ 必要に応じて社会保険労務士など専門家に相談
💡 社内での情報共有が成功のカギ
助成金の目的や計画内容を経営層や関連部署と共有することで、スムーズな計画実行が可能になります。
第3章:人材確保等支援助成金の申請手順【完全ガイド】
ここからは、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を例に、実際の申請手順を詳しく解説します。
申請から受給までの全体の流れ

重要なポイント:
- 助成金は後払い(※先に経費を支出する必要があります)
- 計画認定前に実施した取り組みは対象外
- 申請期限を厳守する
STEP 1:就労環境整備計画の作成
計画に含めるべき内容
1. 現状の課題
- 外国人労働者の受入れ状況
- 現在抱えている課題(コミュニケーション、労務管理など)
2. 具体的な取り組み内容
- 実施する整備内容を明確に記載
- 例:社内マニュアルの英語・ベトナム語翻訳、通訳機器の導入など
3. 実施スケジュール
- いつまでに何を実施するか、具体的な期日を記載
4. 必要な経費
- 見積書に基づいた具体的な金額
5. 期待される効果
- 定量的な目標(離職率〇%削減、労働生産性〇%向上など)
計画書作成の具体例
ケーススタディ:製造業A社の場合
※本事例は、厚生労働省の公式ガイドブックに基づく架空のシミュレーションです。実際の企業事例ではありません。
【企業情報】
• 業種:製造業
• 従業員数:50名(うち外国人労働者10名)
• 在留資格:技能実習、特定技能
【抱えている課題】
• 安全マニュアルが日本語のみで、外国人労働者が正確に理解できていない
• 業務上の質問や相談を日本語で行う必要があり、コミュニケーションに時間がかかる
• 過去1年で外国人労働者2名が早期退職
【計画内容】
| 取り組み内容 | 実施時期 | 経費 |
|---|---|---|
| 安全マニュアルの英語・ベトナム語翻訳(外部委託) | 認定後1ヶ月 | 30万円 |
| 通訳機器(ポータブル翻訳機)5台の導入 | 認定後2ヶ月 | 15万円 |
| 外国人労働者向け相談窓口の設置・研修 | 認定後3ヶ月 | 10万円 |
| 就業規則の多言語化(外部委託) | 認定後4ヶ月 | 25万円 |
| 合計 | 6ヶ月以内 | 80万円 |
【期待される効果】
• 安全に関する理解度向上により、労災リスク50%削減
• 外国人労働者の離職率を30%削減
• コミュニケーション時間の短縮により、労働生産性10%向上
STEP 2:計画書の提出と必要書類
提出先
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局
提出方法
- 窓口持参
- 郵送
- 電子申請(雇用関係助成金ポータル)← 推奨
| 書類名 | 入手先 | 備考 |
| ①就労環境整備計画書 | 厚生労働省HP | 所定様式 |
| ②外国人労働者名簿 | 自社作成 | 在留資格、雇用期間等を記載 |
| ③事業所の概要がわかる資料 | 自社 | 会社案内、登記簿謄本など |
| ④見積書 | 外部業者 | 実施予定の取り組みに関する見積 |
| ⑤労働保険関係成立届等 | 労働局 | 労働保険加入の証明 |
📌 電子申請を活用すると便利!
厚生労働省の「雇用関係助成金ポータル」から24時間申請可能。書類の郵送や窓口訪問の手間が省けます。
STEP 3:計画書を記入する
計画書を提出し、労働局から認定を受けた後の手続きと、計画書作成時に押さえるべきポイントを解説します。
計画書作成時の重要ポイント
計画書を作成する際は、以下の点に特に注意しましょう。
✅ 具体性を重視
【×】「マニュアルを整備する」
【○】「50ページの安全マニュアルを英語・ベトナム語に翻訳」
✅ 数値目標を明記
【×】「定着率を向上させる」
【○】「離職率を30%削減」
✅ 実施方法を明確に
誰が、いつ、どのように実施するのかを明記
✅ 費用の根拠を示す
見積書を添付し、金額の妥当性を証明
計画書の記入例について
実際の計画書の様式や具体的な記入例については、厚生労働省の公式ガイドブックをご確認ください。
▼ 計画書の様式・記入例はこちら
厚生労働省:外国人労働者就労環境整備助成コース記入マニュアル
また、申請様式一式はこちらからダウンロードできます。
| 様式名 | Word・Excel形式 | PDF形式 | |
| 様式a-1号 | 就労環境整備計画(変更)書 | Word[109KB][95KB] | |
| 様式a-1号 別紙1 | 導入する「雇用労務責任者の選任」及び「就業規則等の多言語化」の概要票 | Word[30KB][29KB] | |
| 様式a-1号 別紙2 | 導入する「苦情・相談体制の整備」、「一時帰国のための休暇制度の整備」及び「社内マニュアル・標識類等の多言語化」の概要票 | Word[29KB][34KB] | |
| 様式a-1号 別紙3 | 事業所における外国人労働者名簿 | Word[30KB][31KB] | PDF[67KB][587KB] |
| 様式a-2号 | 事業所確認票 | Word[37KB][37KB] | PDF[73KB][1.1MB] |
| 様式a-6号 | 支給申請書 | Word[50KB][44KB] | |
| 様式a-6号 別紙1 | 導入した「雇用労務責任者の選任」及び「就業規則等の多言語化」の概要票 | Word[30KB][28KB] | |
| 様式a-6号 別紙2 | 導入した「苦情・相談体制の整備」、「一時帰国のための休暇制度の整備」及び「社内マニュアル・標識類等の多言語化」の概要票 | Word[29KB][32KB] | |
| 様式a-6号 別紙3 | 雇用労務責任者による面談結果一覧表 | Word[21KB][25KB] | PDF[48KB][366KB] |
| 例示様式1 | 在留資格を証明する書面(申立書) | Word[19KB][19KB] | PDF[62KB][60KB] |
| 例示様式2 | 労働者10人未満の場合の就業規則への添付書面(申立書) | Word[18KB][18KB] | PDF[45KB][45KB] |
引用:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)様式
STEP 4:計画の実行と証拠書類の保管
計画が認定されたら、認定された計画に基づいて環境整備を実施します。この段階が最も重要で、実施内容と証拠書類の管理が助成金受給の成否を分けます。
実施期間
認定された計画期間内(6ヶ月以内)に、すべての就労環境整備措置を完了させる必要があります。
実施時の重要な注意点
1. 計画認定後に実施する
⚠️ 計画認定前に発注・購入・契約したものは助成金の対象外となります。
❌ NG例
• 計画書提出前に翻訳会社と契約してしまった
• 認定通知が届く前に通訳機器を購入してしまった
✅ OK例
• 認定通知を受領してから、翻訳会社と契約
• 認定後に通訳機器の発注手続きを開始
2. 証拠書類を必ず保管する
助成金の支給申請時には、実施内容と経費を証明する書類の提出が必須です。
保管すべき証拠書類:
- 契約書
- 発注書
- 納品書
- 請求書
- 領収書
- 振込明細書
- 実施状況がわかる写真
- 研修実施報告書・参加者名簿(研修を実施した場合)
- 翻訳前後のマニュアル(多言語化を実施した場合)
💡 証拠書類管理のコツ
• 専用のファイルやフォルダを作成し、取引ごとに即座に保管
• 紙の書類はスキャンしてデジタルコピーも作成
• 経理担当者と連携し、二重チェック体制を構築
3. 計画どおりに実施する
認定された計画書の内容から変更する場合は、必ず事前に労働局に相談し、変更承認を得る必要があります。
変更が必要になるケース例:
- 翻訳会社を変更したい
- 購入予定の機器の機種を変更したい
- 実施スケジュールを変更したい
- 経費の金額が大幅に変わる
⚠️ 無断で変更すると、助成金の減額や取消しにつながる可能性があります。
保管すべき証拠書類の具体例
| 取り組み内容 | 必要な証拠書類 |
| マニュアル翻訳 | • 翻訳会社との契約書 • 翻訳前のマニュアル(原本) • 翻訳後のマニュアル • 請求書 • 領収書または振込明細 |
| 通訳機器購入 | • 購入先の見積書 • 発注書 • 納品書 • 請求書 • 領収書または振込明細 • 機器の写真(納品時) |
| 研修実施 | • 研修カリキュラム • 参加者名簿(署名入り) • 研修実施報告書 • 研修時の写真 • 講師への支払証明 |
| 相談窓口設置 | • 窓口設置の社内通知文書 • 担当者の任命書 • 多言語対応マニュアル • 相談記録簿(様式) |
💡 証拠書類は「多すぎる」くらいがちょうどいい?!
審査で追加資料を求められることもあります。「これは必要ないかも」と思うものでも、関連する書類はすべて保管しておくのも手です。
参照元:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労 環境整備助成コース)ガイドブック」
STEP 5:支給申請と実績報告
すべての就労環境整備措置を実施したら、実施完了日から2ヶ月以内に支給申請を行います。
支給申請のタイミング
申請期限: 就労環境整備措置の実施完了日の翌日から起算して2ヶ月以内
例:
・実施完了日:令和7年9月30日
・申請期限:令和7年11月30日まで
⚠️ 期限を過ぎると申請できなくなるため、必ず期限を厳守してください。
| 書類名 | 内容 |
| ①支給申請書 | 所定様式(厚生労働省HPからダウンロード) |
| ②実績報告書 | 実施内容、実施期間、効果等を具体的に記載 |
| ③経費の証拠書類 | 契約書、請求書、領収書、振込明細等の原本またはコピー |
| ④実施状況がわかる資料 | 翻訳後のマニュアル、機器の写真、研修実施報告書等 |
| ⑤外国人労働者名簿 | 支給申請時点の最新版 |
| ⑥離職状況を証明する書類 | 雇用保険被保険者資格喪失届等 |
実績報告書の記載ポイント
実績報告書では、計画どおりに実施したこととその効果を具体的に記載する必要があります。
STEP 6:助成金の受給
支給申請後、労働局による審査が行われ、要件を満たしていることが確認されると、支給決定通知書が送付されます。
審査期間
審査期間の目安: 申請から2〜3ヶ月
ただし、申請が集中する時期や書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることがあります。
審査内容
労働局では、以下の点を中心に審査が行われます。
審査される主な項目:
- 申請書類の記載内容に不備や矛盾がないか
- 提出された証拠書類が適切か
- 計画どおりに実施されたか
- 経費の支出が適正か
- 離職率の要件を満たしているか
- 不正受給の疑いがないか
追加書類の提出を求められる場合
審査の過程で、内容の確認や証明のために追加書類の提出を求められることがあります。
よくある追加書類の例:
- 実施状況を示す写真の追加
- 契約内容の詳細を示す資料
- 支払いの流れを示す通帳のコピー
- 翻訳の品質を確認できる資料
労働局から連絡があった場合は、速やかに対応しましょう。
支給決定と振込
審査が完了し、支給が決定されると・・・
【1. 支給決定通知書が送付される】
- 支給決定の旨
- 支給額
- 振込予定時期
などが記載されています。
【2. 指定口座に助成金が振り込まれる】
支給決定後、通常1〜2週間程度で指定した銀行口座に助成金が振り込まれます。
受給後の注意点
1. 書類の保管義務
助成金受給後も、5年間は関係書類を保管する義務があります。
保管すべき書類:
- 申請書類一式
- 証拠書類(領収書、契約書等)
- 実施状況を示す資料
- 支給決定通知書
2. 事後調査への対応
受給後も、労働局による事後調査が行われる場合があります。
調査の際は、保管している書類を提示し、誠実に対応してください。
3. 不正が発覚した場合のペナルティ
もし受給後に不正が発覚した場合、以下のペナルティが科されます:
- 助成金の全額返還
- 延滞金・加算金(不正受給額の最大2割)
- 企業名の公表
- 今後5年間の助成金申請資格停止
- 悪質な場合は刑事告発
⚠️ 重要:助成金は「後払い」です
助成金は、環境整備を実施し、経費を支払った後に受給できる「後払い」の制度です。そのため、実施期間中は自己資金で経費を負担する必要があります。
資金計画を立てる際は、この点を必ず考慮してください。
参照元:厚生労働省「雇用関係助成金の不正受給への対応について」
まとめ:外国人雇用助成金を活用して、持続可能な採用体制を構築しましょう
本記事では、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)を中心に、申請の具体的な手順から注意点まで、実践的な情報をお伝えしました。
助成金申請を成功させる最大のポイントは、「助成金ありき」ではなく、「外国人労働者が働きやすい環境づくり」を第一に考えることです。
助成金は、その取り組みを支援するためのツールに過ぎません。
外国人労働者の受入れ環境整備は、一朝一夕にできるものではありません。
しかし、助成金を活用することで、その第一歩を着実に踏み出すことができます。
本記事が、貴社の外国人採用および助成金活用の成功に少しでもお役に立てれば幸いです。
外国人採用の準備、順調ですか?
助成金の活用方法は理解できても、「結局、何から手をつければいいんだろう…」と感じていませんか?
外国人材の採用には、助成金申請だけでなく、在留資格の確認、受入れ体制の整備、社内ルールの策定、必要書類の準備など、同時並行で進めるべきタスクが数多く存在します。
情報収集を進めれば進めるほど、やるべきことが増えていき、「何を優先すればいいのか分からない」「重要な手続きを見落としていないか不安」という声を多くの担当者様からいただきます。
そんな方のために、ガイダブルジョブスでは「外国人採用の事前準備todoリスト」を無料で配布しています。
本記事で学んだ助成金の知識と合わせて、このtodoリストを活用すれば、外国人採用の全体像が見えてきます。
「やるべきことが多すぎて混乱している」「本当にこの進め方で大丈夫か不安」という方こそ、ぜひ一度このリストで現在の準備状況を確認してみてください。
※本記事の内容は、公開時点(2025年11月)における厚生労働省等の公的情報をもとに作成しています。
助成金制度の内容は年度や地域によって変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず最新の公式資料を確認のうえ、各都道府県労働局や助成金の専門家にご相談ください。


-3-780x520.jpg)


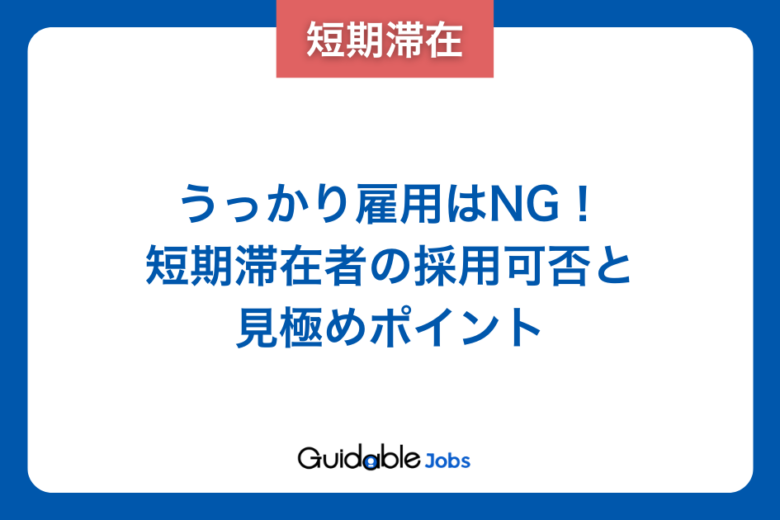





-2-780x520.png)


-7-780x520.png)
-2-780x520.png)
-2-780x520.png)
-1-780x520.png)
