ただの義務じゃない!特定技能の生活オリエンテーションが定着率を左右

外国人採用、特に特定技能制度の活用において、受け入れ企業が必ず実施しなければならない「生活オリエンテーション」。これは法律で定められた義務であると同時に、外国人人材が日本で安心して働き、定着するための重要な第一歩です。
しかし、「具体的に何をすればいいのか」「どこまでサポートすべきか」といった疑問をお持ちの採用担当者の方も少なくありません。
本記事では、特定技能外国人の生活オリエンテーションについて、法的根拠に基づき、その基本情報から具体的な実施項目、注意点までを網羅的かつ簡潔に解説します。
目次
特定技能の生活オリエンテーションはなぜ重要?
特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、彼らが日本で安定的かつ円滑な生活を送れるよう、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援をおこなうことが義務付けられています。生活オリエンテーションは、この支援の中核をなすものです。
法的義務
出入国管理及び難民認定法に基づき、特定技能所属機関は支援計画を作成し、それに従って支援をおこなう必要があります。生活オリエンテーションの実施は、この支援計画に盛り込むべき必須事項です。(参照:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」)
定着の向上
日本のルールや慣習が分からないまま生活を始めると、外国人人材は多くの不安やストレスを抱えることになります。これが早期離職の原因となるケースも少なくありません。適切なオリエンテーションは、彼らの不安を解消し、日本での生活基盤を整え、結果として職場への定着率を高める効果が期待できます。
生活オリエンテーションの基本情報

オリエンテーションの実施にあたり、守るべき基本的なルールが定められています。
(参照:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」)
【チェックリスト】法律で定められた10の実施項目
法律では、オリエンテーションで説明すべき項目が具体的に定められています。以下のチェックリストを活用し、漏れなく実施してください。
▼生活オリエンテーション実施項目リスト
1. 金融機関の利用方法
- 預貯金口座の開設方法、利用方法、手数料など。
- 給与振込のために必要な情報であることを伝えます。
2. 医療機関の利用方法等
- 日本の医療制度の概要、病院のかかり方(診療科の選び方など)、医療費について。
- 企業の業種(例:建設業)によっては、労災保険の対象となる業務災害の事例なども具体的に説明すると、より実践的です。
3. 交通ルール
- 自転車のルール(二人乗り禁止、飲酒運転禁止など)、公共交通機関の利用方法、ICカードの購入・利用方法。
- 罰則についても明確に伝えます。
4. 生活ルール・マナー
- ゴミの分別・収集日、騒音など近隣住民とのトラブルを避けるための注意点。
- 共同生活のルール(寮などがある場合)。
5. 生活必需品の購入方法等
- 近隣のスーパーマーケット、ドラッグストア、家電量販店の場所や営業時間など。
6. 日本の気候・習慣に応じた服装等
- 季節ごとの気候の特徴と、それに適した服装について。
7. 防災・防犯、急病など緊急時の対応
- 地震・台風などの災害情報入手方法、避難場所の確認。
- 警察(110番)、消防・救急(119番)への連絡方法。
8. 出入国在留管理庁への届出等
- 氏名や所属機関の変更、契約終了時などに必要な手続きについて。
- 手続きを怠った場合の罰則についても説明します。
9. 労働基準法等の労働関係法令に関する情報
- 労働契約の内容、労働時間、休日、賃金、時間外労働など、自身の労働条件について説明します。
- 労働基準監督署などの相談窓口も知らせます。
10. 相談・苦情の窓口
- 仕事や生活で困った際に相談できる、社内および公的機関の窓口の連絡先を伝えます。
(参照:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」)
実施方法は2つ|自社実施 vs 外部委託

生活オリエンテーションを含む支援業務は、自社でおこなう方法と、国の登録を受けた「登録支援機関」に全部または一部を委託する方法があります。
【外部委託にかかる費用】 登録支援機関への委託費用は、支援内容によって異なります。生活オリエンテーション単体での依頼は少なく、月々の支援業務とセットになっている場合がほとんどです。一般的には、特定技能外国人1名あたり月額2万円~5万円程度が目安となりますが、必ず複数の機関に見積もりを取り、サポート内容と費用を比較検討することをお勧めします。
オリエンテーションで失敗しないための3つの注意点

義務を果たすだけでなく、効果的なオリエンテーションにするためには、以下の3点を意識することが重要です。
専門用語を避け、分かりやすい言葉で伝える
「住民票」「社会保険」といった行政手続きの言葉も、外国人にとっては難解な専門用語です。図やイラストを用いたり、「市役所でもらう、あなたがここに住んでいることを証明する紙です」のように、簡単な言葉に置き換えたりする工夫が求められます。
一方的に話すだけでなく、質疑応答の時間を設ける
説明の合間や最後に、必ず質問の時間を取りましょう。外国人が母国語で質問できるよう、通訳を手配することが理想です。「何か質問はありますか?」だけでなく、「ここまでで分からない言葉はありましたか?」など、具体的な問いかけをすることで、質問しやすい雰囲気をつくることができます。
実施後のフォローアップ体制を整える
一度の説明ですべてを理解・記憶することは困難です。オリエンテーション後も、定期的に面談の機会を設けたり、困ったときにいつでも相談できる窓口を明確にしたりしておくことが、彼らの安心につながります。オリエンテーション資料をいつでも見返せるように、データや書面で渡しておくことも有効です。
まとめ

特定技能外国人の生活オリエンテーションは、法律上の義務であると同時に、彼らが日本社会と企業の一員として円滑にスタートを切るための不可欠なプロセスです。
本記事でご紹介した項目や注意点を参考に、一つひとつ丁寧な支援をおこなうことが、採用担当者の負担軽減だけでなく、外国人人材の活躍と定着、ひいては企業の成長へとつながります。自社のリソースに不安がある場合は、専門家である登録支援機関への委託も有効な選択肢としてご検討ください。
【無料ダウンロード】外国人採用ハンドブック|担当者必携の完全ガイド
「法律のことは理解したが、募集や面接、採用後のフォローは具体的にどうすれば…?」 外国人採用のプロセスは多岐にわたり、担当者様の不安は尽きません。
本資料では、採用計画から募集・面接のコツ、在留資格の見極め方、入社後の労務管理や定着支援まで、外国人採用の全プロセスをAtoZで網羅的に解説しています。
Guidableが持つノウハウを凝縮したこの一冊があれば、初めての外国人採用でも自信を持って取り組めます。貴社の採用活動を基礎から支える、まさに「お守り」のようなハンドブックです。
▼今すぐ資料をダウンロードして、採用成功へのロードマップを手に入れてください!▼


-30-780x520.png)

-19-780x520.jpg)
-17-780x520.png)
-8-780x520.png)



-2-780x520.png)


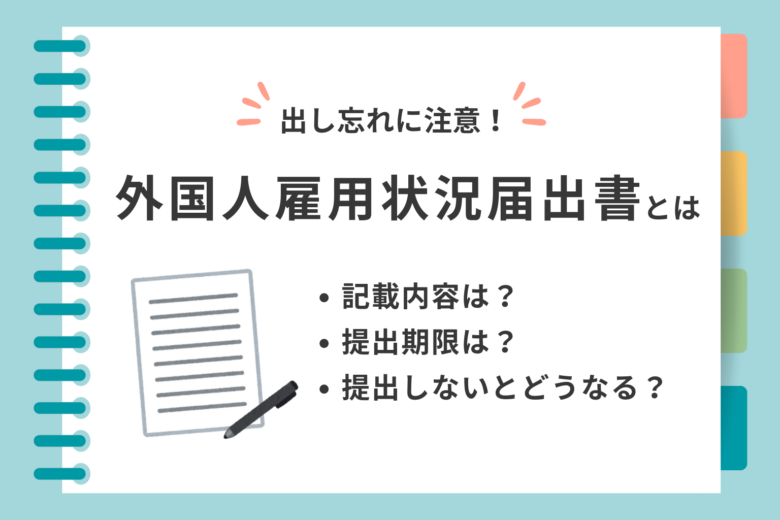
-3-780x520.png)

のコピー-780x520.png)

