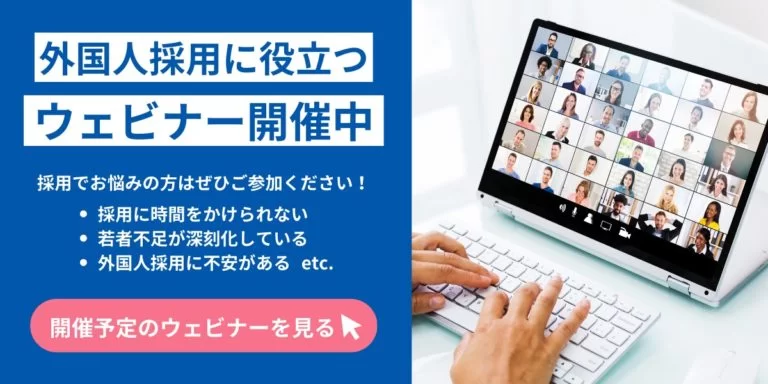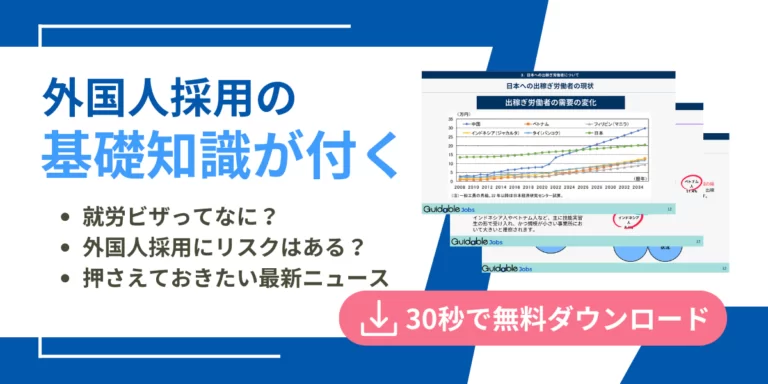外国人の従業員との間で問題になることは? ビザの確認、相手の文化理解、受け入れ側の英語学習、日本語サポートなどについて

「外国人採用を始めたいけれど不安がある」「外国人従業員を雇用しても、定着率が悪いと意味がないため、成功させるための社内マニュアルをつくりたい」今回はこのような悩みを抱えている方へ向けて、外国人従業員を受け入れる際のポイントや外国人従業員の受け入れマニュアルに必須の内容を説明します。
この記事を読むことで、外国人従業員を受け入れる流れが把握できます。また同時に外国人従業員を受け入れる際のポイントや注意点について、事前に把握しておくことができます。
目次
ビザの確認はなぜ必要なの?
もしみなさまの会社で外国人従業員を採用することが決まり、業務内容が確定したら、その方が現在持っている在留資格(=一般的にいう「ビザ」)を確認する必要があります。
なぜならば、外国人の方が日本に在留するための資格には多くの種類があり、在留資格それぞれに働くことのできる職種や業務内容が決まっている場合が多いからです。
もしその外国人の方の持っている在留資格と、採用した仕事内容や職種が合わない場合は、在留資格を変更する手続きを行う必要があるわけです。かならず確認しておきましょう。
就労できるビザは?
一般的にビザといわれる在留資格の中で、日本で就労することができるものは以下の通りです。
- 外交:外交交渉・日本滞在中の自国民の法的な保護や支援などをおこなう者が取得する
- 公用:在留資格「外交」を取得している外国人の付添人や公務員が取得する
- 教授:日本の大学や高等専門学校などでの研究・指導をおこなう者が取得する
- 芸術:芸術の向上を目的とした活動や芸術の指導をおこなう者が取得する
- 宗教:布教やその他宗教上の活動をおこなう者が取得する
- 報道:外国のテレビ局や新聞社などの報道機関関係者が取得する
- 高度専門職(1号/2号):就労可能ないずれかの在留資格(外交・公用・国際業務・特定技能・技能実習以外)を持つ者のなかでスキルが高いと評価された者が取得する
- 経営・管理:日本での開業や投資、経営、事業の管理などをおこなう者が取得する
- 法律・会計業務:法的な資格を持ち、法律や会計に係る活動をおこなう者が取得する
- 医療:法的な資格を持ち、医療に係る活動をおこなう者が取得する
- 研究:公的機関・民間企業のや研究部門に所属する者が取得する
- 教育:日本の小・中学校、高等学校などで教育をおこなう者が取得する
- 技術・人文知識・国際業務:外国の文化に基づく知識・技術を要する活動をおこなう者が取得する
- 企業内転勤:海外事業所から日本へ転勤する職員が取得する
- 介護:介護や介護の指導をおこなう者が取得する
- 興行:公衆に対して演じたり演奏するなどパフォーマンスをおこなう者が取得する
- 技能:外国で考案された技術で熟練したスキルを発揮できる者が取得する
- 特定技能(1号/2号):一定水準以上の技能や日本語能力を持ち、決められた産業で限定された業務内容をおこなう者が取得する
- 技能実習(1号/2号/3号):出身国での習得が難しく、日本で技能を習得・習熟・熟達する者が取得する※廃止(新制度創設)予定
就労できないビザとは?

日本に在留することができるビザの中には、日本の企業では就労できないものがあります。以下のビザを取得している場合は、あらためて日本で就労可能なビザを取得する必要があります。
- 文化活動:日本文化の研究者や専門家の指導を受ける者など
- 短期滞在:観光、会議、親族・知人の訪問など
- 留学:大学、短期大学、高等専門学校、中学校、小学校、専修学校、などの学生
- 研修:技術・技能または知識習得のための研修生
- 家族滞在:在留資格をもっている外国人が扶養する配偶者、子供
在留カードのここを見る!
在留カードとは企業に勤務する場合に外国人に交付されるカードのこと。
観光での滞在や不法滞在者には、原則として交付されないものです。ただ在留カードを持っていても日本で就労できない場合もあるので、かならず内容をチェックしておく必要があります!
日本で就労可能かどうかを把握するためには、在留カード表面の「就労制限の有無」の欄の確認が必要です。「就労不可」「就労制限あり」「就労制限なし」の3パターンがあります。
外国人とのあいだでは、ここが問題になりやすい!
外国人従業員を受け入れて会社で働いてもらう場合、日本人を採用した場合には起こりえない問題が起こることもしばしば。
なぜなら外国人の方は、わたしたちと使用する言語が異なるだけでなく、育ってきた文化や常識が異なるからです。問題になりやすい点は事前に押さえておきましょう!
コミュニケーションを多様化する
外国人従業員を採用して育成していく場合、コミュニケーションを多様化して、いままでとは違うアプローチも試していく必要があります。
なぜなら日本人のあいだでは、いわゆる「阿吽の呼吸」のような考え方が根底にあり、すべてを言葉や文章にしなくても、空気を読んでコミュニケーションを取っているからです。
たとえばアメリカなどの国では「いわなければわからない」というのが基本的な考え方なので、しっかり伝えたいことは言葉にするなど、コミュニケーションの取り方を考えましょう。
◇具体的な取り組みは?
| 取り組み | 内容 |
| 複数言語を使う | 複数の言語を使ってコミュニケーションを取ることが重要です。日本語だけでなく、英語やほかの言語も使用して相手とのコミュニケーションを円滑にします。日本人社員への英語学習を支援するのもいいですね! |
| 言語学習のサポート | 日本語を学ぶ外国人に対して言語学習のサポートを提供します。日本語教室や会話の機会を設けることで、外国人が日本語を習得しやすくなります。 |
| 文化交流イベント | 日本の文化や外国の文化に触れ合えるイベントを開催します。お茶会、料理教室、伝統行事体験、ピクニックなど、異なる文化を体験することでおたがいの理解が深まります。 |
| コミュニケーションツールの活用 | テクノロジーを活用して、異なる地域や国の人々とコミュニケーションを取ることができます。Larkなどの同時通訳機能があるソフトウェアを使うのもおすすめ。 |
| ジェスチャーや表情を大きく | 言葉だけでなく、ジェスチャーや表情、身ぶり手ぶりなど、非言語コミュニケーションの方法も活用します。相手の文化的な背景や言語のちがいに配慮しながら、多様なコミュニケーション方法をさがしましょう。 |
勤務態度を日本人基準にしない
入社初日から勤務態度を日本人基準で考えてしまうと、問題が起きることがあります。例えば南半球の暖かな国の出身の方の場合、おだやかでのんびりしている性格をしていることが多く、時間に対しても厳守すべきという意識はあまりなかったりします。
このような方を入社初日から叱るなどすると、相手としても驚いて会社に来なくなってしまうかもしれません。各国で当たり前の基準がちがうことなどを理解して、組織になじむまでは寛容に構えることが大切です。
配属先はよく相談する
外国人従業員を採用して各種の部署に配属する前に、配属先に関しては本人とよく相談してから決めるようにしましょう。実際に外国人従業員の中には「配属先が思っていたものと違う」といって辞めるケースもあります。
日本ではジョブディスクリプションの概念が希薄で、どんな配属先にしても組織の勝手というような考えがある場合もありますが、世界的な基準からは日本の方が逸脱しています。
どのような仕事にアサインされるのかは、契約前にしっかりと決めておく必要があります。
契約書はしっかり文書にする
外国人従業員と齟齬が起きないように、契約書はしっかり文書化しましょう。外国人従業員向けの契約書を作成する際に、注意すべきポイントは以下のものです。
- 日本の法律に従った雇用契約書を作る
- 英語版も作成する
- 契約書を口で読んであげて、おたがいに労働条件を確認する
もし自分が外国で異国の言葉で契約書を渡されたときには、かなり戸惑うでしょう。
日本語力がとても高ければ契約書もしっかりと理解できるでしょうが、外国人が多く働くブルーカラー系の職種での契約では、相手にも理解してもらえるように口頭で話して理解してもらうなどするとよさそうです。
トラブル例
外国人従業員を受け入れる際には、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。ここまでで説明した点を守っていれば、基本的に問題はありませんが、トラブルに発展するケースを確認し、より注意したうえで説明したポイントを押さえるようにしましょう。
◇具体的にはこんなトラブルに注意!
| トラブルの種類 | 内容 |
| 言語の壁 | 外国人従業員が日本語を十分に理解できないことから生じるコミュニケーションの問題や、業務上の誤解が生じることがあります。 |
| 文化や習慣の違い | 外国人従業員と日本人従業員の間で文化や習慣の違いが原因で、誤解や摩擦が生じることがあります。たとえば、業務の進め方や意思決定のスタイルなどが異なる場合があります。 |
| 労働条件や待遇の不明確さ | 外国人従業員が日本の労働法や企業の規則について理解していないことから、労働条件や待遇に関するトラブルが発生することがあります。 |
| ビザや就労許可の問題 | 外国人従業員のビザや就労許可の手続きが不十分であったり、更新手続きを怠ったりすることが原因で、法的な問題が発生することがあります。 |
| 人種差別や偏見 | 外国人従業員が日本の職場で人種差別や偏見を受けることがあり、それがトラブルの原因となることがあります。 |
| 教育やトレーニングの不足 | 外国人従業員が業務や職場のルールについて理解していないことから、業務のミスや問題が生じることがあります。 |
外国人の定着率は自分たち次第!
母国とちがう環境ではたらくのが初めての方には、日本人なら当たり前ということを押しつけるのはあまりいいとはいえません。定着率を上げるには受け入れる側ができることもたくさんありますので、ぜひ実践できることから企業文化に変化を起こしてみましょう!