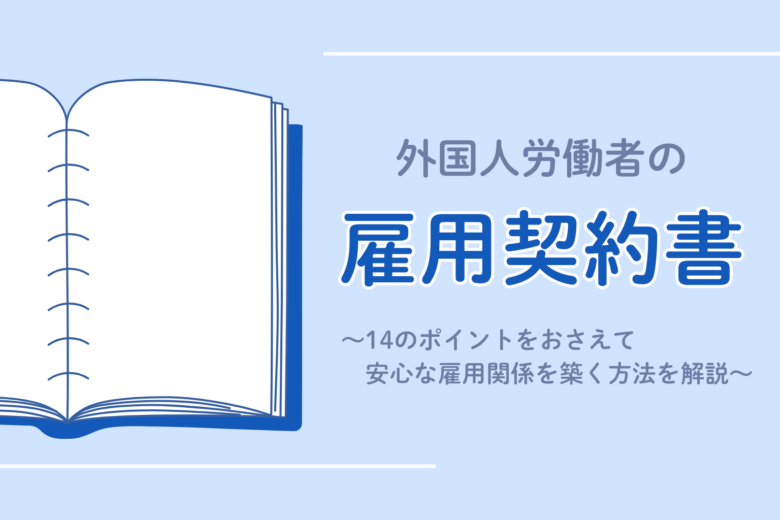入管法違反の罰則、知っていますか? 採用担当者が今すぐ知るべき重大リスクと具体的な回避策を徹底解説!

近年、多くの企業で外国人材の活躍が目覚ましく、その採用は事業成長の鍵となりつつあります。しかし、外国人を受け入れる際には、日本の法律、とりわけ「出入国管理及び難民認定法」(以下、入管法)を正しく理解し、遵守することが不可欠です。
入管法に関する知識が不十分なまま採用活動を進めてしまうと、企業が意図せず法律に違反してしまう事態を招きかねません。
入管法違反は、企業に対して厳しい罰則が科されるだけでなく、長年築き上げてきた社会的信用を大きく損なう可能性もはらんでいます。場合によっては、採用担当者個人の責任が問われることもあります。
この記事では、最低限知っておくべき入管法違反の代表的なケースと、違反した場合にどのような罰則があるのかについて、行政機関の情報をもとにわかりやすく解説します。適切な知識を身につけ、リスクを未然に防ぐためにお役立てください。
目次
要注意!これが入管法違反となる代表的なケース

外国人採用の現場では、どのような行為が入管法違反にあたるのでしょうか。特に注意すべき代表的なケースを解説します。これらの多くは「不法就労助長罪」に該当する可能性があるため、十分な注意が必要です。
ケース1:就労が許可されていない外国人を雇用する
外国人の中には、その持つ在留資格によって日本での就労活動が原則として認められていない人々がいます。例えば、「短期滞在」で観光に来ている方や、「留学」「家族滞在」などの在留資格を持つ方は、そのままでは雇用できません。
これらの在留資格を持った外国人を、就労可能であると誤って判断して雇用した場合や、許可された範囲を超えて業務に従事させた場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。また、在留期間を超えて日本に滞在している、いわゆるオーバーステイ状態の外国人を雇用することも、同様に重大な違反となります。
参照:出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください」
ケース2:在留カードの確認不足・不備
日本に中長期間滞在する外国人には「在留カード」が交付されており、氏名や在留資格、在留期間、そして就労の可否(就労制限の有無)といった重要な情報が記載されています。採用時には、必ずこの在留カードの原本を確認することが法律で義務付けられています。
有効期限が切れていないか、写真と本人が一致するか、そして記載された在留資格で自社の業務に従事させることが可能かを怠ってはいけません。この確認を怠ったり、万が一、偽造された在留カードに気づかず雇用してしまったりした場合も、不法就労を助長したとみなされる恐れがあります。
参照:出入国在留管理庁「『在留カード』とは?」、出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください」
ケース3:許可された業務範囲を超えて働かせる
就労が可能な在留資格であっても、従事できる業務内容には制限が設けられています。例えば、専門的な知識や技術を活かす「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人に、専門性とは関係のない単純作業のみを行わせることは、原則として認められていません。
また、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ方が、事前に入国管理局から「資格外活動許可」を得てアルバイトをする場合でも、許可された時間(原則として週28時間以内)や活動内容の範囲を守る必要があります。雇用主がこれらの制限を超えて働かせた場合も、処罰の対象となり得ます。
参照:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
ケース4:虚偽の申請書類作成に関与する
外国人が在留資格を取得したり、変更・更新したりする際には、入国管理局へ様々な書類を提出します。
この手続きにおいて、雇用主が事実と異なる職務内容や労働条件を記載した雇用契約書や証明書などを作成し、提出することに関与した場合、入管法における「虚偽の文書等の行使・提供」といった違反に問われる可能性があります。
参照:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法」
もし違反したらどうなる?入管法違反の罰則

企業・担当者に対する罰則
上で挙げたような不法就労助長行為(入管法第73条の2)が認められた場合、雇用主(企業または個人事業主)や、採用・労務管理の担当者には、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
不法就労であると知らなかった場合でも、在留カードの確認義務を怠るなど、注意を怠った(過失があった)と判断されれば適用されうるものです。また、法人に対しても別途罰金刑が科される両罰規定が存在します。
さらに、違反の内容や常習性によっては、行政指導や業務改善命令、最悪の場合には関連する事業許可の取り消しといった行政処分を受けるリスクも伴います。
参照:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください」
雇用された外国人本人への影響
不法就労などの入管法違反を犯した外国人本人は、日本からの退去強制(強制送還)の対象となります。一度退去強制されると、原則としてその後5年間(場合によっては10年間または無期限)は日本への上陸が拒否されることになります。
これらの罰則は、直接的な金銭的負担のみならず、企業の評判やブランドイメージを著しく傷つけ、今後の事業展開や採用活動にも深刻な影響を及ぼす可能性があります。
入管法違反を防ぐために企業がすべきこと

採用選考時:在留資格と就労可否の厳格な確認
面接などの選考段階で、応募者には必ず在留カードの原本を提示してもらいましょう。コピーや写真データでの確認は認められていません。カードの有効期間、記載されている在留資格の種類、そして「就労制限の有無」の欄を重点的に確認してください。
「就労不可」と明記されている場合や、在留資格が「短期滞在」「留学」「家族滞在」など、原則就労が認められないものである場合は、そのまま雇用することはできません(別途、資格外活動許可の有無などを確認する必要があります)。
出入国在留管理庁が提供しているウェブサイトで、在留カードの番号が有効かどうかを確認することも、偽造カード対策として有効です。
参照:出入国在留管理庁「不法就労防止にご協力ください」、同庁「在留カード等番号失効情報照会」
雇用契約時:職務内容と在留資格の整合性チェック
雇用契約を結ぶ前には、担当してもらう予定の具体的な職務内容が、その外国人の持つ在留資格で許可されている活動範囲と合致しているかを再度、慎重に確認してください。例えば、「技術・人文知識・国際業務」であれば、その専門性を活かせる業務であるか、といった点です。
判断に迷う場合は、安易に進めず、専門家などに相談しましょう。
雇用管理:在留期間の把握と更新手続きのサポート、資格外活動の管理
雇用している外国人の在留期間は、企業としても正確に把握しておく必要があります。期限が近づいてきたら本人に通知し、更新手続きを失念しないよう注意喚起するなど、必要なサポートを行うことが望ましいでしょう。
資格外活動許可の範囲内で就労している外国人については、許可された時間を超えて働かせていないか、勤怠管理を徹底することが重要です。
参照:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
不明点・懸念点がある場合の相談先
入管法に関する手続きや判断基準について、少しでも疑問や不安を感じた場合は、自己判断せずに、最寄りの地方出入国在留管理局や、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせるか、入管業務を専門とする行政書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
おわりに
外国人採用は、適切に行えば企業にとって大きなメリットをもたらしますが、その根幹には入管法をはじめとするルール遵守が不可欠です。「知らなかった」では済まされないのが法律の世界です。不注意や知識不足が、企業や担当者自身を予期せぬ法的リスクに晒すことになりかねません。
この記事でご紹介した違反ケースや罰則、そして防止策を、自社の採用・労務管理体制を見直すきっかけとしてください。常に最新の情報を確認し、社内での知識共有やチェック体制を整備することが、入管法違反のリスクを確実に回避し、外国人従業員と共に企業が健全に発展していくための重要な第一歩となります。
外国人の採用・受け入れでお悩みならGuidable Jobsへ
外国人材の受け入れ準備や採用活動そのものに関して、「自社の要件に合う優秀な特定技能人材をどこで見つければよいか」「採用後の複雑な諸手続きや定着支援をどのように進めるべきか」といった具体的な課題に直面されている企業様もいらっしゃると思います。
Guidable株式会社では、日本最大級の外国人向け求人媒体「Guidable Jobs」の運営を通じ、様々な業界のニーズに合致する外国人材の採用活動を支援しております。
優秀な外国人材の採用にご関心をお持ちでしたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。











-2-780x520.png)



-2-780x520.jpg)