完全解説!在留カードの受け取りプロセス|採用担当者の為のマニュアル最新版

外国人採用において、在留カードの手続きは避けて通れない重要なプロセスです。特に「受け取り」の段階は、外国人従業員本人が主体となるため、企業側のサポートが求められる場面も少なくありません。
本記事では、外国人従業員が在留カードをスムーズに受け取るための基本的な流れから、起こりがちなトラブルとその対処法、そして企業ができるサポートについて、出入国在留管理庁の情報を基に詳しく解説します。
Guidable Jobsのサービス概要資料のダウンロードはこちら>>
目次
在留カードの「受け取り」は採用の重要プロセス

外国人が日本に中長期間在留するためには、在留カードの交付を受け、常時携帯することが法律で義務付けられています。 (参照:出入国管理関係法令等 | 出入国在留管理庁)
この在留カードの「受け取り」は、外国人従業員が日本で適法に就労・生活を開始するための最初の関門の一つです。受け取りが遅れたり、不備があったりすると、入社手続きの遅延や、最悪の場合、不法就労とみなされるリスクにも繋がりかねません。
企業の人事・採用担当者としては、この「受け取り」プロセスを正確に理解し、必要に応じて従業員をサポートすることで、スムーズな受け入れとコンプライアンス遵守を実現することが重要です。
本記事を通じて、以下の点を明確に理解いただけます。
- 在留カードの基本的な受け取りフロー
- 受け取り時に発生しやすいトラブルと、その具体的な対処法
- 外国人従業員の在留カード受け取りを円滑に進めるために企業ができるサポート
1. 在留カード「受け取り」の基本フロー(外国人本人向け)

在留カードの受け取り方は、日本への新規入国時か、既に日本に在留している方が在留資格の変更や更新の許可を受けた場合かによって異なります。
新規入国の場合
中長期在留者として新規に上陸許可を受けた場合、原則として上陸した空海港で在留カードが交付されます。
受け取り場所:成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国する場合、上陸許可に伴い、その場で在留カードが交付されます。 (参照:在留カードとは? | 出入国在留管理庁)
その他の空海港から入国する場合:後日、市区町村に届け出た住居地宛に簡易書留で郵送されるか、別途指定される方法で交付されます。この場合、パスポートに「在留カード後日交付」の記載がなされます。 (参照:在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁)
必要なもの(空港で交付される場合):
- パスポート
- 在留資格認定証明書(該当する場合)
- ※ 個別の状況により追加書類が指示されることもあります。
在留資格の変更許可・更新許可などを受けた場合
既に日本に在留している方が、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可などを受けた場合、原則として申請を行った地方出入国在留管理局の窓口で新しい在留カードが交付されます。
受け取り場所:申請を行った地方出入国在留管理局
受け取り手続き:
1.許可が下りると、通常、「通知書(ハガキ)」が郵送されてきます。
2.通知書に記載された期間内に、必要なものを持参して本人が窓口で受け取ります。 (参照:在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁、在留期間更新許可申請 | 出入国在留管理庁)
必要なもの(基本的な例):
- 通知書(ハガキ)
- 申請受付票(申請時に渡されたもの)
- パスポート(提示できない場合は、その理由書)
- 現在所持している在留カード
- 手数料納付書(収入印紙を貼付したもの。金額は通知書に記載)
※ 申請内容や個別の状況により、上記以外の書類が必要となる場合があります。必ず通知書や担当官の指示を確認してください。在留カードの申請方法や個別の必要書類の詳細は、出入国在留管理庁のウェブサイトや関連記事をご参照ください。
2. 【採用担当者必見】在留カード「受け取り」でよくあるトラブルと対処法

外国人従業員による在留カードの受け取り時には、いくつかのトラブルが発生する可能性があります。採用担当者として事前に把握し、対策を講じることで、スムーズな入社を支援できます。
ケース1:本人が指定された期間内に受け取りに行けない
状況例: 病気、急な私用、業務の都合などで、交付通知書(ハガキ)に記載された期間内に本人が出入国在留管理局へ行けない。
対処法・企業ができること
- 原則は本人出頭: 在留カードの受け取りは、原則として申請者本人が出頭する必要があります。 (参照:出入国在留管理庁の各種申請手続の案内)
- 代理受領の可否確認: 病気その他やむを得ない理由により本人が出頭できない場合、法定代理人や、地方出入国在留管理庁長官が適当と認める者が代理で受け取れる場合があります。ただし、企業の人事担当者がこれに該当するかはケースバイケースであり、事前に申請した地方出入国在留管理局に確認が必要です。必要な委任状や関係を証明する書類なども確認しましょう。
- 受け取り期間の確認と相談: まずは通知書に記載された期限を確認し、どうしても期間内の出頭が難しい場合は、速やかに申請した地方出入国在留管理局に電話で相談し、指示を仰ぐように本人に助言してください。状況によっては、受け取り期間の延長について考慮される場合もありますが、個別の判断となります。
ケース2:受け取り場所がわからない、行き方が複雑
状況例: 初めて日本の出入国在留管理局へ行く外国人従業員が、場所や交通手段を理解できず、受け取りに手間取る。
対処法・企業ができること
- 事前の情報提供: 交付通知書に記載されている出入国在留管理局の名称、住所、受付時間などを正確に伝え、地図アプリのURLや最寄り駅からのアクセス方法などを具体的に案内します。
- 交通費の支給: 企業によっては、受け取りにかかる交通費を支給することも従業員の安心感に繋がります。
- 同行サポートの検討: 日本の地理や公共交通機関に不慣れな従業員の場合、特に初期においては、企業担当者や日本語が堪能なスタッフが同行することも有効なサポートです。ただし、業務としての位置づけや時間的制約を考慮して判断してください。
ケース3:受け取った在留カードに記載ミスがあった
状況例: 氏名、生年月日、在留資格、在留期間などの記載事項に誤りがある。
対処法・企業ができること
- その場での確認を徹底: 在留カードを受け取ったら、必ずその場で記載内容(氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労制限の有無など)に誤りがないか、本人に確認するよう強く促してください。 (参照:在留カードとは? | 出入国在留管理庁)
- 誤り発見時の対応: もし誤りを発見した場合は、直ちにその場で窓口の職員に申し出させ、訂正を依頼します。後日気づいた場合でも、速やかに交付を受けた地方出入国在留管理局に相談し、指示に従うよう助言してください。放置すると、後の手続きで不利益を被る可能性があります。
- 企業側の確認: 従業員が在留カードを受け取った後、企業としてもコピーを預かる際に記載内容を確認し、万が一誤りがあれば速やかに本人に伝え、対応を促すことが重要です。
ケース4:そもそも「交付通知書(ハガキ)」が届かない
状況例: 在留資格変更や更新の申請後、相当期間が経過しても交付通知書(ハガキ)が届かない。
対処法・企業ができること
- 申請時の住所確認: 申請時に提出した書類の住所に誤りや不備がなかったか、本人に確認させます。転居している場合は、郵便局への転居届の提出状況も確認が必要です。
- 審査状況の確認: 通常、審査には標準処理期間が設けられていますが、状況により前後することがあります。あまりにも連絡がない場合は、申請した地方出入国在留管理局に、申請受付票に記載された申請番号を伝えて審査状況を問い合わせるよう本人に助言してください。 (参照:在留審査処理期間 | 出入国在留管理庁)
- 郵便事故の可能性: 可能性は低いですが、郵便事故も考えられます。まずは出入国在留管理局への問い合わせを優先し、その結果に応じて対応します。
3. 企業ができる!在留カード「スムーズな受け取り」のためのサポート体制

外国人従業員の在留カード受け取りを円滑に進めるためには、企業側の事前の準備と継続的なコミュニケーションが不可欠です。
採用決定~入社までのコミュニケーションのポイント
- 採用決定後、速やかに在留カードの取得・更新状況を確認し、受け取り手続きについて事前に説明します。
- 受け取りに必要な準備や注意点をまとめた資料(可能であれば母国語併記)を提供するのも有効です。
- 定期的に進捗状況を確認し、困っていることがないかヒアリングする体制を整えます。
外国人従業員への事前説明事項リスト(例)
- 在留カード受け取りの重要性
- 受け取り場所、日時、おおよその所要時間
- 持参する必要書類(通知書、パスポート、現有の在留カード、手数料など)
- 受け取り時の確認事項(記載内容のチェック)
- トラブル発生時の連絡先(企業担当者、出入国在留管理庁)
受け取り後の確認事項と社内手続き
- 従業員が在留カードを受け取ったら、速やかに提示を求め、コピーを預かり保管します(法律上の義務ではありませんが、雇用管理上推奨されます)。
- 在留カードの記載内容(特に就労制限の有無、在留期間)を必ず確認し、雇用契約との整合性をチェックします。
- 在留カード番号、有効期限などを社内で適切に管理し、更新時期が近づいたら本人にリマインドする体制を構築します。
まとめ:在留カードの確実な受け取りで、スムーズな外国人採用を実現

在留カードの「受け取り」は、外国人従業員が日本で安心して働き、生活するための重要なステップです。企業がこのプロセスを理解し、適切なサポートを提供することは、採用の円滑化だけでなく、従業員との信頼関係構築にも繋がります。
本記事で解説した情報を参考に、トラブルを未然に防ぎ、外国人従業員の受け入れ準備を万全に整えていただければ幸いです。
【無料ダウンロード】外国人採用 成功事例集|成功のヒントがここに
外国人材のポテンシャルを最大限に引き出す鍵は、円滑なコミュニケーションにあり!現場ですぐに役立つ実践的なテクニックや考え方を、この資料で詳しく解説しています。
実際にGuidableのサービスを活用し、外国人採用によって事業成長や課題解決を実現した企業のリアルな事例が満載です。 貴社の外国人採用戦略を具体化し、成功へと導くためのヒントがきっと見つかります。



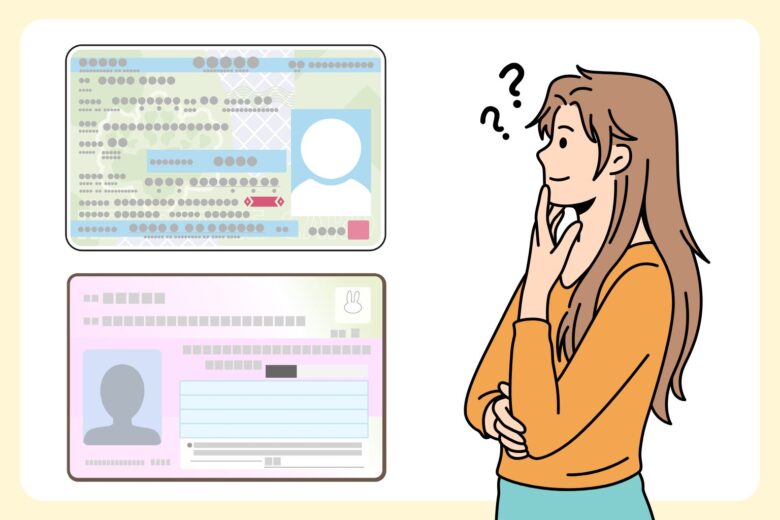







-2-780x520.png)







