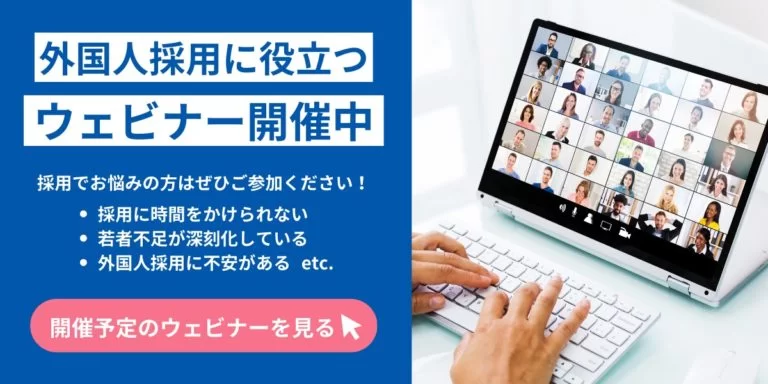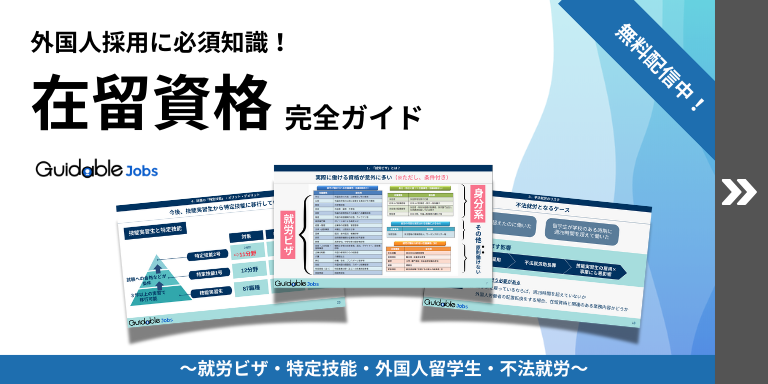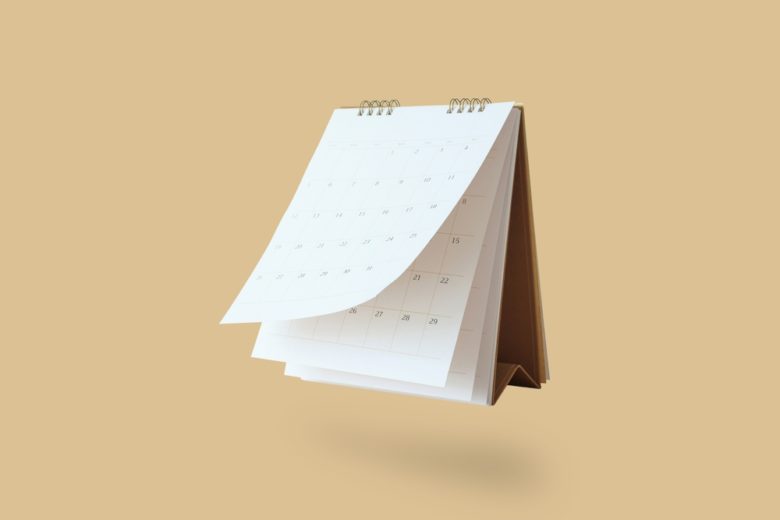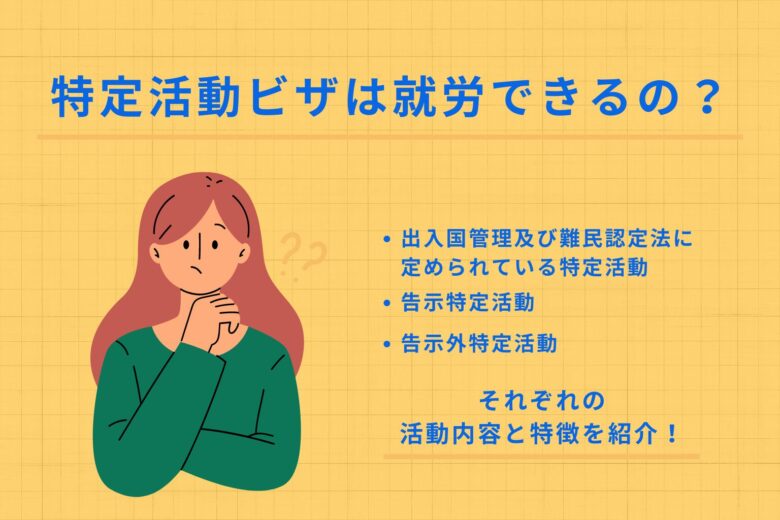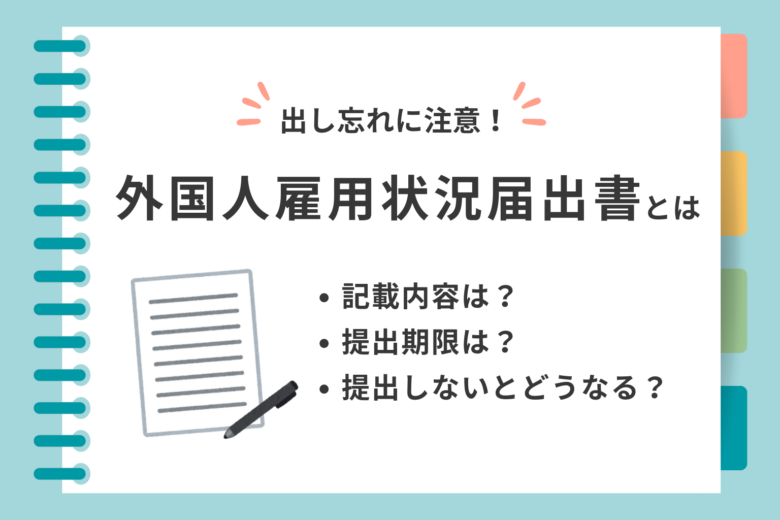不法就労助長罪は身近な問題?!逮捕、起訴されたケースの事例についても紹介します!

不法就労助長罪についてご存知でしょうか?現在の日本では少子高齢化による人材不足の深刻化を受け、多くの業種・業界で外国人が働いています。
日本で働く外国人といえば以前は中国人、韓国人が大半でしたが、最近ではインドネシア、ミャンマー、べトナムなどさまざまな国のひとびとが日本国内で就労。経済のグローバル化で社内公用語を英語にする会社が増えるなど、これからも日本における外国人雇用ニーズは高まっていくことが予測できます。
こうしたことから日本で働く外国人は身近になってきましたが、一方でさまざまなトラブルが発生しているのも事実。なかでも不法就労の外国人に関するトラブルは、刑事事件にまで発展することもあるため要注意です。こちらでは身近な存在となった外国人労働者にかかわる問題としてよく耳にする機会も多い、「不法就労助長罪」について解説してまいります。
目次 [非表示]
不法就労助長罪とは?
「不法就労助長罪」とは、実際にどんな罪なのでしょうか?
これは外国人に不法就労をさせたり、生業として外国人に不法就労をあっせんしたりすることで、外国人の不法就労活動を助けた者に対して課される罪のことです。
そしてここでいう「不法就労」とは、つぎの3つのケースに該当する就労のことです。
1)不法滞在者、被退去強制者が働くケース
密入国した人、在留資格が切れた人が働く
退去強制されることがすでに決まっている人が働く
2)入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
観光等短期滞在目的で入国した人が働く
留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
3)入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
外国料理のコックや語学学校の先生として働くことが認められた人が、工場・事業所で単純労働者として働く
留学生が許可された時間数を超えて働く など
これら不法就労を助長する不法就労助長罪は「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に定められている罪で、違反者には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が処せられることがあります。
入管法とは?
ところで「入管法」とはどんな法律なのでしょうか?
こちらは正式には「出入国管理及び難民認定法」と呼ばれる法令の略称で、おもに以下のものを定めています。
・日本からの出国
・日本への入国、帰国
・外国人が日本に滞在するうえでの在留資格、期限、違反時の罰則
・難民の認定やその取扱い
人権保護や政治的目的から、外国人の在留資格や上陸審査の緩和が進み、それにともない入管法が改正されています。
これらの制度改正によって、日本上陸後の失踪者が増加するようになっているとも指摘されています。
不法就労助長罪はこれ!
不法就労助長罪に問われ、摘発の対象となるのは以下の3つの行為をした者です。
外国人に不法就労活動をさせた者
たとえば不法就労に該当する外国人(不法就労者)を雇用した者、使用した者、派遣して労務に従事させた者が摘発の対象です。
外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた者
たとえば不法就労者に宿舎を提供した者、不法就労者のパスポート等を預かった者、入国費用の負担などにより事実上の支配下に置いた者が摘発の対象になります。
外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関し斡旋した者
たとえばブローカーなど不法就労活動を斡旋した者、仲介等をした者が摘発の対象です。
不法就労助長罪の事例をご紹介

国内の外国人雇用ニーズの高まりを受けて、これから本格的に外国人採用を検討している企業も多いと思います。しかし安易に外国人採用を行うと、不法就労助長罪に問われかねないこともあります。
こちらでは実際に不法就労助長罪で逮捕・起訴された事例をニュースを元にしてご紹介しましょう。
事例1:不法残留の中国人派遣 入管法違反で3人逮捕 京都
2019年9月26日
京都府警は人材派遣会社役員の男、同社社員で中国籍の男など男女3人を在留期間がすぎた中国人4人を食品加工会社に派遣して労務に従事させた入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕。
事例2:検察「国際的非難に値」不法就労助長の理事長 懲役2年求刑 群馬
2017年2月20日
日本語学校「東日本国際アカデミー(栃木県足利市)」において、ベトナム人留学生3人を不法就労させたとして、入管法違反(不法就労助長)の疑いで起訴された同校理事長。
法人として起訴された人材派遣会社「東毛テクノサービス(前原被告経営)」の第2回公判が開かれ、検察側は被告個人に懲役2年と罰金200万円、同社に対して罰金200万円を求刑。
被告は留学生を借上げアパートに住まわせ、逃走阻止の目的でパスポートを没収したうえで、労働力と賃金を搾取したとして厳しく批判し「身勝手かつ私欲目的に動機に酌量の余地はない」と断罪。
事例3:老舗串カツ店 不法就労助長の疑いで書類送検 大阪
2017年3月
大阪府警は大阪の老舗串カツ店の運営会社の社長や、幹部の計6名、及び法人としての同社を入管法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検したと発表。
同社は2015年9月から2016年11月にかけて、大阪市内の5店舗でベトナムやミャンマー国籍の留学生など男女17人をアルバイトで雇い、週28時間の法定労働時間を超えて働かせるなどの疑いがあるとした。
さらに入管法違反(不法就労)の疑いで、これら留学生アルバイトのうち3人を逮捕、14人を書類送検。
***
これらの事例では、不法残留者を派遣して労働に従事させたこと、不法就労者に宿舎を提供したこと、またパスポートを預かるなどにより外国人に不法就労させるために自己の支配下に置いたこと、入国管理局から認められた範囲を超えて働かせたこと、などを理由として企業及び責任者が不法就労助長罪に問われています。
不法就労助長罪になりたくない!
不法就労助長罪の逮捕事例をみると、不法就労助長罪はわたしたちの身近に起こりやすい問題です。
在留期限が切れた外国人を知らずに雇った場合や、入国管理局から認められた労働時間数を超えて勤務させた場合でも、「不法就労」に該当してこれらの外国人を働かせていた企業が不法就労助長罪に問われます。
ではわたしたちが不法就労助長罪に問われることなく、適法かつ適切に外国人労働者を採用するにはどうすればいいでしょうか?
以降では防止策について説明いたします。
防止策とは?
企業として不法就労助長罪に問われないための防止策には、どのようなものがあるでしょう?
それは対象となる外国人が「不法就労に該当しているか否かを事前に確認する」ということがもっとも有効でしょう。
具体的には雇用し、使用し、または派遣しようとする外国人が、不法就労に該当していないかを事前にチェックすること。
そのためのポイントが、厚生労働省のリーフレット「外国人を雇用する事業主の皆様へ 不法就労防止にご協力ください」にて説明されています。
ポイント1:在留カード等の番号が失効していないか確認
入国管理局のホームページで、在留カードの番号が失効していないか確認しましょう。
ポイント2:在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認
就労不可の場合には原則雇用はできませんが、以下に記述するポイント3により雇用できる場合があります。
ポイント3:在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認
資格外活動許可欄に「許可」と記載されている場合、記載された条件において雇用が可能になります。
ポイント4:仮放免許可は在留資格ではない
仮放免許可とはなんらかの理由で、退去強制の対象となっている外国人でありながら、健康上の理由などで一時的に収容が説かれている状態のことです。仮放免許可証に「就労禁止」のむねが記載されている場合は雇用することはできません。
これらのポイントを参考にして、適法で適切な外国人雇用を実現しましょう。
不法就労助長罪について知識が深まりましたか?

日本国内で働く外国人の方々は、母国語が堪能であるのは当然として、日本人にはない発想、思考、価値観を持っており、これらの能力を活かせれば事業の成長と発展につなげることができます。
外国人労働者を単なる労働力としてではなく、貴重なパートナーとしてリスペクトして付き合えば不法就労問題など発生することもなくなります。
外国人労働者へのリスペクトこそが、最大の防止策と言えるのではないでしょうか。
外国人採用ハンドブックを見てみる⇒資料はこちらから