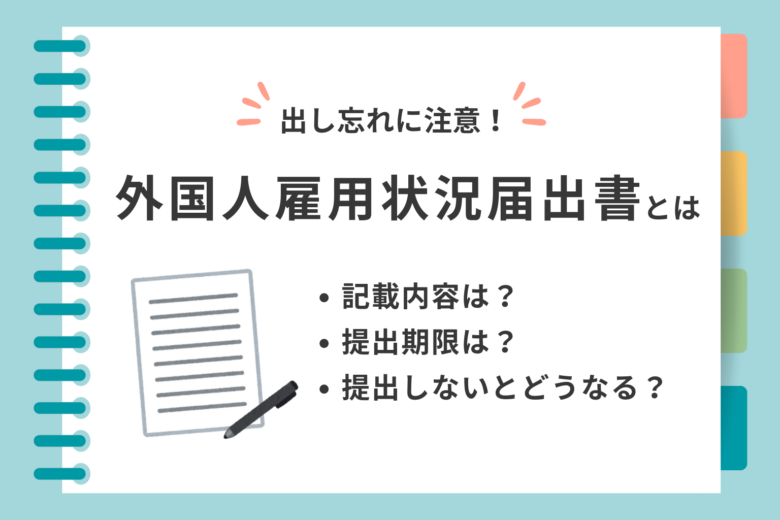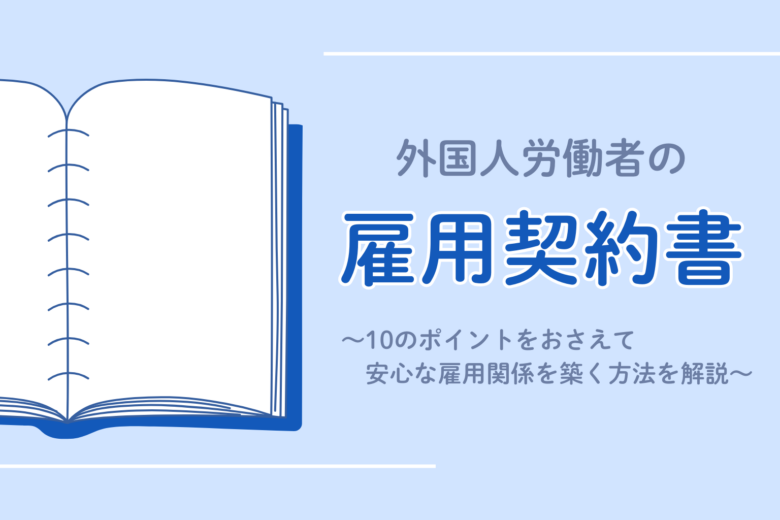外国人「永住者」と「特別永住者」の違いは?在留資格の要件、雇用手続きの注意点を解説

外国人を雇用する際に、「永住者」や「特別永住者」という言葉を耳にする機会があるかもしれません。
みなさんは、この2つの言葉の違いを知っていますか?
「永住」という言葉からおおよそのイメージはつかめるものの、具体的に説明するのは難しいかもしれません。
この記事では永住者と特別永住者の違いと、それぞれを取得している外国人を雇用する際の注意点をご紹介します。
永住者と特別永住者の違い
はじめに「永住者」と「特別永住者」は、それぞれどのような人を指しているかを解説します。
永住者とは
永住者とは、永住権の申請が法務大臣に許可され、永続的に日本に滞在することが可能な外国人のことです。
2023年6月時点で日本には約88万人の永住者がいます。内訳は中国、フィリピン、ブラジルが上位で、この3カ国が6割以上を占めています。
永住者がその他の外国人滞在者と異なる点はおもに以下の2点です。
永住者は日本での活動に制限がない

日本に中長期滞在している外国人は、活動目的に応じて適切な在留資格を取得していることが多く、原則として特定の活動以外の仕事に就くことはできません。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であれば、理学や工学、法律学や社会学など、活動目的と等しくその技術や知識を活かした仕事のみ許可されています。そのため接客や販売などの単純労働に就くことは不可となっています。
また「留学生」の在留資格は、おもに学業に関連しているため、アルバイトで働きたい場合は資格外活動許可の申請が必要です。そして許可がおりた場合でも、週あたりの労働時間や賃金に関する規制があります。
これに対して「永住」の在留資格を持つ外国人(永住者)は、活動の制限がなく他の在留資格にあるような労働の制約を受けないため、日本人と同様に資格やスキルに関係なく幅広い職種で働くことが可能です。
永住者は日本に滞在する期間の制限がない
日本に滞在している外国人の多くは、あらかじめ滞在期間が決められています。
たとえば一般的な就労資格であれば、契約の期間が切れると同時に在留期限も終了します。企業との契約更新や新しい雇用契約を締結しなければ、帰国しなければなりません。
一方で永住者は在留期間に制限がないため、在留資格の取り消しをされない限りは日本に永住することが可能です。注意点として「在留カード」には有効期限があり、7年ごとに更新が必要となっています。
永住者と認められている外国人が満たしている要件
永住許可申請が下りている外国人は、以下の審査基準を満たしています。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない
このような審査基準に基づき、日本の永住者となる外国人の数は年々増加傾向にあります。

引用:出入国在留管理庁 令和5年6月末現在における在留外国人数について

特別永住者とは
特別永住者とは、日本が第二次世界大戦の敗戦国となった際に、平和条約に基づき日本の国籍を離脱したが、すでに日本に定住をしていたことから永住資格が付与された外国人のことを指します。
朝鮮半島や台湾が日本の占領から解放されたため、特別永住者の多くは韓国人・朝鮮人・台湾人です。
特別永住権は、第二次世界大戦前から日本に住んでいる在日韓国人・朝鮮人・台湾人はもちろん、その子孫まで受け継がれています。
特別永住者は日本での活動に制限がない

特別永住者は、永住者と同様に就労上の制限がない在留資格です。 そのため本人が希望すれば、どのような仕事をすることも自由です。
2023年現在、日本には約28万人の特別永住者が住んでおり、その9割以上を韓国人が占めています。日本人と同様に働き、生活しています。
特別永住者は日本に滞在する期間の制限がない
滞在期間に関しても、制限はありません。資格の取り消しをされない限りは日本に永住することが可能です。
注意点として、永住者と同様に「特別永住者証明書」には有効期限があり、7年ごとに更新が必要となっています。
永住者と認められている外国人が満たしている要件
特別永住者であるためには「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」であることが前提要件とされています。
具体的には、1952年のサンフランシスコ講和条約で日本国籍を離脱したとされた在日韓国人・朝鮮人と在日台湾人が対象です。日本国外に出国して在留資格を喪失した者、つまり帰国した人は「平和条約国籍離脱者」には該当しません。
永住者と特別永住者で違う採用の注意点
2種類の在留資格はどちらも就労に関わる制限がないため、雇用主がおこなう手続きは比較的簡単です。
しかしながら、採用までの流れは永住者と特別永住者で異なる部分があります。
「永住者」と「特別永住者」それぞれを雇用する際の手続きについて解説します。
永住者と特別永住者、採用手続きの違いを比較
以下の表に、それぞれの採用手続きの違いをまとめました。
| 永住者 | 特別永住者 | |
| 就労制限 | なし | なし |
| 在留カードの確認 | 必要 | – |
| 特別永住者証明書の確認 | – | 不要 |
| 外国人雇用状況の届出 | 必要 | 不要 |
| 通称名での届出 | 不可 | 不可 |
就労制限
前述の通り、永住者・特別永住者ともに就労に関する制限はありません。
在留カード・特別永住者証明書の確認
雇用者が「永住者」の場合は、在留カードを提示してもらう必要があります。
在留カードは、雇用主が労働者の身分を確認するための重要な手段です。
雇用者が自分の在留資格に合致するかどうかを確認し、不正な雇用や不法滞在を防ぐ役割を果たします。
また、雇用保険加入手続きの際に在留資格の種類やカード番号を記載する必要があることも把握しておきましょう。
「特別永住者」は、在留カードの代わりに特別永住者証明書が交付されています。しかし、この特別永住者証明書は雇用する際に提示してもらう必要はありません。常時携帯する義務もなく、在留カードとは扱いが異なるため注意が必要です。
外国人雇用状況の届出
外国人を雇用したら、「外国人雇用状況届出書」で外国人労働者の氏名や在留資格、在留期間の届け出が必要です。
これは、外国人労働者の雇用状況を把握し適切に雇用管理を行うために必要とされている制度です。
「永住者」は外国人のため例外なく届出が必要になります。ただし、在留資格が「外交」や「公用」の方は対象外となります。
しかしながら、「特別永住者」は外国人雇用状況の届出は必要ありません。
通称名での届出
永住者・特別永住者ともに、住んでいる市区町村の役所で通称名の登録が可能です。
日常生活や一般的なコミュニケーションにおいて通称名を使用できるため、日本で生活を送るうえで便益がありますが、法的文書や公的手続きにおいては、本名が必要とされることがあります。
具体的な手続きや要件は個別のケースによって異なる場合があるため、手続き内容はしっかり確認して進めるようにしましょう。
永住者と特別永住者の違いは分かりましたか?
永住者と特別永住者は日本国内での滞在や就労において制限がない、という点は同じです。
しかしながら、雇用する際の手続きには違いがあることを紹介しました。
永住者や特別永住者を、いざ雇用するとなったときに慌てないよう、しっかり押さえておきましょう。
外国人採用ハンドブックを見てみる⇒資料はこちらから