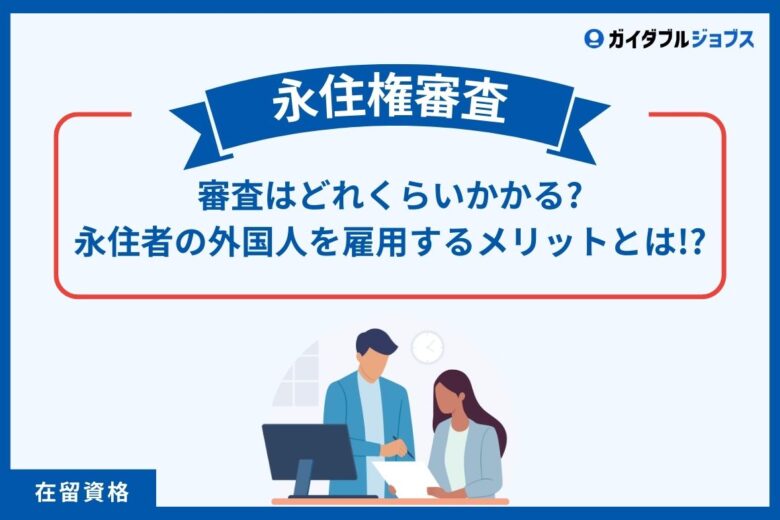申請で失敗させない!永住権「取得要件」と企業の鉄壁サポート術

外国人従業員に長く活躍してもらうため、永住権取得のサポートを検討されている企業の採用担当者様も多いのではないでしょうか。永住権の基本的なメリットはご理解されていることを前提に、本記事では、永住権の具体的な「取得要件」と、企業が従業員の申請をどのようにサポートできるか、その実践的なフローや注意点を詳しく解説します。
本記事が、外国人従業員の円滑な永住権取得と、貴社の人材戦略の一助となれば幸いです。
Guidable Jobsのサービス概要資料のダウンロードはこちら>>
目次
【雇用形態・状況別】永住権「取得要件」達成のポイントと企業の確認事項

永住許可を得るためには、出入国在留管理庁が定める複数の要件を満たす必要があります。ここでは主要な要件について、特に企業が関与できるポイントや、多様な雇用形態の従業員を抱える企業が注意すべき点を解説します。
収入要件:安定性と継続性が鍵
永住許可の要件の一つに「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」があります。これは、公共の負担にならず、安定した生活を継続できる経済的基盤があるかどうかが審査されるものです。
目安と立証
- 年収の具体的な基準額は明示されていませんが、一般的には継続して300万円程度以上の年収が目安の一つとされています。ただし、これはあくまで目安であり、扶養家族の人数などによって個別に判断されます。
- アルバイトや派遣社員の場合でも、安定した収入が継続的に得られていることを客観的な資料(課税証明書、納税証明書、預貯金通帳の写し等)で立証できれば、要件を満たす可能性があります。(参照:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) | 出入国在留管理庁の「ウ 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の項目)
企業として協力できる収入安定化策
- 適正な評価と処遇: 従業員の能力や貢献度に応じた昇給や手当の支給は、収入の安定化・向上に繋がります。
- 雇用契約の安定性: 有期雇用契約の場合、契約更新の見込みや実績を示すこと、可能であれば無期雇用への転換を検討することも、安定性の証明に資する場合があります。
- キャリアパスの提示: 企業内でのキャリアアップの道筋を示すことで、将来的な収入増の見込みを従業員に持たせ、申請への動機付けにもなります。
在留歴・在留状況:継続性と現在の在留資格
原則として「引き続き10年以上本邦に在留していること」が必要です。ただし、この期間中、就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要します。
転職が多い従業員: 転職自体が直ちに不利になるわけではありませんが、キャリアの一貫性や安定した就労状況が重視されます。企業としては、採用時にこれまでの職歴や在留状況を丁寧に確認し、現在の職務との関連性や今後の定着見込みを説明できるようにしておくことが望ましいでしょう。
特定技能からの移行検討者: 「特定技能1号」の在留期間は永住許可の要件となる「5年以上の就労・居住実績」には通常含まれません。「特定技能2号」へ移行し、その在留資格で一定期間活動することで要件を満たす道筋が考えられます。企業としては、特定技能外国人材のキャリアプランを共に考え、必要な資格取得支援や2号への移行支援を行うことが、将来的な永住申請に繋がります。(参照: 永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) | 出入国在留管理庁の「ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は居住資格をもって引き続き5年以上本邦に在留していることを要する。」の項目)
納税・社会保険の確実な履行:公的義務の遵守
税金(所得税、住民税など)や公的年金、公的医療保険の保険料を適切に納付していることが求められます。未納や滞納がある場合は、永住許可申請において不利になる可能性が非常に高いです。
企業による証明書発行協力
従業員の求めに応じて、源泉徴収票や給与明細など、収入や納税状況を証明する書類を速やかに発行します。
日頃の適切な管理と指導
- 企業は、従業員の給与から所得税や住民税、社会保険料を適正に徴収・納付する義務があります。この確実な履行が、従業員の永住申請を間接的に支援することになります。
- 外国人従業員に対し、日本の税金や社会保険制度の重要性を説明し、理解を促すことも大切です。(参照:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) | 出入国在留管理庁の「イ 公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。」の項目)
素行善良要件:法令遵守の意識
「素行が善良であること」も重要な要件です。日本の法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されることのない生活を送っていることが求められます。
企業ができる従業員への啓発
- 日本の法律や交通ルール、社会規範について、外国人従業員に理解しやすい形で情報提供を行います。
- 社内研修などを通じてコンプライアンス意識を高めることも有効です。
- 万が一、従業員が何らかの法的トラブルに巻き込まれたり、交通違反を犯したりした場合は、正直に申告させ、適切な対応を指導することが求められます。隠蔽は状況を悪化させる可能性があります。(参照:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) | 出入国在留管理庁の「エ 素行が善良であること」の項目)
企業が主導する!外国人従業員の永住権申請サポート・実践フロー

従業員から永住権取得の相談があった場合、企業はどのようにサポートを進めればよいのでしょうか。具体的なフローを4つのステップで解説します。
ステップ1:従業員からの相談対応と「取得要件」充足状況の初期アセスメント
- まずは従業員の話を丁寧に聞き、永住権取得の意思や現在の状況(在留歴、収入、家族構成、納税状況など)を把握します。
- 出入国在留管理庁のウェブサイト等で公開されている「永住許可に関するガイドライン」や必要書類リストを従業員に提示し、自身が要件を満たしているか、またどのような準備が必要かを一緒に確認します。(参照:永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂) | 出入国在留管理庁)
ステップ2:企業が準備・発行する書類一覧と作成時の注意点
永住許可申請には、申請者本人が準備する書類の他に、勤務先企業が発行する書類も必要となる場合があります。
- 主な企業発行書類の例:
- 在職証明書
- 源泉徴収票(直近数年分)
- 会社の登記事項証明書、決算報告書の写し(申請者本人または身元保証人が経営者や役員の場合など)
- (任意)推薦状:企業の代表者や直属の上司が、申請者の勤務状況や貢献度、人柄などを具体的に記述し、永住許可が相当である旨を推薦する書面です。法的に必須ではありませんが、審査において補足的な資料となり得ます。
作成時の注意点:
- 正確な情報を記載し、社印(または代表者印)を鮮明に押印します。
- 従業員の申請スケジュールを考慮し、速やかに発行できるよう社内体制を整えておくことが望ましいです。
ステップ3:「身元保証人」を企業(または役員等)が引き受ける場合の判断基準・手続き・責任範囲
永住許可申請には、原則として身元保証人が必要です。身元保証人は、通常、日本人または永住者で、安定した収入があり、納税等の公的義務を履行している人がなります。
企業(法人)は身元保証人になれるか
- 法人そのものは身元保証人にはなれません。代表者や役員、上司などが個人として身元保証人になるケースが一般的です。
企業関係者が身元保証人になる場合の判断基準
- 従業員との信頼関係、身元保証人自身の経済的安定性、公的義務の履行状況などを総合的に考慮します。
- 社内で身元保証に関する規定や基準を設けておくと、公平な判断がしやすくなります。
身元保証人の責任範囲
- 身元保証人は、申請者が日本で滞在するにあたり、経済的保証や法令遵守の指導を行うことが期待されます。具体的には、滞在費の支弁、法令遵守の指導などが挙げられます。ただし、これは道義的責任であり、民法上の保証人のような法的支払い義務を負うものではありません。
手続き
- 身元保証人は、身元保証書、住民票、所得証明書、在職証明書(会社員の場合)などを提出する必要があります。
ステップ4:(推奨)専門家(行政書士等)との連携体制と費用負担に関する社内規定
永住許可申請は手続きが複雑で、必要書類も多岐にわたります。
専門家の活用:
- 申請手続きに行政書士などの専門家のサポートを得ることで、書類準備の漏れを防ぎ、スムーズな申請が期待できます。
- 企業として、信頼できる行政書士を紹介したり、相談窓口を設けたりすることも有効な支援です。
費用負担:
- 専門家への依頼費用や申請手数料について、企業が一部または全額を補助する制度を設けることも、従業員の永住権取得を後押しする有効な手段となります。福利厚生の一環として検討する企業もあります。これらの費用負担については、社内規定を整備し、公平性を保つことが重要です。
こんな時どうする?採用担当者のための永住権「取得要件」Q&A

ここでは、採用担当者様が直面しやすい疑問についてQ&A形式で解説します。
Q1. 過去に税金や社会保険の支払いに遅延があった従業員は、永住申請は難しいでしょうか?
A1. 税金や社会保険料の未納・滞納は、永住許可申請において不利に働く可能性が高いです。ただし、過去に一時的な遅延があったとしても、その後の改善状況(完納し、現在は適切に納付している等)や遅延の理由によっては、総合的に判断される場合もあります。まずは正直に状況を把握し、改善に向けた努力(例えば、完納証明書の取得、今後の確実な納付計画の提示など)を行うことが重要です。企業としては、従業員に対し、公的義務の重要性を日頃から指導し、適切な納付を促すことが求められます。
Q2. 扶養家族が多い従業員の収入要件は、どのように考えればよいでしょうか?
A2. 収入要件は、申請者本人だけでなく、生計を同一にする家族全体の生活が安定しているかどうかが判断基準となります。そのため、扶養家族が多い場合は、それに応じてより多くの収入が求められる傾向にあります。具体的な金額基準は明示されていませんが、家族全員が安定した生活を送れるだけの十分な収入があることを客観的な資料で示す必要があります。企業としては、当該従業員の給与水準が扶養家族の人数に対して十分であるか、また、将来的な昇給の見込みなどを考慮し、必要であれば給与体系の見直しや手当の支給などを検討することも一つの支援策となり得ます。
Q3. 永住申請中に従業員が転職・退職した場合、企業として何かすべきことはありますか?
A3. 永住申請中に申請者の就労状況に変更があった場合(転職、退職など)、速やかに出入国在留管理庁に届け出る必要があります。これは申請者本人の義務ですが、企業としても、従業員からそのような申し出があった場合は、手続きを怠らないよう助言することが望ましいです。 転職した場合、新しい勤務先の状況(職務内容、収入、安定性など)が改めて審査の対象となります。退職して無職の状態になった場合は、収入要件を満たせなくなるため、永住許可は難しくなるのが一般的です。企業が身元保証人になっている(またはなろうとしていた)場合、その前提条件も変わるため、状況に応じて保証を取り下げるなどの対応が必要になることもあります。
まとめ:積極的な永住権取得支援で、選ばれ続ける企業へ

外国人従業員の永住権取得は、本人の生活基盤の安定のみならず、企業にとっても人材の長期的な活躍と定着、ひいては組織全体の活性化に繋がる重要な取り組みです。
本記事で解説した取得要件の詳細や企業のサポート体制を整備することは、従業員のエンゲージメントを高め、企業への貢献意欲を促進する効果も期待できます。また、外国人材の採用市場において、「従業員のキャリア形成を長期的に支援する企業」としての魅力向上にも繋がり、優秀な人材の獲得競争においても有利に働く可能性があります。
永住権取得のプロセスは複雑であり、企業側の理解と適切なサポートが不可欠です。本記事が、貴社における外国人従業員の永住権取得支援の一助となり、共に成長できる関係構築に繋がることを心より願っております。
【無料ダウンロード】外国人採用 成功事例集|成功のヒントがここに
外国人材のポテンシャルを最大限に引き出す鍵は、円滑なコミュニケーションにあり!現場ですぐに役立つ実践的なテクニックや考え方を、この資料で詳しく解説しています。
実際にGuidableのサービスを活用し、外国人採用によって事業成長や課題解決を実現した企業のリアルな事例が満載です。 貴社の外国人採用戦略を具体化し、成功へと導くためのヒントがきっと見つかります。
▼今すぐ資料をダウンロードして、企業の課題解決方法をご確認ください!▼
「外国人材とのコミュニケーションの課題を解決する方法」を無料ダウンロード>>



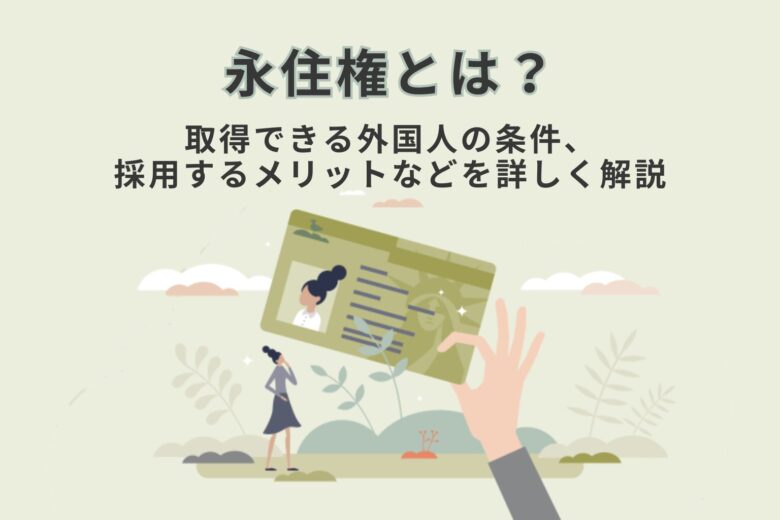

-11-1-780x520.png)

-8-1-780x520.png)




-2-780x520.png)