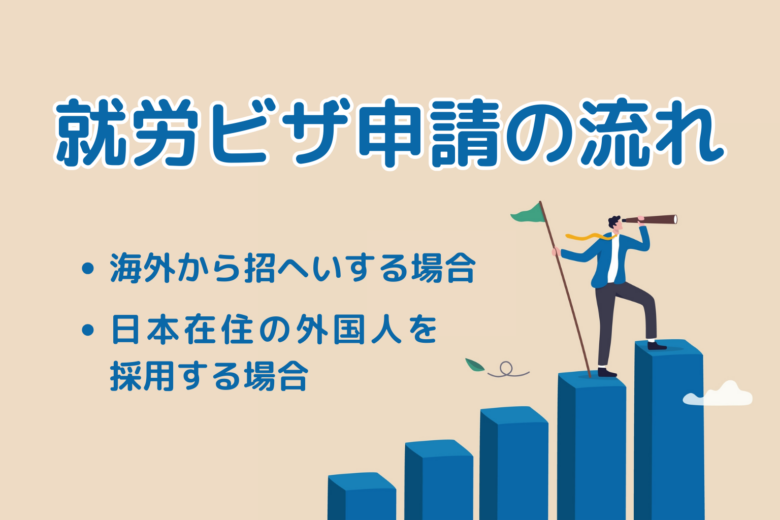ケース別解説!外国人の在留カード不携帯・紛失時の対応完全ガイド

外国人採用を進める中で、候補者や従業員の在留カードに関するトラブルに遭遇する可能性はゼロではありません。
特に「在留カードを携帯していない」という状況は、法律違反にあたり、採用担当者としても正しい知識と対応が求められます。
本記事では、採用担当者が遭遇しうるケーススタディを通じて、在留カード不携帯時の適切な対応方法、法的リスク、そして知っておくべきポイントを解説します。
(本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的アドバイスではありません。必要に応じて専門家にご相談ください。)
目次
はじめに:外国人採用で遭遇するかも?在留カード「不携帯」トラブル

外国人材の活躍が不可欠となる中、企業には適正な雇用管理が強く求められています。
その基本となるのが、在留資格や就労可否を確認するための「在留カード」です。
中長期在留者(※)である外国人は、日本に滞在する間、原則として常に在留カードを携帯することが法律で義務付けられています(出入国管理及び難民認定法 第23条第2項)。
この義務に違反した場合、外国人本人には罰則が科される可能性があります。
採用担当者としては、候補者や従業員がこの義務を遵守しているか直接取り締まる立場にはありませんが、面接時や雇用後に「不携帯」の状況に直面する可能性はあります。その際に適切な対応が取れなければ、意図せず不法就労を助長してしまうリスクも考えられます。
本記事を通して、在留カードの不携帯に関する正しい知識を身につけ、万が一の事態に備えましょう。
※中長期在留者とは、3ヶ月を超える在留期間が決定された方や、永住者、特別永住者などを指します。短期滞在者などは該当しません。
ケーススタディ1:「面接時に在留カードを忘れた」と言われたら?

【状況】
採用面接に来た外国人候補者が、「すみません、今日、在留カードを家に忘れてきてしまいました」と申し出てきました。
【確認すべきこと・対応フロー】
1. まずは落ち着いて、候補者の話を聴く: 相手にプレッシャーを与えない尋ね方をしつつ、候補者の状況や様子から、単純な忘れものか、他に何か事情がありそうかなどを把握する程度に留めます。
(深入りはせず、あくまで確認は後日の原本で行います。)
2. 在留カードの携帯が法的義務であることを伝える: 「在留カードは法律で常に携帯することが義務付けられています。次回からは必ず携帯してください」と、重要性を伝えます。
3. 在留カードの有効性・就労可否の確認は必須: 面接時に現物で確認できない場合、その日のうちに、あるいは後日改めて在留カードの提示を求め、必ず原本で以下の点を確認します。
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域
- 住居地
- 在留資格、在留期間、在留期間の満了日
- 就労制限の有無(「就労制限の有無」欄、「資格外活動許可欄」)
- ードの有効期間
- 偽変造の疑いがないか(ホログラム等)
(参照:出入国在留管理庁「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」)
4. 確認できるまで採用プロセスは保留: 在留カードの現物で適法な在留資格と就労可否が確認できるまで、内定出しや雇用契約の締結は絶対に行わないでください。
5. コピーの取得と保管: 確認後は、在留カードの両面のコピーを取得し、適切に保管します(ただし、コピーの取得・保管は法律上の義務ではありませんが、雇用管理上推奨されます)。
【法的リスク】
もし、在留カードを確認せずに、あるいは不携帯の事実を知りながら就労が許可されていない外国人を雇用した場合、企業側が「不法就労助長罪」(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)に問われる可能性があります。これには、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。
面接時に不携帯であっても、後日確実に原本を確認することが極めて重要です。
ケーススタディ2:「従業員が職務質問で不携帯を指摘された」と連絡があったら?

【状況】
雇用している外国人従業員から、「外出中に警察官から職務質問を受け、在留カードを持っていなかったため注意された(あるいは警察署で確認を受けた)」と報告がありました。
【会社としての対応】
1. 事実確認: まずは従業員から詳細な状況(いつ、どこで、どのような状況で、警察からどのような指示や処分を受けたか)をヒアリングします。
2. 会社への直接的な影響: 通常、在留カードの不携帯は本人に対する罰則(20万円以下の罰金:出入国管理及び難民認定法 第76条)であり、企業が直接罰せられることはありません。ただし、従業員が罰金刑を受けた場合、今後の在留資格更新などに影響が出る可能性は否定できません。
3. 再発防止の徹底: なぜ不携帯だったのか理由を確認し、改めて在留カードの常時携帯が法的義務であり、違反すると罰則があること、在留資格にも影響しうる重要なことであることを、当該従業員および他の外国人従業員にも周知徹底します。
- 朝礼やミーティングでの呼びかけ
- 社内掲示板やポータルサイトでの注意喚起
- 入社時のオリエンテーションでの説明強化 など
4. 状況の注視: 当該従業員の在留期間更新が近い場合は、今回の件が影響しないか、状況を気にかけておくことが望ましいでしょう。
【注意点】
警察官や入国警備官等は、職務上必要がある場合に外国人に対して在留カードの提示を求めることができます。この提示を拒んだ場合も罰則(1年以下の懲役又は20万円以下の罰金:出入国管理及び難民認定法 第75条の2)の対象となります。携帯義務と合わせて提示義務についても従業員に周知しておくことが重要です。
ケーススタディ3:「在留カードを紛失(または盗難された)」と報告があったら?

【状況】
雇用している外国人従業員から、「カバンごと盗難にあい、在留カードも一緒に失くしてしまった。(あるいは、どこかで紛失してしまった)」と、現在手元にない旨の報告がありました。本人は動揺しており、どうすればよいか尋ねています。
【確認すべきこと・対応フロー】
1. 従業員を落ち着かせ、状況を確認する
まずは従業員の安全と心情に配慮し、落ち着いて話を聞きます。
いつ、どこで、どのような状況で紛失または盗難にあったのか、詳細を確認します。
2. 警察への届出を促す(または確認する)
- 紛失の場合: 速やかに最寄りの警察署または交番に遺失届を提出するよう伝えます。提出済みであれば、受理番号などを控えておくようアドバイスします。
- 盗難の場合: 速やかに最寄りの警察署または交番に盗難届を提出するよう伝えます。同様に、提出済みであれば受理番号などを控えておくようアドバイスします。
3. 出入国在留管理庁への手続きを説明・確認する
- 届出義務: 在留カードを紛失・盗難等で失った場合、その事実を知った日(日本国外で知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に、本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に届け出て、在留カードの再交付を申請しなければならないことを明確に伝えます(出入国管理及び難民認定法 第19条の11)。
- 申請状況の確認: すでに申請済みか、これから申請するのかを確認します。これから申請する場合は、必要な書類(パスポート、写真、遺失届受理証明書・盗難届受理証明書など)について、出入国在留管理庁のウェブサイト等で確認するよう促します。
(参照:出入国在留管理庁「在留カードの紛失等による再交付申請」)
在留カードの再交付申請手続き
在留カードを紛失した場合、紛失に気づいた日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で再交付申請を行う必要があります(海外で紛失に気づいた場合は、帰国日から14日以内)。
必要書類
• 在留カード再交付申請書
• 証明写真(縦40mm×横30mm)1枚
• 紛失を証明する書類(警察発行の遺失届出証明書または盗難届出証明書など)
• パスポート
手数料と交付
再交付に手数料はかかりません(証明写真代は自己負担)。受付時間内に申請すれば、基本的に即日交付されます。
企業による代理申請も可能
外国人を雇用している企業は、「申請等取次制度」を利用して、従業員に代わって再交付申請を行うことができます。
必要なもの
• 委任状
• 在留カード再交付申請書
• 証明写真(縦40mm×横30mm)1枚
• 紛失を証明する書類(警察発行の遺失届出証明書または盗難届出証明書など)
• パスポート
企業の担当者が入国管理局へ出向き、申請から新しいカードの受け取りまで代行できます。
申請を怠った場合の罰則
14日以内に申請を行わなかった場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科される可能性があります(入管法 第71条の4)。
4. 再交付までの期間と注意点を伝える
- 再交付申請から新しい在留カードが交付されるまでには、通常時間がかかります(即日交付される場合もあります)。
- 在留カード本体がない間も、不携帯の状態にならないよう注意が必要です。パスポートと警察への届出の控えを携帯しておくことが望ましいです。これらが在留カードの代わりになるわけではありませんが、警察官から職務質問を受けた際に、紛失手続き中であることを証明する助けになります。
- 身分証明ができないと、不法滞在者と疑われることがあります。もし意図的に在留カードを持ち歩かないと判断されると、最大で1年の懲役や20万円の罰金が科せられることがあり、処分の情報は記録され、次回の在留資格の更新にも影響が出ることがあるので注意が必要です。
5. 会社としてのサポート姿勢を示す
手続きに関して本人が不安を感じている場合や、日本語での手続きに困難がある場合は、会社として情報提供(手続き案内ページの共有など)や、必要に応じて可能な範囲でのサポート(書類準備のアドバイスなど)を行う姿勢を示します。
6. 新しい在留カードの確認
新しい在留カードが交付されたら、必ず会社に提示してもらい、内容(氏名、在留資格、有効期間など)を確認し、必要であればコピーを保管します。
一時帰国中に在留カードを紛失した場合
一時帰国や旅行などで海外にいるときに在留カードをなくしてしまった場合の対応についても、従業員に周知しておくことが重要です。
海外での対応手順
1. 現地の警察で届出
まず現地の警察署に行き、紛失を届け出ます。各国での手続きは異なるため、現地の警察に在留カードを失くしたことを伝え、適切な証明書をもらってください。この証明書は、日本での再発行申請の際に提出が必要になるため、コピーを何枚か取っておくことをおすすめします。
2. 再入国許可期限証明書が必要な場合
ビザが必要な国から日本に再入国する場合、帰りの便の搭乗手続きで再入国許可の期限がまだ有効だと証明する必要があります。在留カードがないと、この証明ができず、搭乗を断られることがあります。
この場合、「再入国許可期限証明書」を用意する必要があります。
再入国許可期限証明書の取得手順
1. 委任状の作成
証明書は日本の入国管理局が発行するので、代わりに手続きをしてもらうための「委任状」を、在留カードを無くした本人が作成します。
2. 代理人への依頼
「委任状」と「紛失・盗難の証明書」(現地の警察が発行したもの)を、日本にいる代理人にメールやFAXで送ります。
3. 代理人による手続き
日本の入国管理局で代理人に「再入国許可期限証明書」をもらってもらいます。
4. 証明書の受け取り
代理人から、再入国許可期限証明書をメールや国際郵便で送ってもらいます。
空港では、「再入国許可期限証明書」と「紛失・盗難の証明書」を見せて搭乗手続きを行います。
(参考:出入国在留管理庁 再入国許可申請)
3. 日本帰国後の再交付申請
海外では在留カードを再発行できないため、日本に帰国したあと14日以内に再発行の手続きを行い、新しい在留カードを交付してもらいます。
紛失したカードが見つかった場合
新しい在留カードをもらったあとに、以前なくしたカードが見つかった場合は、その日から14日以内に古いカードを返納しなければなりません。この点も従業員に伝えておきましょう。
企業が在留カードを預かることは禁止
厚生労働省は「外国人労働者の在留カードやパスポートを預かってはいけない」と決めています。
外国人の社員からこれらを取り上げることはもちろん違法ですが、紛失防止のために好意で預かることも禁止されています。外国人の社員から「保管をお願い」と言われても、うっかり預かってしまわないように注意しましょう。
法的リスク・注意点
在留カードの紛失・盗難は、従業員本人の責任において速やかに手続きを行う必要があります。会社としては、正しい手続きを促し、状況を把握しておくことが重要です。手続きを怠り不携帯の状態が続くと、ケース2で述べたような職務質問時のリスクや、本人の在留資格更新への影響も懸念されます。
押さえておくべき法的ポイントまとめ
外国人採用担当者として、在留カードの携帯義務に関して最低限押さえておくべき法的ポイントをまとめます。
携帯義務と提示義務
- 携帯義務: 中長期在留者は、常に在留カードを携帯する義務がある(入管法 第23条第2項)。
- 提示義務: 警察官、入国審査官、入国警備官などから提示を求められた場合、拒否できない(入管法 第23条第2項)。
罰則
- 不携帯の罰則: 携帯義務に違反した場合、20万円以下の罰金が科される可能性がある(入管法 第76条)。
- 提示拒否の罰則: 正当な理由なく提示を拒んだ場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科される可能性がある(入管法 第75条の2)。
- 再交付申請義務違反の罰則: 紛失・盗難から14日以内に再交付申請を行わなかった場合、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科される可能性がある(入管法 第71条の4)。
- 「逮捕」の可能性: 法律上罰則が規定されている行為であり、状況によっては(例:提示を強く拒否する、他の違反と併合されるなど)逮捕を含む厳しい対応がなされる可能性もあります。
例外規定
- 16歳未満: 携帯義務はありません。
- 在留カードの交付・再交付申請中など: 交付されるまでの間は、パスポートや在留資格証明書、登録証明書などを携帯する必要がある場合があります。また、再交付申請中の場合は「申請受付票」が在留カードの代わりとはなりませんが、不携帯の情状として考慮される可能性はあります。原則として、有効な在留カードを受け取るまでは、常に携帯が必要と考えておくのが安全です。
おわりに:適切な知識で、安心・安全な外国人雇用を
在留カードの不携帯は、外国人本人にとって罰則のリスクがあるだけでなく、採用担当者にとっても、採用時の確認漏れや不法就労助長のリスクに繋がる可能性がある重要な問題です。
今回ご紹介したケーススタディや法的ポイントを参考に、日頃から在留カードの重要性について社内で意識を高め、万が一の際にも冷静かつ適切に対応できる体制を整えておくことが、コンプライアンスを遵守し、外国人従業員が安心して働ける環境を作る上で不可欠です。
外国人材の受け入れ準備や採用活動そのものに関して、「外国人採用の手続きが複雑で不安…」「コンプライアンスを守れているか心配…」「採用後の定着や管理にも課題を感じている…」といった具体的な課題に直面されている企業様もいらっしゃると思います。
外国人採用に関するお悩み、Guidable Jobsが解決します!
Guidable株式会社では、日本最大級の外国人向け求人媒体「Guidable Jobs」の運営を通じ、様々な業界のニーズに合致する外国人材の採用活動を支援しております。
優秀な外国人材の採用にご関心をお持ちでしたら、まずはお気軽にお問い合わせください!
\ 初めての外国人採用も安心。Guidable Jobsが伴走します。/




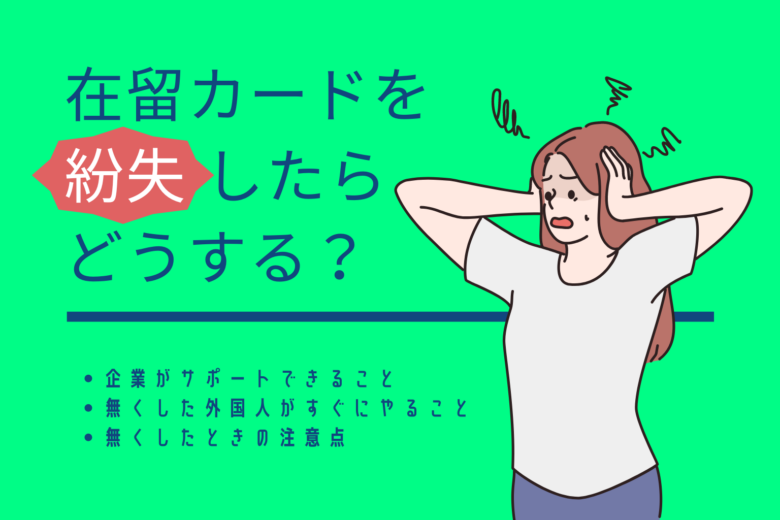







-2-780x520.png)