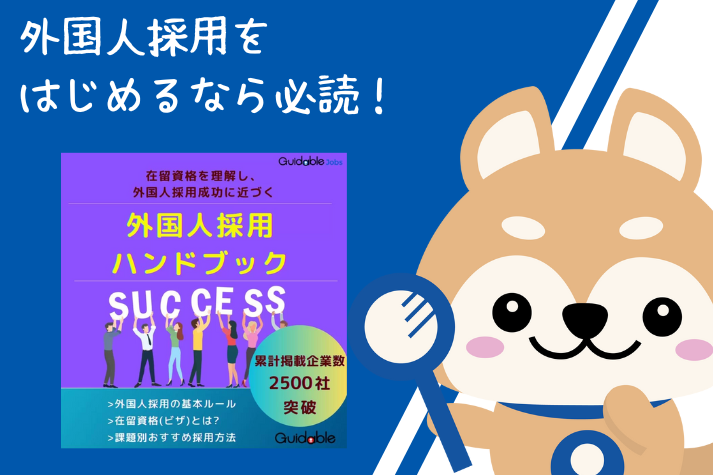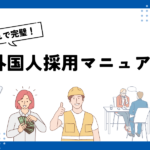外国人採用でおさえるべき法律はこちら! 抑えておくべき主要な法律についてまとめました

目次
外国人採用の法律:出入国管理および難民認定法
日本国内で外国人を雇用する際には「出入国管理および難民認定法」で定められたルールに基づいて雇用します。
外国人の雇用を考えている方には必須の法律です。今回の記事では外国人を採用する際に関わる法律について、詳しく解説いたします。外国人採用に関する法律の概要を把握しておくことで、問題を未然に防ぐことができるでしょう。
どんな法律?
「出入国管理および難民認定法」とは、日本に出入国するすべての外国人に対し定められた法律です。一般的に「入管法」と呼ばれているものです。入管法の起源は1951年に制定された「出国管理令」で、それから何度か改正されたうえで現在の入管法にいたります。
どこが改正されたの?
2019年4月に、大きな入管法の改正が行われました。新規で在留資格として「特定技能」が創設されたのです。
これまでは外国から日本に働きに来る人は肉体労働に近い仕事につきにくくしていました。しかし日本の少子高齢化によって労働力が減り、外国人を積極的に受け入れていく方針に変わりました。
特定技能とは?
特定技能は、「技能実習」の延長のような在留資格。技能実習では、特定の技能を習得する目的として、最長5年間の労働許可が与えられます。しかし期間を終えると、母国に帰らなければいけません。日本でより働きたい外国人が増えている中で需要を満せなくなってきました。そこで「特定技能」を新設したことにより、外国人労働者のニーズをより満たすかたちになります。
▼特定技能について詳しくはこちら
外国人採用の法律:雇用対策法

「雇用対策法」は日本における、労働についての基本的ルールが定められた法律。正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」です。
具体的には、青少年の労働の推進や、女性の安定した雇用、事業主は労働者に均等な機会を与えることなどが定められています。
2019年に入管法が改正され、新たに政府の「働き方改革」の意向が盛り込まれました。
それにともない、雇用対策法も改名されたのです。
現在は「労働施策総合推進法」と呼ばれています。
労働施策総合推進法
労働施策総合推進法は全部で九章あり、外国人の労働に関して定められているのは第七章です。
第七章では外国人を雇用する際の基本的な事項が定められています。
ここではさまざまなルールが定められていますが、要点をまとめると
「外国人を雇用する際は雇用状況に関する書面を用紙すること」
「外国人の中でも雇用が認められた者を雇用すること」
「外国人を雇用する際は労働時間や給料など差別せず、法律に基づくこと」
の3点が挙げられるでしょう。
とくに重要なのが、ひとつ目にあげた外国人を雇用する際に用意すべき書面。この書面を「外国人雇用状況届」といいます。
外国人の法律:外国人雇用状況届
「外国人雇用状況届」の提出は、外国人を雇用するすべての事業主の義務です。
外国人を雇用する際はもちろんのこと、離職する場合も必要となります。
「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」の改正に伴い、2017年10月から定められています。外国人雇用状況届に必要なことを書いて、ハローハークか外国人雇用状況届出システムで提出します。
外国人雇用状況届はすべての外国人に当てはまるわけではありません。
「外交」と「公用」以外の在留資格、あるいは「特別永住権」以外の外国人が対象です。また留学生が働くケースでは、提出する必要はありません。
外国人雇用状況届に記載する情報は以下です。
- 氏名
- 在留資格
- 在留期間
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 勤務先の住所
外国人雇用状況届に関する情報は、雇用する「外国人の在留カード」や「パスポート」をみせてもらって記入してください。とはいえ偽の在留カードやパスポートをみせてくる場合もあるので、何か不審な動きを感じたら入国管理局に連絡しましょう。
不法滞在の可能性があるためです。
記入事項に関してですが、雇用する外国人が雇用保険に加入する場合と、加入しない場合で記載事項が少し異なります。注意が必要です。
また提出先はハローワークか外国人雇用状況届出システムがあると先ほど説明しましたが、提出先によって提出期限や書式が異なります。こちらも注意が必要です。
外国人採用の法律:事業主の対処指針

事業主の対処指針とは、雇用対策法第八条に基づいて、事業主が適切な対処をするようまとめた指針です。なお正式名称は「外国人労働者の雇用管理改善等に関する事業主の対処指針」です。
具体的には以下のような内容です。
- 外国人の雇用について労働期間、業務内容、労働時間や休日などを書面で交付すること
- 外国人労働者のあっせんを受ける場合は法律で定められた届け出を行った団体のみとし、それ以外からは受けないこと
- 在留資格上、従事することが認められる者を雇用すること
- 外国人の国籍で賃金や労働時間を差別してはならない
雇用対策法の部分でも説明しましたが、事業主の対処指針の重要なポイントは以下の3つです。
- 外国人の雇用状況について書面で明示すること
- 就労資格のない外国人は雇用しないこと
- 外国人労働者を法律に基づいて労働時間や休日の確保などを守ること
ひとつめの「書面」とはさきほど解説した「外国人雇用状況届」のことです。
ふたつめは就労可能な在留資格をもっていない場合は、不法労働になることを意味します。
そのため雇用側は就労不可な在留資格なのかを見極める必要があります。ここでは詳しく解説しませんが、在留カードを確認することでチェックできます。
外国人採用の法律:不法就労助長罪
冒頭で説明しましたが、日本に入国した外国人の基本的なルールは入管法で定められています。もし雇用した外国人の不法労働が発覚した場合、「不法就労助長罪」として罰せられます。
助長とは「助けること」を意味し、わざとではなくても「不法労働を助けた」とみなされます。不法就労罪となれば、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が課せられます。
不法労働となるのは、不法滞在者を雇用するケースや、就労不可の外国人を雇用するケース、外国人労働者が規定の労働時間を超えて労働させるケースがあげられます。
外国人の雇用に関する知識が乏しく、雇用側が知らずに雇用した外国人が就労不可だったケースは往々にしてあります。注意が必要です。
外国人採用の法律については詳しくなりましたか?
外国人採用の法律についての理解が深まったでしょうか?
外国人を雇用する際の法律を理解しておかなければ、知らずのうちに「不法労働」となってしまうリスクもあります。
不法労働のリスクを最小限に抑えるためにも、外国人を採用する際の法律を把握しておいてください。