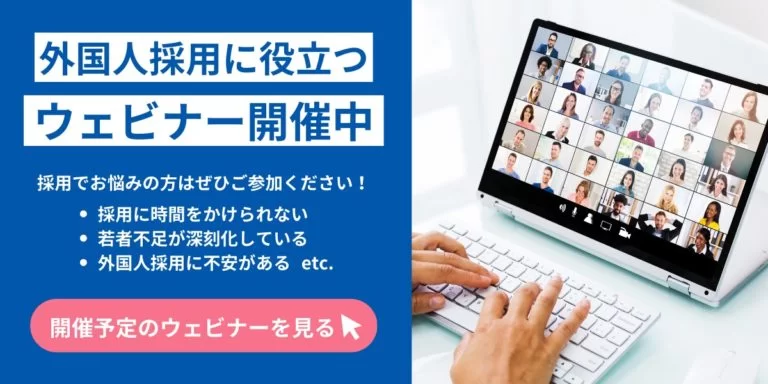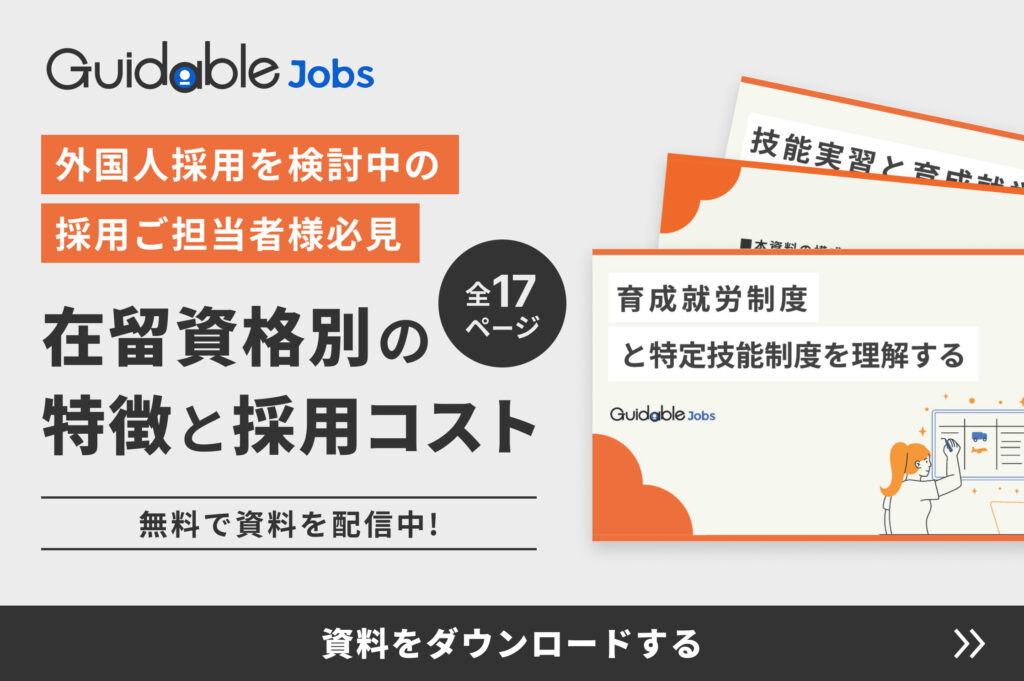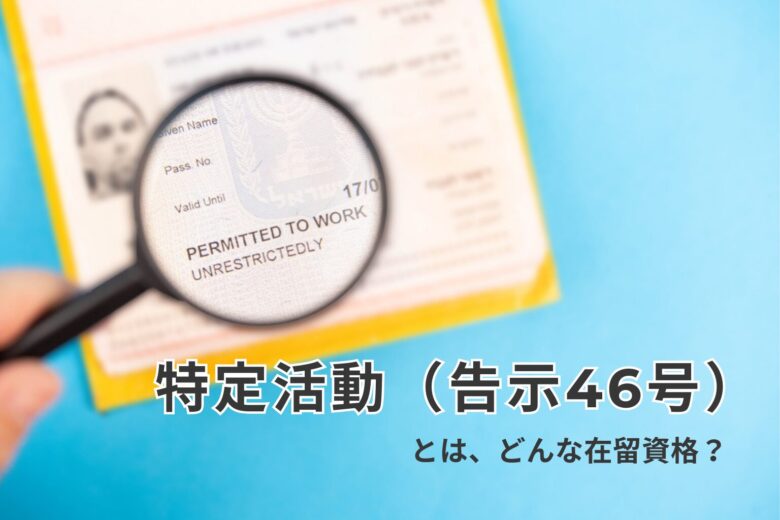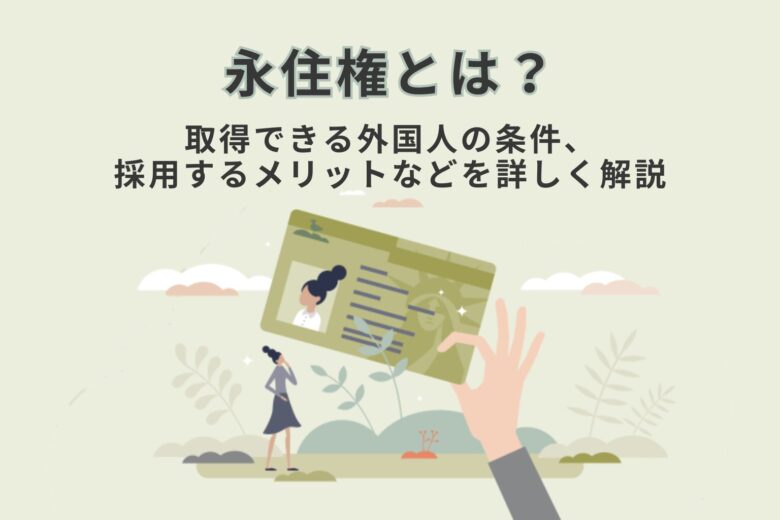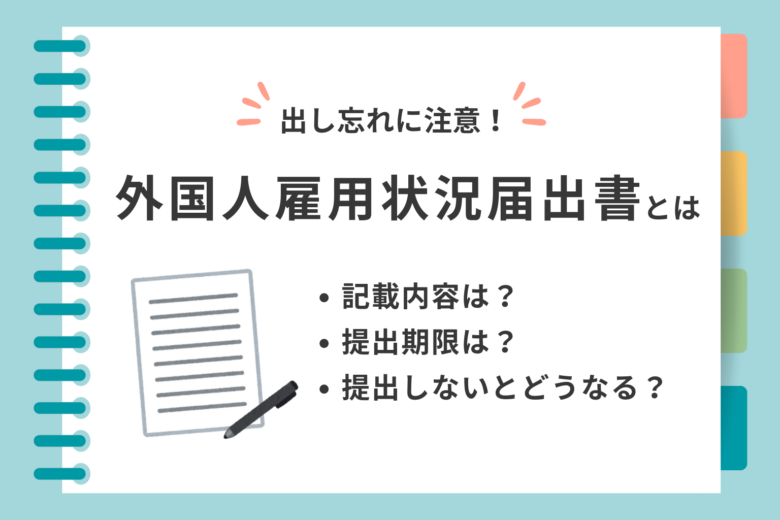研修生制度(外国人技能実習生制度)を正しく理解! 劣悪な労働環境、賃金安などの問題について
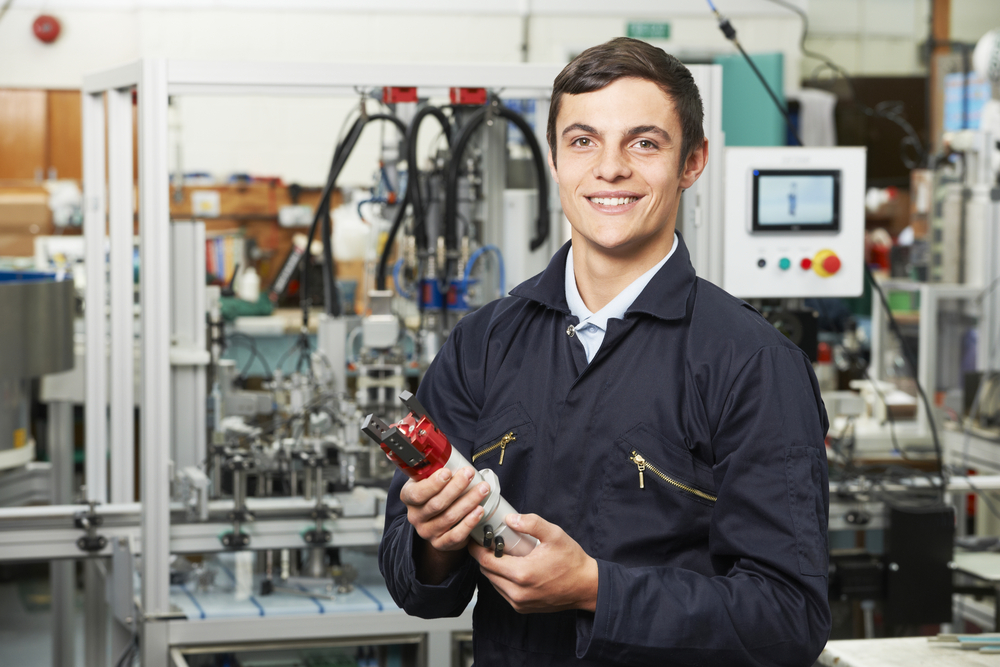
日本には研修生・実習生として、外国人留学生を企業で雇用する制度、「技能実習制度」があります。
この制度では海外の優秀な人材に技術を学んでもらい、その技術やノウハウを母国に持ち帰って経済発展を担う制度です。今回は発展途上国の支援の一環として、50年以上かたちを変えて継続している、この研修生制度についてまとめました。
目次 [非表示]
研修生制度とは?

研修生制度である「外国人技能実習制度」は外国人を企業が雇用し、さまざまな技能を習得してもらうという制度です。
「あくまでも研修の制度であり、雇用の需要と供給を合わせるための手段としてはならない」と示されています。あくまでも研修であり、雇用するための制度ではないということですね。
研修生制度の歴史、始まりは60年代
日本には1960年代から外国人の研修制度が存在していました。1960年代後半から始まったこの制度は、発展途上国の人材に対して日本の企業で技術研修を行い、帰国後にその技術を活かしてもらうことが目的でした。この研修制度は政府主導で行われ、企業が研修生を受け入れ、技術指導を一定期間行うというものでした。
この制度はその後1980年代に入ってから、国際協力の一環としてさらに拡充されました。1993年に正式に外国人技能実習制度が発足する以前のこれらの研修制度は、技能実習制度の基礎となり、その理念や運用方法が引き継がれるかたちで進化していきました。
93年に発足した外国人技能実習制度
「外国人技能実習制度」は、1993年に発足しました。当初は発展途上国への技術の移転を目的としており、実習生が日本で技能を習得して帰国後に活かすことをめざしていました。
2009年には制度改正が行われ、実習期間が3年から5年に延長されました。
しかしながら労働環境の悪化や、人権侵害の問題が指摘され、2017年には技能実習法が施行され、監督機関の設立や実習計画の厳格化が行われました。
2021年にはさらなる改善策が導入され、労働環境の整備と実習生の権利保護が強化されました。
しかしこのようにたび重なる変更をしてきましたが、途上国支援という実態とは乖離した状況はつづき、きびしい職場環境に置かれた実習生の失踪があいつぎました。
| 年 | 失踪者数 |
| 2016 | 約5,000人 |
| 2017 | 約7,000人 |
| 2018 | 約9,000人 |
| 2019 | 約10,000人 |
| 2020 | 約6,000人 |
| 2021 | 約7,000人 |
2023年の11月には政府の有識者会議は、「この制度を廃止する」とした最終報告書をまとめました。今後は「育成就労制度」と名前が変更され、ルールも変わります。
▽育成就労制度について、詳しくはこちらから
特定技能とは? 外国人技能実習制度となにが違う?
「特定技能」と「技能実習」は、日本における外国人労働者受け入れの制度ですが、目的と要件は明確に異なります。技能実習制度は「発展途上国への技術移転」を目的としており、実習期間中に技術を習得して、帰国することが前提です。それゆえ技能実習生は最長5年間の滞在が認められています。
一方で特定技能制度は「労働力不足を補うための制度」であり、すぐに戦力として日本で働いてもらうことを目的としています。特定技能には1号(最長5年滞在)と2号(永続的な滞在が可能)の2種類があり、特定技能2号になれば、家族の帯同も認められています。
つまり特定技能は、より長期的かつ安定的な労働力の確保を目的としているのです。
▼特定技能について詳しくはこちら
技能実習生は日本にどれぐらいいる?
技能実習生は日本に約410,000人(2023年10月末時点)程度います。
近年、その数は増加傾向にあり、特に2010年代後半から急増しました。これは日本の労働力不足に対応するため、外国人労働者の受け入れが拡大されたためです。
新型コロナウイルスの影響で2020年には一時的に減少しましたが、ふたたび増加基調に戻りつつあります。
技能実習生を受け入れる方法は?
実習生を受け入れる方法は2つあり、単独の企業で受け入れる「企業単独型」と、協同組合や商工会議所などの非営利団体が受け入れ、企業で実習をする「団体管理型」という2つの方法とそのほかに受け入れ条件があります。
企業単独型とは
大手企業などが直接現地の法人に出向いて、常勤職員として受け入れる方法です。
法務省、厚生労働省の資料によると、2022年末時点の技能実習生の受け入れ割合は企業単独型は1.7%(5,394人)です。
団体管理型とは
団体管理型は単独での受け入れが困難な中小企業からの研修機会拡大のニーズを受けて、平成2年8月より導入された方法です。
中小企業の団体や商工会議所などが受け入れ先となります。
このときの受入団体は、公的制度の外国人技能実習制度であるため、非営利団体に限ります。
団体型が全体の98.3%(31万9,546人)のため、大半を占めています。
受け入れ人数の制限
外国人技能実習制度では、一年間に受け入れていいとされている人数は基本的に「事業所の人数の20分の1」です。
これは大企業などの301人以上の事業所の場合で、それ以下の事業所の人数は以下のように定められています。
| 会社の規模 | 上限の人数 |
| 201人以上、300人以下の場合 | 15人以内 |
| 101人以上、200人以下の場合 | 10人以内 |
| 51人以上、100人以下の場合 | 6人以内 |
| 50人以下の場合 | 3人以内 |
受け入れ可能な職種
受け入れられる職種にも制限があり、2023年の10月末時点では90職種165作業が該当します。
詳しくは厚生労働省が公開している、「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」をご覧ください。
技能実習制度の問題点
技能実習生の労働環境に問題
技能実習制度における労働環境の悪化は深刻な問題です。多くの実習生が過酷な労働条件、長時間労働、低賃金、不適切な待遇に直面しています。これにより実習生が健康を害したり、労働災害に巻き込まれるケースが増えています。さらに一部の企業では労働基準法を無視し、実習生に対するハラスメントが報告されています。
これらの問題は、受け入れ機関や監督機関の監視が不十分であること、実習生が日本の労働法規について十分に知らないこと、言語の壁が存在することなどが原因です。また実習生が借金をして来日している場合、劣悪な条件を受け入れざるを得ない状況に追い込まれやすいです。
これらの問題に対処するため、日本政府は監督体制の強化や法規制の厳格化を進めていますが、根本的な改善にはまだ多くの課題が残っています。労働環境の改善と実習生の権利保護が急務です。
技能実習生の賃金が安い?
技能実習生の賃金が外国人正社員より安い、という実態が浮き彫りになっています。
正社員での雇用は平均が27.6万円、実習生での雇用は18万円以下が半数以上を占める結果になっています。外国人正社員に限ると日本人と同水準の給与になっていますが、実習生となるとかなり低いのが実情です。
これは実習生が3年間しか在留資格がないので、高度なことを任せることができないという実情があります。高度なことを任せることが難しい上に、長期的に雇うことができないため賃金は低くなりがちです。
また中小企業、零細企業では深刻な人手不足が顕在化しており、制度の趣旨とは違い、労働者確保のために外国人技能実習制度を利用したり、実習生側も日本の高賃金を期待して出稼ぎとして、外国人技能実習制度を利用している場合が少なからずあります。
技能実習制度から育成就労制度へ
外国人の人材を獲得するうえで、技能実習制度は国内企業でしっかりと使われていたケースもありました。しかしながら、その一方で問題となるケースも多く、世界から見ても「現代の奴隷制度」と表現され、批判が高まっていました。
技能実習制度で問題となっていた部分が、育成就労制度では見直されることが期待されています。
今後どのように育成就労制度が使われていくのか、世間的な注目が集まっています。
外国人採用ハンドブックを見てみる⇒資料はこちらから