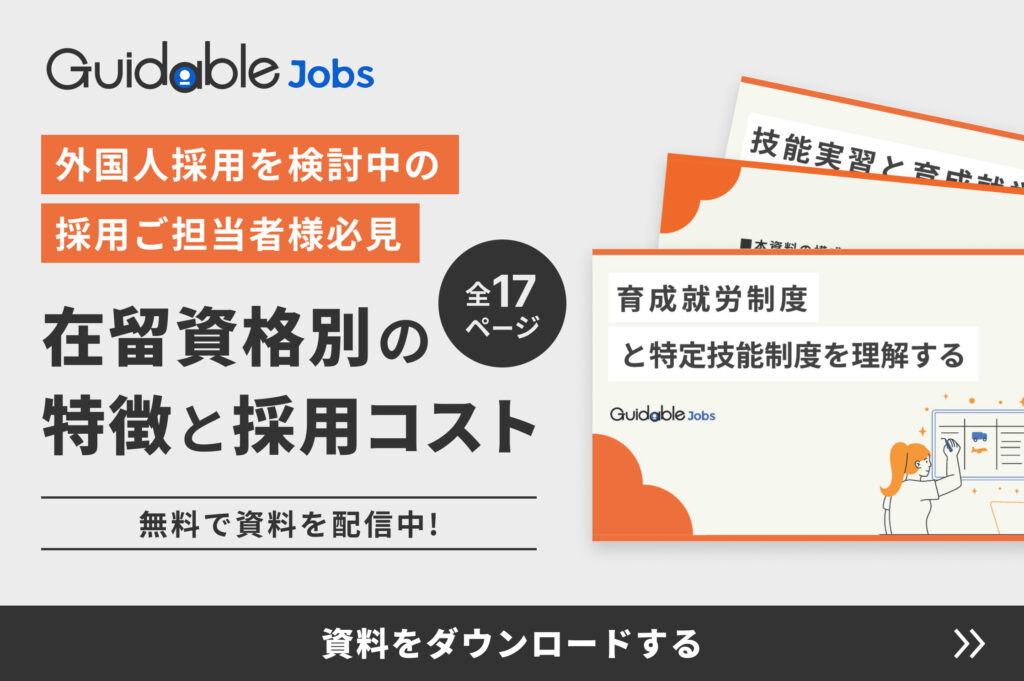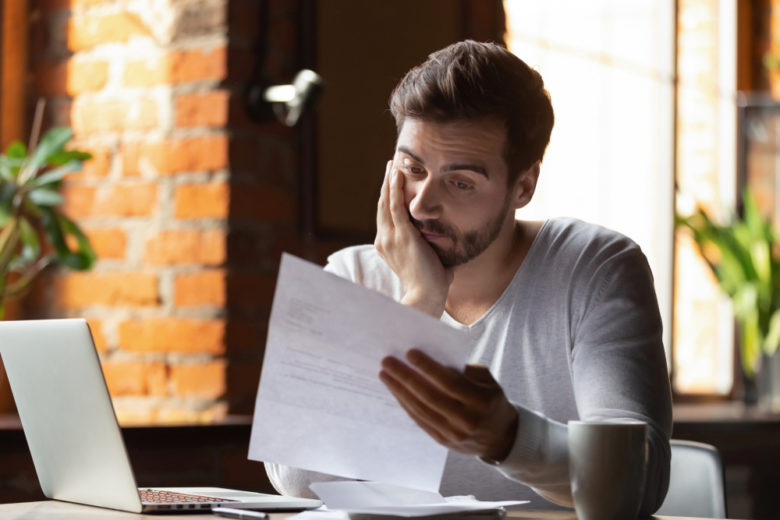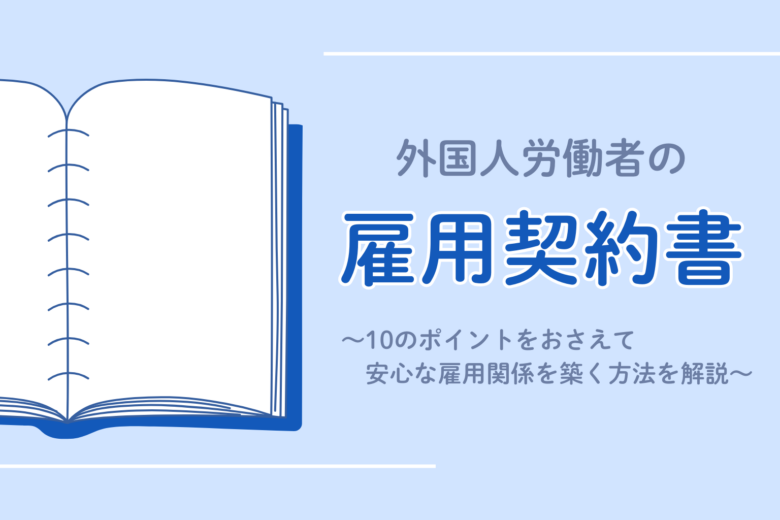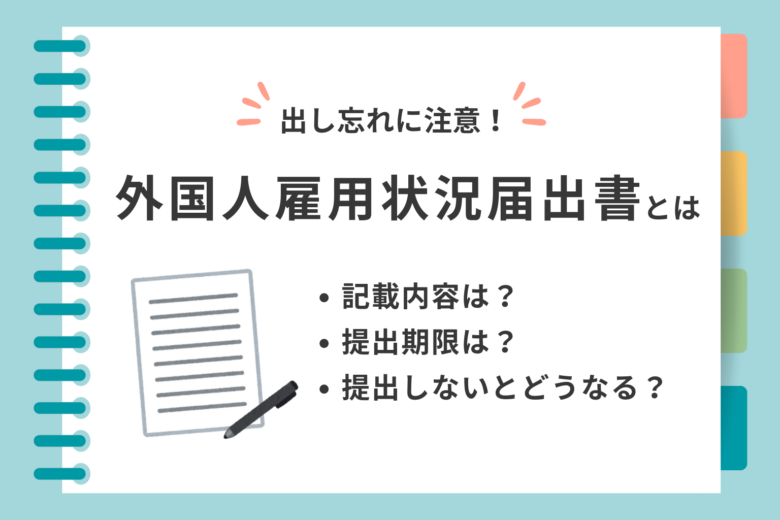技能実習生の給与はどのくらい? 賃金を支払うときに気をつけるべきこと

外国人技能実習制度は、日本の進んだ技術を外国へ教えることで、母国の成長のために外国人の勉強の場となる制度として創設されました。技能実習生(この制度は「育成就労制度」に変わることが決まっています)の受け入れを検討している企業さまの中には、給与の額はどのくらいなのか、相場を知っておきたいという方も多いでしょう。
今回は技能実習生への給与相場、給与を支払う際に気をつけることなど、重要な点について解説いたします。
目次 [非表示]
技能実習生への給与に相場はある?
まず初めに、技能実習生の給与の相場を見てみましょう。「特定技能」や「身分系の人材」「留学生など(その他)」と比較したデータが以下です。ちなみに参照したデータは、厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」です。
| 在留資格区分 | 平均給与 |
| 外国人労働者の平均 | 24万8,400円 |
| 専門的・技術的分野 (特定技能を除く) | 29万9,600円 |
| 特定技能 | 20万5,700円 |
| 身分系の人材 | 28万700円 |
| その他 (特定活動及び留学以外の資格外活動) | 22万900円 |
| 技能実習 | 17万7,800円 |
表からもわかるように、技能実習生の平均給与はかなり低い額になっており、この点に大きな問題があることがわかるでしょう。
技能実習生の給与を考える上で大切なこと
技能実習生(今後は育成就労制度を利用して日本にくる方)に対しての給与を考えるうえで、大切なのは以下のようなことです。
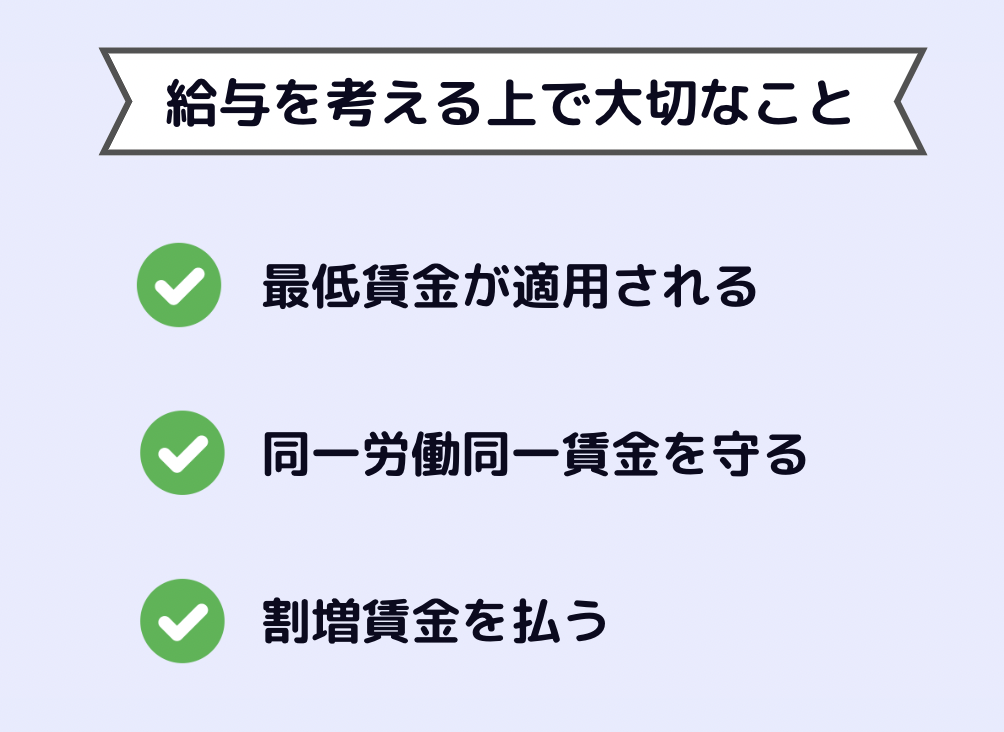
最低賃金が適用される
技能実習生に対しても、原則として日本人の労働者と同じ給与の水準で支払うことが必要です。
最低賃金とは?
最低賃金は「労働者の生活の安定と、賃金の底上げを図る」ためのものです。日本で働いている方には出身の国籍に関係なく、非常に重要です。
最低賃金は以下の2種類があります。
| 種類 | 内容 |
| 地域別最低賃金 | 各都道府県ごとに設定される最低賃金です。その地域の経済状況や物価水準を考慮して決定されるため、各地域で異なります。 |
| 特定(産業別)最低賃金 | 特定の産業に対して設定される最低の賃金で、ふつう「地域別最低賃金」よりも高く設定されます。特定の産業労働者が対象です。 |
技能実習生の賃金を設定するときには、上記のどちらも適用されるときにはより高い方を設定する必要があります。もし最低賃金を下まわると、受け入れの停止になることがあります。
同一労働同一賃金
同一労働同一賃金は、同じ仕事をするなら正規雇用でも非正規雇用でも同じ額の賃金を払うというルールです。もし同じ労働をしていても、賃金が違っていると不信感などが生まれるのは想像に難くありません。
技能実習制度では、転籍が原則不可とされていたことから、話に聞いていたことと違う条件で働くことになっても、外国人としては働かざるを得ない状況になっていました。しかし今後変わる予定の「育成就労制度」では、本人の以降による転籍が可能になっています。今後は外国人人材の流動生がさらに高まることから、このようなルールを守ることが企業にとってはさらに重要になります。
割増賃金を払う
もし技能実習生に、時間外勤務や休日の勤務をしてもらった場合には、やはり日本人と同様で「割増賃金」を支払う必要があります。
割増賃金の種類は以下の表のようになります。
| 割増賃金の種類 | 内容 |
| 残業手当(時間外労働割増賃金) | 法定労働時間(ふつうは1日8時間、週40時間)を超える労働時間に対して支払われる割増賃金。 割増率は25%以上 |
| 休日手当(法定休日労働割増賃金) | 法定休日(ふつうは週1日)に労働した場合に支払われる割増賃金です。 割増率は35%以上 |
| 深夜手当(深夜労働割増賃金) | 午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働した場合に支払われる割増賃金。 割増率は25%以上 |
たとえ技能実習生と合意のうえで、時間外労働で発生する賃金を低く設定していた場合でも、上記の割合に基づく算出額を下まわるときには、労働法基準の違反になります。
技能実習生の給与を最低賃金に設定することのリスク
技能実習生の給与を最低賃金に設定するのは法的には問題ないですが、それでも多くのデメリットやリスクがあります。具体的なケースにも触れながら、この点について考えてみましょう。
労働環境の悪化が失踪などにつながる
最低賃金での雇用は、労働者にとって経済的な不安を増大させる要因です。生活費が高い地域では生活が成り立たず、仕事に対してモチベーションも低くなり、生産性が落ちていく悪いループに入ります。
技能実習生の失踪はよくニュースになっていますが、最低賃金で働かせている、もしくは最低賃金すら払っていない、ということが多く関わっています。
労働者の権利侵害で転職のおそれ
技能実習生はまだ日本に慣れておらず、言語や文化の違いから権利を理解してないことが多いです。社会から不当な扱いを受け、権利侵害と感じる方もいるでしょう。
技能実習生は、条件によってはほかの在留資格である「特定技能」への移行が可能です。また技能実習制度の代わりの新しい制度である「育成就労」制度では転籍が可能なため、能力に応じて高い給与を設定してくれる企業へと転職することがより考えられます。
いずれにしても、「最低賃金を守っていればいい」と考えるのではなく、企業はしっかりと個人を評価して、外国人労働者からも信頼される存在になっていく必要があります。
給与面以外でも、技能実習生を受け入れる上で知っておくことは?

保険の加入義務
技能実習生は、日本の労働基準法の適用を受けます。労働保険に加入するのは義務であり、もし仕事中や通勤中の事故でのケガや病気には保険が適用されます。
36協定(時間外労働、休日労働に関する協定)
この36協定とは、労働基準法の第36条で定められている労使協定のことです。
36協定では時間外労働の上限は、原則として月に45時間、年360時間と決められています。
上限を超えた労働をさせることがないように、企業がしっかりとマネジメントする必要があります。
ハラスメント対策
企業は技能実習生に対する、セクハラ、パワハラを防止する対策をする必要があります。ハラスメント防止のための研修、相談窓口の設置などをしましょう。
生活支援
技能実習生に対して、安全で衛生的な環境の住居を提供しましょう。日本語教育や生活指導も必要です。
帰国後の技能実習生といくつかの問題について
充分に評価されないスキル
多くの技能実習生が帰国後、母国での職に就こうとするものの、期待する賃金を得られず再び日本に戻ることを希望するケースが多いようです。これは日本で得たスキルや経験が母国では十分に評価されないことや、日本での生活費や借金返済の負担が大きいためといわれています。
具体的な帰国後の状況について、ベトナム人の実習生に関する調査では、母国の日系企業での雇用が限定的であることや、もとめる賃金と実際の賃金のギャップが問題となっていることが理由としてあるようです。
問題を解決するには
単純な労働を長時間、過酷な状況でさせられる技能実習生は、母国に帰ってもあまり評価されないという状況が明らかになっています。このような問題を解決するには、外国人労働者にとってもよりスキルを磨いていく、キャリアパスをしっかりと企業とともに考えることが大切です。
技能実習制度に代わる制度として、育成就労制度ができることが決まりましたが、こちらの制度ではより、特定技能1号の技能水準の人材を育成することをめざすという意向がはっきりしています。
育成就労から特定技能へ、そして永住権を得て、より高いレベルの仕事ができるように、日本企業とともに成長していく姿勢が必要になります。
まとめ
外国人を雇用する際には、同一労働同一賃金がとても大切です。技能実習制度は育成就労制度へと変わる予定です。この制度ではより人材の流動性が高くなります。
外国人からもいい企業が選べるようになるため、企業は制度作りや実習生に対しての支援が大切になります。
外国人採用ハンドブックを見てみる⇒資料はこちらから