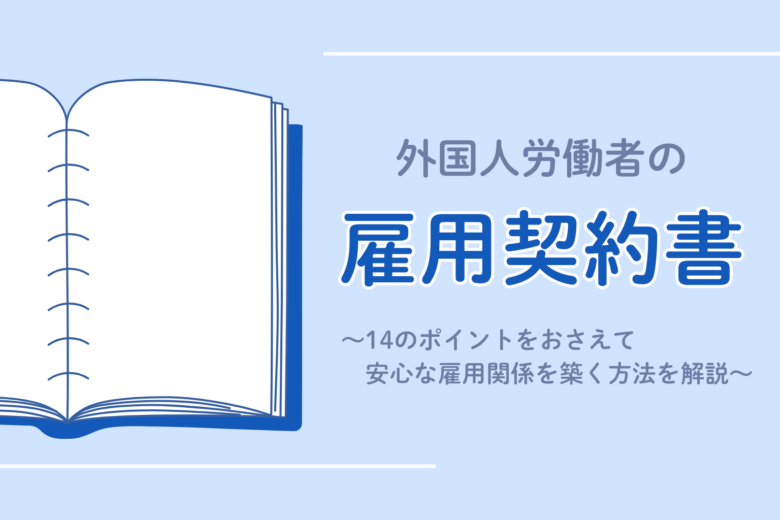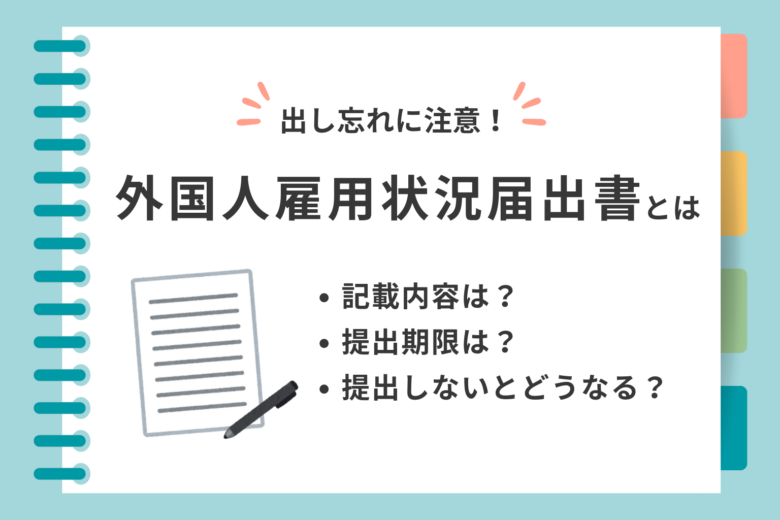外国人と日本人にかかる税金の違い|どの税金に違いがあるのか、租税条約で軽減・免税ができるのか具体例を用いて解説!

外国人労働者を雇用したり、外国人と一緒に働くことは珍しくない時代になりました。
日本政府も外国人雇用の増加に向けて積極的に取り組んでいるため、受け入れを検討している企業は少なくありません。
採用担当者の中には、「通常の税制に加えて、外国人に特有の税制も学ばないといけないのは大変…」と感じている方も多いです
この記事では、外国人と日本人にかかる税金の違いをわかりやすく説明します。
税金の仕組みを知り「どこが違うのか?」という疑問を解消するための参考にしてください。租税条約などの最新情報も交えながら、役立つ知識をお伝えします。
目次
代表的な税金は、日本人と外国人で違うの?
日本では、住んでいる期間や滞在の仕方によって税金のルールが変わります。とくに外国人の場合「居住者」と「非居住者」に分かれ、それぞれ課税の対象が異なるため、注意が必要です。
外国人は「居住者」か「非居住者」かで税金が変わる
一般的に日本に「住所」があるか、1年以上住んでいる場合は「居住者」となり、日本だけでなく海外で得た収入にも税金がかかります。
一方、それ以外の人は「非居住者」となり、日本で得た収入のみに税金がかかる仕組みです。
企業が外国人を雇うときは、従業員の滞在状況を確認し、正しく税金を計算することが求められます。
日本人と外国人(居住者・非居住者)で異なる税金一覧
私たちに身近な税金について、日本人と外国人の違いをまとめました。
| 税金の種類 | 日本人 | 外国人(居住者) | 外国人(非居住者) |
| 所得税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(一律20.42%) |
| 住民税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 非課税 |
| 固定資産税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| 不動産取得税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| 相続税 | 課税 | 課税(条件あり) | 課税(条件あり) |
| 贈与税 | 課税 | 課税(条件あり) | 課税(条件あり) |
| 消費税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| 酒税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
| たばこ税 | 課税 | 課税(日本人と同じ) | 課税(日本人と同じ) |
外国人に関係する税制のポイントは、所得税や住民税などの直接税には違いがあることです。一方で、消費税や酒税などの間接税は、日本で生活するすべての人が同じように支払います。
直接税とは?
直接税は、納税者が自分で政府に支払う税金のことです。所得税や住民税、相続税などがこれにあたります。税金を負担する人と、実際に納める人が同じなのが特徴です。
間接税とは?
間接税は、商品やサービスを買うときに、間接的に支払う税金です。たとえば、消費税や酒税などがあり、お店で商品を買うときに含まれています。
実際に税金を納めるのは販売店やメーカーですが、負担するのは消費者です。
それぞれの税金の違いをチェック!

外国人も日本の税金のルールに従って手続きをしなければなりません。先ほどの一覧で紹介した税金の違いについて、具体的にどのような点に注意すべきかを説明します。
「所得税」は外国人が非居住者の場合に税率が変わる
所得税は、給料や賞与などの収入にかかる税金です。日本の所得税は「累進課税」と呼ばれる仕組みで、所得が多いほど税率が高くなります。
日本人は、国内だけでなく海外で得た収入にも税金がかかり、税率は5%から最大45%まで上がる仕組みです。ただし、医療費控除や生命保険料控除、扶養控除などを利用すると、実際に支払う税金が減る場合があります。
居住者の外国人にかかる所得税
「居住者」の外国人は、日本人と同じように海外で得た収入も課税対象となり、累進課税が適用されます。そのため、医療費控除や生命保険料控除など、さまざまな控除を受けることができ、税金の計算方法も日本人と変わりません。
非居住者の外国人にかかる所得税
「非居住者」の外国人は、日本国内で得た収入のみに税金がかかります。
たとえば給料をもらう場合、一律20.42%の税率が適用され、会社が税金を差し引く「源泉徴収」という方法で納めます。ほとんどの場合、これで税金の手続きが完了するため、年末調整をする必要はありません。
また、非居住者は使える控除が限られています。適用されるのは「基礎控除」「寄附金控除」「雑損控除」の3種類のみです。そのため、日本人や居住者の外国人が受けられる医療費控除や扶養控除は使えず、税金の負担が大きくなる可能性があります。
さらに、日本に不動産を持っていて家賃収入がある場合や、源泉徴収だけでは税金が足りない場合は、確定申告をしなければなりません。状況によって手続きが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
外国人の源泉徴収【2025年版】居住者・非居住者の判定方法と税率早見表
「住民税」は外国人が居住者になった時点で課税対象になる

住民税は、住んでいる地域の行政サービスに必要な費用をまかなうために支払う税金です。前年1月1日から12月31日までの国内外の所得をもとに計算され、毎年1月1日時点で日本に住所がある人が納めることになっています。
税率は一律10%で、医療費控除や生命保険料控除などを利用することで、負担を軽くすることが可能です。支払い方法には、給与から自動的に引かれる「特別徴収」と、納付書を使って自分で支払う「普通徴収」があります。
居住者の外国人にかかる住民税
外国人でも、日本に住んでいて前年に一定以上の所得があれば、日本人と同じように住民税がかかります。税率や控除の仕組み、納税方法も日本人と変わりません。
非居住者の外国人にかかる住民税
1月1日時点で日本に住所がない外国人は、住民税を支払う必要がありません。たとえば、前年の12月に日本に来て、そのまま1月1日までに住所を持たなかった場合、その年の住民税は課税されません。
年の途中で居住者になった場合の住民税
年の途中から日本に住み始めた場合、翌年の1月1日時点で住所があれば、住民税の課税対象になります。
たとえば、2025年4月に日本に来て住み始めた場合、2025年の所得に対する住民税は2026年から支払うことになります。ただし、日本に来る前(2025年3月以前)に得た所得は住民税の対象外となるため、2026年の課税対象は2025年4月以降の所得(国内・海外)だけになります。
「固定資産税」や「不動産取得税」は外国人の居住形態にかかわらず課税対象になる

固定資産税は、日本の土地や建物の所有者に対して課税される税金です。また不動産取得税は、日本で新しく土地や建物を買ったときに支払う税金です。これらの税金は、日本人だけでなく、外国人の居住者や非居住者も対象になります。
一方、日本ではなく海外の土地や建物を所有している場合は、その国の税制度に従うため日本で税金を支払う必要はありません。
ただし、居住者が海外の不動産を貸して家賃収入を得た場合、その収入は「国外源泉所得」として扱われます。日本の税法では、居住者は世界中で得た所得が課税対象になるため、海外の家賃収入も日本で申告しなければなりません。
海外ですでに税金を支払っている場合は「外国税額控除」を使うことで、日本での二重課税を避けられる可能性があります。
「相続税」や「贈与税」は関係者の居住条件で課税範囲が変わる
相続税とは、亡くなった親など(被相続者)からお金や土地などの財産を受け継いだ人(相続者)が、受け取った財産に対して課される税金です。
贈与税は、誰か(贈与者)から財産を受け取った人(受贈者)がその金額に応じて課される税金です。
日本人は財産が「日本国内の財産」「海外の財産」どちらの場合でも、基本的に受け取ったすべての財産が課税対象になります。
冒頭の一覧表に「課税(条件あり)」と記載しましたが、この条件とは関係する外国人が「一時居住者 ※」に当てはまるかどうかという点です。相続税と贈与税には「非居住者」という区分がなく、そのかわりに「居住者」「一時居住者」の2区分で課税範囲が決められます。
※「一時居住者」とは
以下2つの条件のどちらも満たしている外国人のことを指します。
■身分系(永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)以外の在留資格を持っている
■過去15年以内に日本に住んでいた期間が合計10年以下である
相続者(または受贈者)が居住者の場合
外国人が一時的ではない居住者の場合、被相続者(または贈与者)が外国人であっても「日本国内の財産」「海外の財産」どちらも課税対象になります。
相続者(または受贈者)が一時居住者の場合
- 被相続者(または贈与者)が10年以内に日本で生活していた期間がある日本人の場合、「日本国内の財産」「海外の財産」どちらも課税対象になります
- 被相続者(または贈与者)が上記以外の場合は「日本国内の財産」のみ課税対象になります
租税条約を理解して、外国人の二重課税を回避しよう

租税条約とは、二重課税の排除や脱税を回避するために日本と海外の二国間で締結される条約です。租税条約を結んでいる国から来た外国人は、二重課税を防ぐために外国税額控除を受けることができます。
【適用例】外国人労働労働者と租税条約
具体的に、租税条約でどのような免税措置が受けられるのかを紹介します。
中国から来日した留学生へアルバイト代を支給する場合
たとえば、中国から来日した留学生が「資格外活動」で何らかのアルバイトをするとします。
この場合「日中租税協定第21条」が適用され、日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば免税とされます。
インド企業からの派遣労働者への対価を送金する場合
インドの会社にコンサルティングやソフトウェア開発などの人的役務を外注した場合などが、これに当てはまります。
通常、国内法では源泉所得税(一律20.42%)が課税されますが「日印租税条約第12条」の適用により、税率を10%に軽減できます。
そのほかにも、経済的・文化的交流の促進をはかるために工業所有権や著作権の使用料が軽減されるなど、国によって様々な内容があります。
租税条約に規定されている項目の適用を受けるには、原則として届出が必要です。
支払者(源泉徴収義務者)を通して税務署に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があるため、外国人労働者を雇用する際は出身国と締結されている条約を確認しておきましょう。
外国人労働者が税金を滞納するとどうなる?

税金を納めないと、延滞金が発生するだけでなく、財産の差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があります。
とくに外国人の場合、税金を滞納すると在留資格の更新や再入国に影響が出ることがあります。税務署から督促状が届いたり、調査の対象になったりすることもあり、勤務先の企業にとっても信用問題に発展する恐れがあるので注意が必要です。
滞納が続くと行政処分を受けることもあるため、期限を守って税金を納めることが大切です。トラブルを防ぐためにも、疑問があれば専門家に相談し、必要に応じて納税管理人を選任するとよいでしょう。
納税管理人とは?
納税管理人とは、税金を納める人が日本にいない場合に代わりに手続きをする人のことです。具体的な役割として、次のようなものがあります。
- 納税通知書の受け取り:納税者に代わって税務署からの通知を受け取る
- 税金の納付:本人の代わりに税金を支払う
- 還付金の受け取り:税務署からの税金の払い戻しを受け取る
- 税務関連の書類の管理:税務署から届く書類を受け取り、適切に処理する
外国人労働者が退職して母国に帰る場合、納税管理人は以下のような場面で必要になります。
- 海外移住後の退職金の申告:退職後に海外へ移住する際、退職金に源泉徴収が適用されるため、確定申告をする必要があります。
- 住民税の納付:退職後も住民税の支払いが必要な場合、納税管理人が代わりに納税します。
このように、海外へ移住する人が日本の税務手続きをスムーズに進めるためには、納税管理人が大きな役割を果たします。
納税管理人を選ぶ際は、税務署に「納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。日本国内に住所や居所がある人であれば、個人・法人どちらでもなれますが、一般的には親族や税理士など、信頼できる人が選ばれることが多いです。
さいごに
今回は外国人労働者と日本人労働者の税制の違いについて紹介しました。最初は戸惑うことがあるかもしれませんが、仕組みを理解すれば雇用の計画を立てやすくなり、税務リスクの管理にも役立ちます。
外国人の採用は企業にとってグローバルな視点を広げる機会となり、成長につながる可能性があります。このチャンスを活かし、新たな人材の採用を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。








-780x520.png)
-1-780x520.png)





-2-780x520.png)


-2-780x520.jpg)