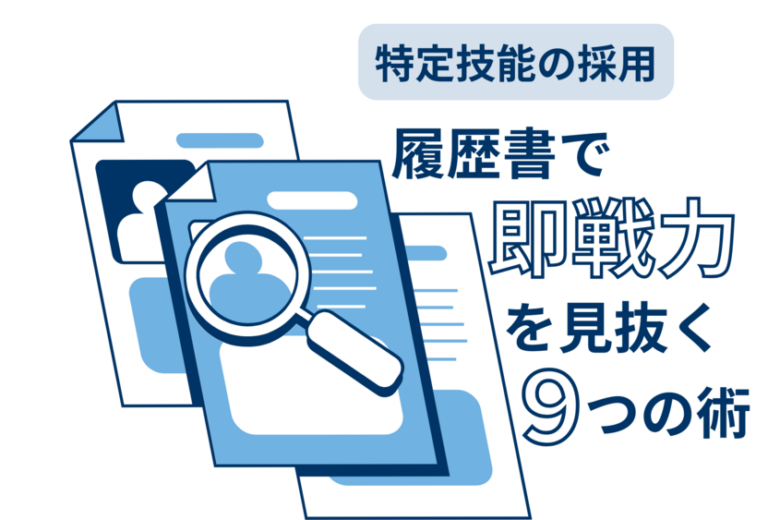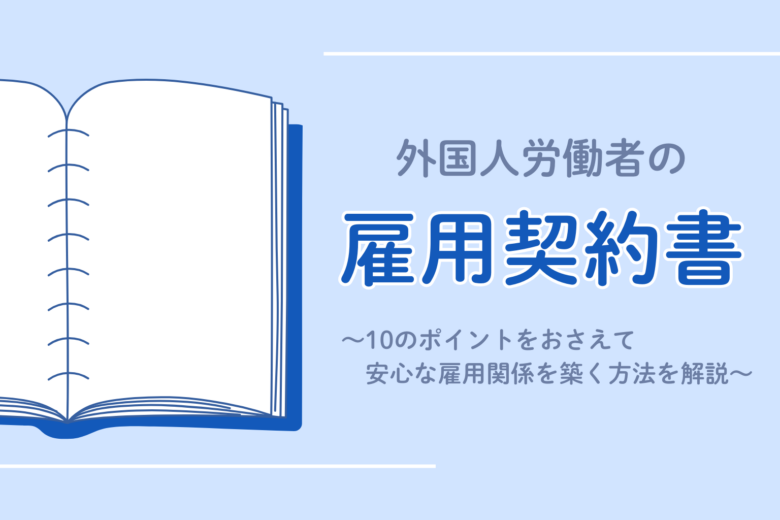特定技能外国人の受け入れ方法とは? 制度と手続きの基本を解説

特定技能外国人を受け入れるためには「どんな手続きが必要なのか」「対象となる職種には何があるのか」など、最初はわかりにくいことが多いかもしれません。
この記事では、制度のしくみから手続きの流れ、実際の準備で気をつけたい点まで、順を追ってわかりやすくまとめています。
これから外国人の採用を考えている企業だけでなく、すでに受け入れている担当者にも役立つ内容です。
目次 [非表示]
在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の概要
「特定技能」は、2019年4月に新しくできた在留資格です。人手が足りない産業分野(2025年6月時点で16分野)で、すぐに現場で働ける外国人を受け入れるためにつくられました。
この資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、本人の技能レベルなどに応じて次のように分かれています。
比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
在留期間 | 最長5年 | 無期限(更新が必要) |
家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子どもを呼べる |
技能水準 | 基本的な業務に必要な技能 | より高度で熟練した技能 |
日本語能力 | 日常会話レベル(JLPT N4程度) | 一部の分野でN3レベルが必要 |
対象分野 | 全16分野 | 全11分野 |
試験等 | 技能評価試験と日本語試験 | 技能評価試験 |
※特定技能2号へは、1号で3年以上働いたあとに、試験に合格することで移行できます。

この制度では、日本にすでに住んでいる外国人(たとえば技能実習や留学を経験した人)が「特定技能」へ変更して働くケースが多くなっています。※緑色の棒グラフ
すでに国内で暮らし、日本での就労経験のある人が特定技能に切り替えることで、企業としてもすぐに戦力になる人材を確保できるのがメリットです。こうした理由から、在留資格の変更手続きを使う外国人が増えています。
一方で「最初から特定技能の許可を受けて日本に入国する人(※橙色の棒グラフ)」も年々増えており、受け入れ方法が多様化しています。
さらに、政府は2024年度から2028年度の5年間で、受け入れ人数の上限を最大82万人まで広げる方針を発表しました。これは、以前の上限(約34万人)の約2.4倍、実績と比べると約4倍にあたる大幅な増加です。
今後、さらに多くの業種で活躍する外国人が増えていくと予想されています。
特定産業に設定されている16分野
「特定技能1号」で働ける産業(特定産業分野)は、以下の16分野に定められています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業(2024年に追加)
- 鉄道(2024年に追加)
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業(2024年に追加)
- 木材産業(2024年に追加)
このうち「特定技能2号」へ進めるのは、次の11分野に限られます。
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
2号へ移行するには、1号での勤務経験に加えて、より高度な技能があることを証明する試験に合格しなければなりません。
また、今後受け入れ人数が増えるにつれて、2号の対象分野も広がっていく可能性があります。
「特定技能1号」「特定技能2号」を取得できる外国人
「特定技能」の資格を取得するには、特定産業分野で即戦力として働ける能力が必要です。
申請前に「分野ごとの技能試験」や「日本語試験」を受けて、一定の基準を満たしているかを確認します。
分野によっては、実際の職務経験がなくても、試験に合格すれば在留資格を得ることができます。
「1号」「2号」の詳しい条件については、以下の記事もあわせてご覧ください。
特定技能外国人を受け入れるまでの流れ

出典:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
特定技能の外国人を雇うには、いくつかのステップが必要です。試験の受験や契約、申請の手続きなどを順番に進めていきます。
この手続きの流れは、外国人がすでに日本に住んでいるか、それとも海外から来るのかによって少しだけ違いがあります。
主なルート | 国内にいる外国人 | 海外に住む外国人 |
試験 | 国内で受験 | 海外または日本で受験 |
申請方法 | 本人または支援者が在留資格変更許可申請を提出 | 企業が在留資格認定証明書交付申請を提出 |
入国の有無 | 不要(すでに日本に滞在) | 査証(ビザ)を取得して来日 |
雇用開始 | 在留カードが交付されたら勤務開始 | 入国後に在留カードを受け取り、その後勤務開始 |
STEP1. 技能試験と日本語試験の受験

まずは、日本で働くために必要な日本語力と、希望する職種に関する技能を確認する試験を受けます。
- 技能評価試験(職種ごとに内容が異なります)
- 日本語試験(基本はJFT-Basic、または日本語能力試験N4以上)
これらの試験は日本国内だけでなく海外でも実施されており、出入国在留管理庁や各分野の公式サイトから申し込めます。
※なお、特定技能1号を取得する場合、技能実習2号を良好に修了していれば、試験が免除されることがあります。
STEP2. 就職先の決定
試験に合格したら、特定技能の受け入れを行っている企業と雇用契約を結びます。自分で企業に応募する場合もあれば、以下のような方法で職場を探すこともできます。
- 民間の人材紹介会社を利用する
- ハローワークを通じて探す
- 海外の送出し機関を通じて見つける
企業側では、雇用契約の前に「支援計画」の準備や、必要書類の確認なども同時に進めておくことが大切です。
STEP3. 在留資格の取得(または変更)

雇用契約が決まったら、出入国在留管理庁へ在留資格の申請を行います。申請の方法は、外国人が国内にいるか海外にいるかによって異なります。
- 国内にいる場合:在留資格変更許可申請
- 海外にいる場合:在留資格認定証明書の申請 → 査証(ビザ)の取得 → 入国
在留資格の取得・変更に必要な主な書類
企業が準備する書類 | 外国人本人が用意する書類 |
|
|
※申請の種類によって必要書類が一部異なることがあります。詳しくは以下の記事をご確認ください。
【2025年最新】特定技能の必要書類を徹底解説!
STEP4. 入社前の準備
在留資格の許可が下り、在留カードを受け取ったら就労に向けた準備が始まります。
ただし、日本での生活に慣れていない外国人にとっては、手続きや生活面の整備が難しく感じられることもあります。そのため、企業側はサポート体制をしっかり整えておきましょう。
外国人本人とおこなう主な準備
- 生活オリエンテーションの受講(労働条件や生活マナーなどの説明)
- 市区町村での住民登録(住民票の作成)
- 給与の振込用口座の開設(日本国内の本人名義の銀行口座)
- 住まいの確保(企業が手配したり保証人になったりすることもあります) など
STEP5. 受け入れ機関での就労開始
生活面の準備が整い、初出勤の日を迎えたら、いよいよ就労がスタートします。
ここからは、実際に働きながら定着してもらうためのサポートが重要になります。とくに「特定技能1号」の外国人に対しては、法律で決められた支援計画にもとづき、企業が責任を持って支援を行わなければなりません。
※具体的な支援の内容については、後のセクション「支援計画10のポイント」で紹介しています。
なお「特定技能2号」の外国人に対する支援は義務ではありませんが、継続的なサポートがあると職場になじみやすくなります。
長く活躍してもらうには、2号の人に対しても丁寧にフォローする体制が望ましいといえるでしょう。
特定技能外国人と受け入れに関わる機関の役割・条件

出典:出入国在留管理庁 外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
特定技能の在留資格で外国人を雇う場合「外国人本人」と「受け入れ企業(所属機関)」に加え「登録支援機関」や「送り出し機関」といった組織も関わってきます。
ここでは、それぞれの立場と役割について、順番に見ていきましょう。
外国人本人の条件
特定技能の外国人として働くには、次のような条件を満たす必要があります。これらは、安心して仕事ができる環境を整えるための最低限のルールです。
- 18歳以上である
- 技能試験と日本語試験に合格している(※技能実習2号を修了している場合、試験は免除)
- 特定技能1号として、通算5年を超えて在留していない
- 保証金を支払っていない、または違約金付きの契約を結んでいない
- 自己負担がある場合、その内容を正しく理解している
最近は、保証金の禁止や費用負担の透明化など、制度の整備が進んできました。外国人を守るための仕組みも強化されています。
また、出身国によっては、政府に認定された送り出し機関を通す必要がある場合や、日本語研修の修了証が求められることもあります。手続き前に、それぞれの国のルールを確認しておくと安心です。
受入れ機関(所属機関)の役割と条件
受け入れ機関とは、実際に外国人を雇う企業のことを指します。
外国人を採用するには、以下の条件を満たし、支援担当者(支援責任者)を社内に選任しておく必要があります。
- 入管法や労働法などの法律を守っている
- 特定技能外国人や同じ業務の日本人を、過去1年以内に会社都合で退職させていない
- 不適切な支援や未払い賃金などが原因で、過去1年以内に行方不明になった外国人がいない
- 給与を銀行口座に振り込むことができる
- 特定技能協議会に加入できる
- 外国人が理解できる言語で支援を行える
特定技能1号の受け入れでは、上記に加えて「支援計画」を作成し、実際に支援を実施する必要があります。※特定技能2号の場合、この支援義務はありません。
支援計画とは?
支援計画とは、外国人が安心して働けるよう、生活面や職場環境をサポートするための計画です。
住まいや生活オリエンテーションなど、決められた10項目の支援内容をもとに策定します。
この計画の作成は受け入れ企業の責任とされており、最初の書類は自社で用意する必要があります。登録支援機関にすべてを任せることができないため、多くの企業はアドバイスを受けながら進めています。
なお、日々の支援業務や書類提出は、登録支援機関へ委託するケースが一般的です。
近年は、支援体制の不備によって申請が不許可になる例も増えてきました。とくに、外国人が失踪した場合は、企業に受け入れ制限がかかる可能性があります。
そのため、書類の準備だけでなく、社内の理解や支援体制の整備も重要です。
登録支援機関の役割と条件

登録支援機関は、特定技能1号の外国人に対して「支援計画」の作成サポートや実施を行う外部の専門機関です。
企業のなかに支援体制が整っていれば、必ずしも登録支援機関を利用する必要はありません。しかし、多くの場合は専門知識や実績のある支援機関に任せることで、スムーズに手続きを進めることができます。
とくに、実績のある登録支援機関と連携すれば、書類の不備による申請の不許可や支援上のトラブルも防ぎやすくなります。
登録支援機関として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 入管法や労働関係の法令を守っている
- 支援責任者・支援担当者を配置している
- 以下のいずれかの実績・経験がある
- 中長期在留者を受け入れた実績(過去2年以内)
- 外国人向け相談業務を事業として行っている
- 支援担当者が過去2年以上、外国人支援に携わっていた
- 上記と同等と認められる体制やスキルを持っている
- 外国人が理解できる言語で支援を行える
- 過去1年以内に重大な不正(失踪など)を起こしていない
- 支援にかかる費用を、外国人本人に負担させていない(直接・間接問わず)
登録の有効期間は5年で、継続するには更新手続きが必要です。
登録支援機関の一覧は、出入国在留管理庁の公式サイトで確認できます。
参考:出入国在留管理庁 登録支援機関(Registered Support Organization)
登録支援機関とは?特定技能1号の外国人雇用で利用できる、政府認定機関による労働者支援「10項目」を解説
Guidable株式会社では、特定技能外国人の受け入れに関するあらゆる業務をサポートしています!
- 登録支援機関としてのサポート
- 初期相談から就労開始までの手続き代行
- 書類作成・MOC対応・受け入れ体制の整備まで一括対応!
「何から始めればいいかわからない…」という企業様も、ぜひお気軽にご相談ください。
▼Guidable Jobs for 特定技能について詳しくはこちら▼
送り出し機関の役割と条件
送り出し機関とは、日本で働きたい外国人を海外で募集し、日本に送り出すまでのサポートを行う機関です。
※技能実習制度における送り出し機関とは定義が異なり、特定技能では利用が任意です
すでに日本で生活している外国人の在留資格を変更して雇用する場合、この機関を通さないこともあります。一方で、海外から新たに呼び寄せるケースでは、相手国の行政との手続きが必要になるため、送り出し機関との連携が重要なポイントです。
次のような条件を満たす機関を選ぶと、トラブルのリスクを減らせます。
- 日本語でのやり取りができる現地担当者がいる
- 候補者の選定や日本語教育の体制が整っている
- 相手国政府からの認可・推薦を受けている
- 不透明な費用請求や保証金の徴収をしていない
出入国在留管理庁は、送り出し機関との契約内容についてもチェックしており、不適切な契約(例:違約金、罰金条項など)がある場合は不許可になることもあります。
信頼できる機関と連携することが、スムーズな受け入れとトラブル回避のポイントです。
特定技能外国人の「支援計画」10のポイント

特定技能の在留資格を持つ外国人には、ほかの在留資格と比べて、企業が行うべき支援内容が多く決められています。
とくに「特定技能1号」の場合は、支援の内容と方法をあらかじめ書面でまとめて提出しなければなりません。
ここからは、外国人の職業生活・日常生活・社会生活を支えるために、省令で定められている10項目の支援内容について説明していきます。
1. 事前ガイダンス
在留資格認定証明書の交付申請や、在留資格変更許可申請を行う前に、以下の内容を説明します。説明は、対面やテレビ電話(Zoomなど)でおこなうことが可能です。
- 労働条件(勤務時間・賃金・休日など)
- 業務内容(職種・勤務地・勤務形態など)
- 入国時の流れと必要な手続き
- 保証金徴収の有無と禁止事項の説明
とくに入国前のガイダンスは、外国人本人の不安を軽減するうえで重要です。できるだけ母国語に近い言語で丁寧に説明しましょう。
2. 出入国する際の送迎
外国人が日本に入国・出国する際には、移動の不安をやわらげるためのサポートが必要です。
- 入国時:空港から事業所または住居までの送迎
- 帰国時:住居から空港まで同行し、保安検査場まで案内
空港でのピックアップには、登録支援機関のスタッフや翻訳者が同行することも多いです。
3. 住居確保・生活に必要な契約支援
安心して働き始められるよう、以下をはじめとした住まいや生活インフラの準備を支援します。
- 社宅の提供、または連帯保証人としての協力
- 銀行口座の開設
- 携帯電話・インターネット・電気・ガス・水道などの契約サポート など
生活インフラが整っていないと、働くどころではなくなってしまいます。そのため、受け入れ時点で入居できる住宅を確保しておくことが、実務上とても重要です。
近年では、保証人不要のサービス住宅と提携している企業も増えています。
4. 生活オリエンテーション
日本での暮らしに早く慣れてもらうため、基本的なルールや習慣を説明します。
- ごみの出し方や交通ルール
- 公共機関・施設の利用方法
- 火災・病気・地震などの緊急時の対応
- 医療機関の受診方法 など
口頭での説明だけでなく、多言語対応の資料や動画、地域の外国人支援センターとの連携なども活用すると効果的です。
5. 公的手続などへの同行
行政の手続きをひとりで進めるのが難しい場合、企業側の支援が重要になります。
- 住民登録やマイナンバーの取得
- 社会保険・税金に関する手続き
- 医療保険・年金の加入 など
入国後、役所での手続きは多く発生するため、企業の担当者が通訳や書類作成をサポートできる体制を整えておくと安心です。
6. 日本語学習の機会の提供
職場での円滑なコミュニケーションのために、日本語学習のサポートが欠かせません。
- 日本語教室・通信講座の紹介
- 学習教材やアプリの案内
- 学習時間の確保や受講費用の一部負担(可能な範囲で) など
日本語能力は職場定着に直結するため、N3以上の合格を目指す支援制度を設けている企業も増えています。
7. 相談・苦情への対応
仕事や生活に関する悩みを相談できる環境を整えることも、大切な支援のひとつです。
- 仕事や生活に関する不安やトラブルへの対応
- 本人が理解できる言語での助言
- 専用の相談窓口やLINEなどでの受付体制づくり など
外部の支援機関やNPOと連携し、第三者による相談窓口を設けておくと、企業側の負担も軽減でき、安心感にもつながります。
8. 日本人との交流促進
外国人の孤立を防ぐため、職場や地域での交流の機会をつくりましょう。
たとえば、以下のように日本人と交流する機会を設けることができます。
- 職場での歓迎会や社内イベントの実施
- 地域のお祭りや自治会活動への案内
- 社員食堂や休憩所などでの交流の場づくり など
地域の国際交流協会などと連携し、イベントへの参加を呼びかけている企業も増えています。
9. 転職支援(人員整理などの場合)
受け入れ企業の都合で雇用契約を解除する「非自発的離職」の場合には、以下のような支援が義務づけられています。
- 転職先の紹介やハローワークへの同行
- 推薦状の作成
- 求職活動のための有給休暇の付与
- 行政手続きに関する情報提供
本人の在留資格に影響が出ないよう、早めかつ丁寧に対応する必要があります。
なお、自己都合による退職の場合は支援義務はありませんが、希望があれば一定の範囲で対応する企業もあります。
10. 定期的な面談・行政機関への通報
定期面談や必要に応じた通報など、就労中のフォロー体制も支援計画に含まれます。
- 3か月に1回以上、上司・支援責任者・本人による面談を実施
- 就労状況や悩みをヒアリング
- 違法行為や人権侵害などを確認した場合、通報する義務がある
形式的な面談で終わらせず、本人の声にしっかり耳を傾ける姿勢と、記録を残す仕組みの整備を進めましょう。
支援を自社だけで行う場合は、上記の10項目すべてに対応できる体制が整っているかを事前に確認してください。
また、業務の一部だけを登録支援機関に委託することも可能です。企業の負担や人員状況に応じて、無理のない体制を組むことが大切です。
【最新情報】新制度「育成就労」について|技能実習制度との違い、何が変わるのか、今後の動きを詳しく解説
今後の制度動向と企業が今から備えておくべきこと

政府は、2024年から2028年度までの5年間で、特定技能外国人の受け入れ枠を累計で最大82万人まで拡大する方針を発表しました。
この方針とあわせて、今後は制度そのものの見直しも予定されています。
育成就労制度とのすみ分けに注意
2027年度からは、新たな在留資格として「育成就労制度」が創設される見込みです。
この制度は、これまでの技能実習制度に代わる仕組みとして準備されており、日本国内で外国人が段階的に成長していけるよう支援することを目的としています。
もともと技能実習制度は「技能移転を通じて母国の経済発展に貢献すること」を目的とした制度でした。
しかし、帰国を前提としていたにもかかわらず、実際には企業の長期的な人材ニーズや外国人本人の希望により「特定技能への移行」を見越して受け入れるケースが増えていたのが実情です。
こうした状況をふまえ、育成就労制度では、初めから人材育成と就労の両方を目的とした新たな枠組みが用意される予定です。
制度名 | 主な目的 | 在留期間 | 転籍 | 支援義務 |
育成就労制度 | 人材育成 | 最大3年 | 一部可 | あり |
特定技能1号 | 即戦力の確保 | 最大5年 | 可 | あり |
特定技能2号 | 熟練人材の定着促進 | 無期限 | 可 | なし |
※制度の詳細は、今後の法改正や政省令によって正式に決定される予定です。
【最新情報】新制度「育成就労」について|技能実習制度との違い、何が変わるのか、今後の動きを詳しく解説
今後を見据えた企業側の備えとは
特定技能の制度がさらに広がっていくなかで、企業には次のような対応が求められるようになります。
- 複数の国から人材を確保できるルートの整備
- 支援計画を社内で行うか、外部に委託するかの体制見直し
- 日本語教育やキャリア支援など、定着を意識した中長期的な制度づくり
- 社内の多文化理解やマネジメントに関する研修の充実
こうした準備を早めに進めておくことで、制度の変化にも柔軟に対応でき、安定した採用や定着にもつながっていきます。
さいごに
特定技能制度は、単に「人手不足を補うための仕組み」ではなく、長く一緒に働ける外国人と信頼関係を築いていくための制度です。
制度の変更や社会の変化に柔軟に対応しながら、早めに体制を整えておくことが、これからの採用を成功に導くポイントになるでしょう。
外国人雇用を「特別なこと」ととらえるのではなく、「当たり前の選択肢」として社内に根づかせることで、外国人にとっても企業にとっても安心できる受け入れ環境が少しずつ整っていきます。
「制度の違いがわかりにくい…」と感じたら、まずはこの資料をチェック!
「技能実習と特定技能のちがいって?」「育成就労って結局どうなるの?」
外国人採用を検討する中で、そんな疑問を感じたことはありませんか?
ガイダブルジョブスでは、技能実習・育成就労・特定技能の3制度について、特徴や移行パターン、採用にかかる主な費用、活躍しやすい人材のタイプなどを、わかりやすくまとめた資料をご用意しています。
制度の全体像を把握したい方や、社内で導入を検討している方にとって、役立つ内容が詰まった1冊です。
変化の多い今のタイミングでこそ、基本をしっかり押さえておくことで、制度を味方にした採用が進めやすくなります。
外国人採用ハンドブックを見てみる⇒資料はこちらから