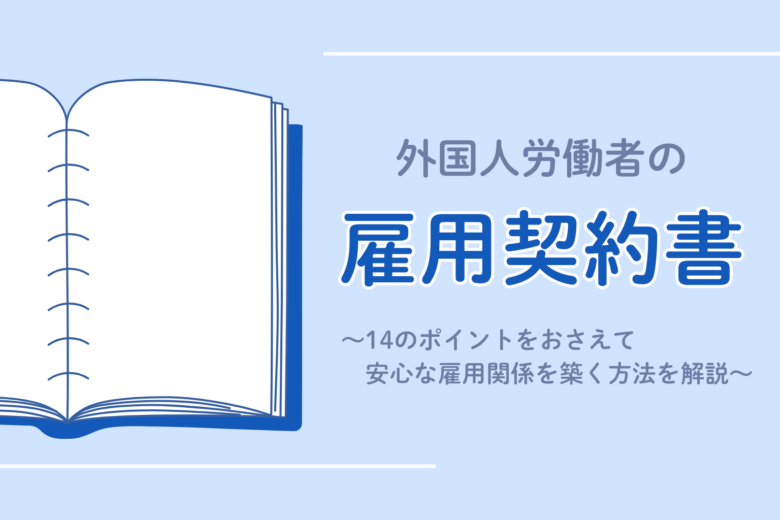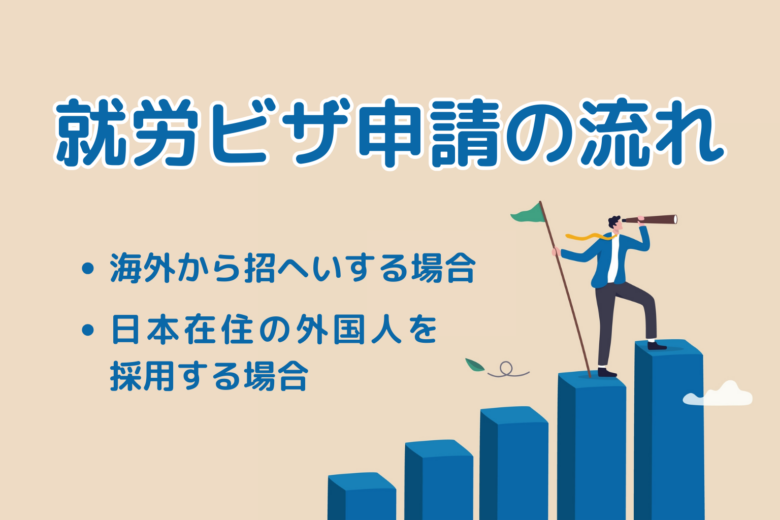【保存版】外国人採用の必要書類まとめ|雇用形態・時期別にポイント解説

「外国人を採用したいけれど、どんな書類が必要なのかよくわからない」「手続きの流れに不安がある」と感じている方も多いのではないでしょうか。
実際には、雇用形態やタイミングによって準備すべき書類や確認内容が大きく変わります。対応を間違えると、トラブルや不法就労につながることもあるため、事前にしっかり把握しておくことが大切です。
この記事では、正社員・派遣社員・アルバイトといった雇用形態ごとに、面接の段階から入社後までに必要な書類と確認のポイントをわかりやすく整理しました。
外国人採用が初めての担当者でも、スムーズに手続きを進められるよう、実際の流れに沿って実務的な視点から解説しています。
目次
外国人採用に必要な書類と手続きの基本
外国人を採用する場合、面接前・内定後・入社後といった各段階で、確認すべき書類や必要な手続きが大きく異なります。国内在住か海外在住か、どの在留資格を持っているかによっても準備内容が変わるため、それぞれの違いを理解しておくことが大切です。
また、正社員・派遣社員・アルバイトなど、雇用形態によって企業側の対応や手続きのポイントもさまざまです。
まずは採用の目的や雇用形態ごとの特徴をふまえ、今後の解説の土台となる考え方を整理しておきましょう。
雇用形態別に押さえたい採用のポイント
同じ業界や職種であっても、雇用形態によって採用の目的やメリットが異なります。
また、採用から入社後にかけて必要な手続きも変わってくるため、企業がどのような働き方で人材を受け入れたいのかを明確にしておくことが重要です。
その上で、どんな手続きが必要か、どの書類を準備すべきかを早めに整理しておくと、スムーズに進めやすくなります。
正社員・契約社員の特徴
- 長期的に安定して働ける人材を確保でき、専門スキルの育成にもつなげやすい
- 在留資格の確認や変更、入社後の各種手続きまで、企業側で一貫して対応する必要がある
- 自社対応が難しい場合は、行政書士や登録支援機関など、外部の専門家に一部を委託することも可能
- 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働く場合は、職務内容が資格の条件に合っているかを必ず確認する
日本の就労ビザとは|種類・要件・申請の流れを解説【2025年最新】
派遣社員の特徴
- 雇用契約は派遣元企業との間で結ばれ、在留資格の確認や更新も派遣元がおこなう
- 在留期間の管理や不法就労のリスクを軽減でき、手続き負担が比較的少ない
- 派遣先企業は、日本人の派遣社員と同様の受け入れ対応を行えば問題ない
- 製造や介護、ITなど、特定分野に強みを持つ派遣会社も多く、即戦力人材を受け入れやすい
派遣会社は外国人雇用が当たり前の時代に!派遣業務ができる在留資格にはどのようなものがある?
パート・アルバイトの特徴
- 短期的な仕事や繁忙期の対応など、柔軟な働き方に向いている
- 「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」などの在留資格がある人は、時間や業務の制限なく働ける
- 「留学」や「家族滞在」の人は資格外活動の許可を得れば勤務できるが、週28時間以内などの制限がある
- 接客や清掃、工場ラインなど、単純労働にも対応しやすい
- 採用から契約まで企業で行う点は正社員と同じだが、在留資格の更新などは基本的に本人が対応するため、企業側の負担は少なめ
アルバイトで採用できる在留資格は? 資格外活動許可が必要な資格はある?
面接・顔合わせの際に確認する書類
正社員・契約社員の場合
- 履歴書
- 職務経歴書
- 日本語能力試験の結果(必要に応じて確認)
- 卒業証明書 または 卒業見込証明書(専門性を確認したい場合)
派遣社員の場合
- なし
※労働者派遣法により、面接などの選考行為は禁止されています。
パート・アルバイトの場合
- 履歴書
- 日本語能力試験の結果(必要に応じて確認)
入社前に確認・準備する書類
正社員・契約社員の場合
- 在留カード
- パスポート
- 雇用契約書 または 労働条件通知書
- 就労資格証明書
- やさしい日本語で書かれた就業規則
- 在留資格変更許可申請に必要な書類(該当する場合)
- 在留資格認定証明書交付申請に関する書類(海外在住者の場合)
派遣社員の場合
- なし
※在留資格や就労条件の確認は派遣元企業が行います。国籍に関わらず、通常の派遣契約に従って進められます。
パート・アルバイトの場合
- 在留カード
- パスポート
- 学生証や長期休暇の証明書(留学生の場合)
- 指定書(特定活動・文化活動などの場合)
- 雇用契約書 または 労働条件通知書
- やさしい日本語で書かれた就業規則
入社後に確認・準備する書類
正社員・契約社員の場合
- 雇用保険被保険者資格取得届 または 外国人雇用状況届出書(入社時)
- 所属機関・契約機関に関する各種届出
- 在留資格更新許可申請に関する書類
- 雇用保険被保険者資格喪失届 または 外国人雇用状況届出書(離職時)
派遣社員の場合
- なし
※雇用や在留資格に関する手続きはすべて派遣元企業が担当します。受け入れ先企業が独自に書類の提出を求めることはできません。
パート・アルバイトの場合
- 雇用保険被保険者資格取得届 または 外国人雇用状況届出書(入社時)
- 雇用保険被保険者資格喪失届 または 外国人雇用状況届出書(離職時)
また、外国人労働者の入社時にも、日本人と同じような書類が必要になります。
マイナンバーや年金手帳、源泉徴収票、給与振込先の口座情報などは、事前に用意してもらうとスムーズです。
外国人との面接・顔合わせの際に使用する書類のチェックポイント

外国人を採用する際も、日本人と同じように、公正な選考を行うことが大切です。
職業安定法では、社会的な差別につながるおそれがある個人情報を、選考の段階で集めることを禁じています。そのため、面接時に在留カードや就労資格証明書を提示させることはできません。
ここでは、面接や顔合わせのときに確認できる書類と、それぞれのチェックポイント・注意点を紹介します。
履歴書・職務経歴書
外国人候補者の学歴や職歴、過去の勤務内容などを確認するための基本的な書類です。
とくに、就労系の在留資格が必要な業務を想定している場合は、学歴や職歴が条件に合っているかを確認する材料になります。
面接では、履歴書や職務経歴書の内容に沿って、以下の点を丁寧に確認しておくとよいでしょう。
- 応募している業務内容と、本人のスキルや経験が合っているか
- 現時点でどの在留資格を持っているか、今後資格変更の予定があるか
- 在留資格が「留学」「家族滞在」「文化活動」などの場合、資格外活動許可を取得しているかどうか(履歴書の記載や口頭確認でチェック)
これらを早めに確認しておくことで、採用後の手続きがスムーズになり、在留資格の審査も通りやすくなります。
日本語能力試験の結果
接客や文書作成など、日本語でのやり取りが多い職種では、応募者の日本語力を採用判断の材料にすることがあります。たとえば、日本語能力試験(JLPT)の結果や、自社で独自に日本語テストをおこない、その結果をもとに評価する方法がよく使われています。
面接時には、以下の点を押さえておくと安心です。
- 「JLPT N2以上」など、あらかじめ基準を設定しておく
- 求職者が日本語力を証明する書類を持っている場合、任意で提出を依頼する(強制は不可)
- 自社テストを活用する場合は、試験方法や評価基準も説明しておく
日本語力の確認を早い段階で行っておくことで、入社後のミスマッチやトラブルを防ぎやすくなります。
卒業証明書・卒業見込証明書
新卒の外国人材を採用する場合や、中途採用で専門知識を確認したいときには、卒業証明書や卒業見込証明書を事前に確認しておくと安心です。とくに、在留資格の審査では、学歴が条件を満たしているかが重要になることがあります。
面接時には、以下の点を押さえておきましょう。
- 「技術・人文知識・国際業務」など就労系の在留資格では、業務内容に関連する学部・学科を卒業しているかどうか
- 提出が面接当日でなくても問題はないが、理由を事前に説明しておく
※ただし、採用後の在留資格申請にも関わるため、できるだけ早めに確認する
卒業証明書の内容は、在留資格との関連性を判断する重要な資料です。準備が間に合わない場合も、口頭での確認や提出予定日の共有をしておくと、後の手続きがスムーズに進みます。
外国人面接の基本ガイド|確認事項・NG質問・フォロー手順を紹介
外国人の入社前(内定後)に必要な書類のチェックポイント

採用が決まったら、外国人採用ならではの書類確認や手続きが始まります。
在留資格に問題がないか、働くための条件がそろっているかを確かめるために、雇用形態に応じて必要な書類を整理しておきましょう。
在留カード

採用が決まった段階で、まず確認すべきなのは「在留カードの現物」です。就労が可能かどうかを見極めるために、以下の5点を中心にチェックしましょう。
1. 偽造されていないか
以前は目視で確認するのが一般的でしたが、最近は精巧な偽造カードも出回っています。
そのため、2020年以降は、ICチップを読み取るアプリを使った確認方法が推奨されています。
参考:出入国在留管理庁 在留カード等読取アプリケーション サポートページ
参考:出入国在留管理庁 「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方
2. カードが有効期限内か
カードの表面下部には「在留期限」が記載されています。この期限が過ぎていないかを確認し、もし近づいている場合は更新を案内しましょう。
また、カード右上の番号を使えば、出入国在留管理庁のウェブサイトで失効していないかを調べることもできます。
3. 就労制限の有無
「就労制限の有無」欄には、下記のいずれかが記載されています。
担当してもらう業務が、この制限内で可能かどうかを事前に確認しておくことが大切です。
| カード記載 | 就労内容 | |
| 1 | 就労制限なし | ・日本人と同様に就労が可能 ・単純労働が可能 |
| 2 | 在留資格に基づく就労活動のみ可 | ・取得している「在留資格」の確認が必要 ・単純労働は不可 |
| 3 | 指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可 | ・パスポートに貼付されている「指定書」の確認が必要 ※詳細は後項に記載 |
| 4 | 指定書により指定された就労活動のみ可 | ・パスポートに貼付されている「指定書」の確認が必要 ※詳細は後項に記載 |
| 5 | 就労不可 | ・在留カード裏面の「資格外活動許可欄」の確認が必要 |
4. 取得している在留資格と職務の整合性
就労制限の有無欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と書かれている場合、その在留資格が職務内容に合っているかを見極める必要があります。
もし業務内容が資格の範囲に入らないときは、入社前に必ず「在留資格変更許可申請」をおこないましょう。
5. 資格外活動の許可があるか
就労制限の有無欄に「就労不可」と書かれていても、カード裏面に資格外活動の許可があれば、アルバイトなどが認められる場合があります。
「資格外活動許可欄」には下記のいずれかが記載されています。
| カード記載 | 就労内容 | |
| 1 | 許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く | ・1週間につき28時間以内 ・単純労働が可能 |
| 2 | 許可:資格外活動許可書に記載された範囲内の活動 | ・「資格外活動許可書」の確認が必要 ・単純労働は不可 |
また、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持つ人が副業を希望する場合は、別途「資格外活動許可書」で内容を確認する必要があります。なお、副業であっても単純労働は原則として認められていないため、注意が必要です。
パスポート
在留カードとあわせて、本人確認のためにパスポートも確認します。
学生証・長期休暇証明書
在留資格が「留学」の場合は、資格外活動の許可があれば、週28時間以内の就労が可能です。
また、夏休みなどの長期休暇中であれば、週40時間まで働くことが認められます。ただし、この休暇は「学校の学則で定められた期間」に限られるため、不安なときは「長期休暇証明書」を学校に発行してもらいましょう。
指定書
特定の在留資格を持っている場合、パスポートに「指定書」が貼られていることがあります。
本人に認められた活動内容や就労の条件が記載されているため、就労可否の判断に使える書類です。
指定書が貼付される在留資格の例
- 特定活動(インターンシップ、ワーキングホリデーなど)
- 特定技能
- その他、個別に制限のある在留資格
確認時のポイント
- 指定された活動内容と、実際の仕事内容が一致しているか
- 「報酬を受ける活動を除く」などの制限がないか(ある場合、給与の発生する業務は不可)
- 働く場所や機関が指定されているときは、その範囲を超えていないか
指定書ってなに?発行される外国人の条件、書かれている内容や採用時に確認したいポイントを見本付きで解説!
雇用契約書・労働条件通知書
外国人であっても、労働基準法に基づき、労働条件を明示することは雇用主の義務です。
とくに外国人の場合は、言葉の行き違いによるトラブルを防ぐためにも、書面での合意が重要とされています。そのため、できるだけ「雇用契約書」を作成し、両者でしっかり確認したうえで締結しましょう。
契約書には、次の内容を必ず明記しておく必要があります。
- 契約期間
- 勤務地
- 業務内容
- 労働時間や休日の条件
- 賃金
- 退職や解雇に関する取り決め
【外国人採用】雇用契約書の作り方|必要項目やトラブル防止策を解説
就労資格証明書

在留カードだけでは、実際にその仕事内容で働けるかどうかがわかりにくい場合があります。とくに転職者などで不安がある場合は「就労資格証明書」の提出をお願いすると、より確実に確認できます。
この証明書は、雇用契約書や労働条件通知書などをもとに、出入国在留管理庁へ申請することで発行されます。
内容に問題がなければ「転職後の勤務先」が明記されるため、企業側も安心できます。
なお、この確認は必須ではありません。前職と同じような仕事内容であれば、証明書を取得しなくても問題ないとされています。
やさしい日本語を使った就業規則
就業規則は、雇用主が労働者にきちんと内容を伝えることが法律で決められています。
掲示や書面での配布など、周知の方法はいくつかありますが、外国人にも伝わるように配慮することが大切です。
なお「外国人専用の就業規則」を作るのは望ましくありません。
日本人と同じルールを適用し、そのうえで内容をやさしい日本語や母国語で説明する資料を作成しましょう。そうすることで、働く本人も安心して業務に取り組むことができます。
やさしい日本語って何? 建設、介護、清掃業界で使える「言い換えの表現」も収録しています!
在留資格変更許可申請に関する書類
「留学生を正社員として雇う」場合など、仕事内容と現在の在留資格が一致していないときは、かならず入社前に在留資格の変更を行う必要があります。
この申請をせずに働き始めてしまうと「資格外活動」にあたるおそれがあり、在留資格の取り消しにつながる可能性もあります。
申請には、本人の資料だけでなく、企業側が用意する書類も複数必要です。たとえば、登記事項証明書(登記簿謄本)や定款の写し、直近の決算書などが求められます。
申請から許可が出るまでは、通常1か月ほどかかるため、採用が決まったらすぐに、必要な書類の準備と情報共有を始めましょう。
在留資格認定証明書交付申請に関する書類
海外在住の外国人を日本に呼び寄せて採用する場合には、まず「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
この申請は企業側が行い、来日前の手続きを支援しましょう。
最近では、この手続きもオンラインで完結できるようになりました。
認定証明書が発行されると、PDFでのダウンロードやメール送信が可能になります。その後、本人が現地の日本大使館や領事館にそのPDFを持参して、ビザの申請を行う流れです。
証明書の交付までには、通常1〜3か月程度かかるため、採用が決まったらすぐに取りかかりましょう。
【行政書士監修】就労ビザ申請の流れ|海外から招へいする場合、日本在住の外国人を採用する場合の2通りに分けて解説!
なお、海外から外国人を受け入れる場合は、生活面での支援も重要です。
安心して新しい暮らしを始められるよう、入国後に必要となる手続きを企業がサポートするケースが増えています。
たとえば、次のような準備があげられます。
- 住民登録(入国後14日以内)
- 銀行口座の開設
- 携帯電話やWi-Fiの契約
- 住まいの確保や契約の立ち会い
こうした支援があることで、本人も不安なく働き始めることができます。受け入れ側の丁寧な段取りが、その後の定着にもつながっていくでしょう。
外国人の入社後に必要な書類のチェックポイント

外国人労働者が入社したあとは、日本人の採用とは異なり、ハローワークへの届出や在留資格に関する手続きが必要になることがあります。
また、退職する際にも速やかな報告が求められるため、企業が責任をもって対応することが大切です。
ここでは雇用形態ごとに必要な書類を整理したうえで、それぞれの注意点を確認していきましょう。
雇用保険被保険者資格取得届・外国人雇用状況届出書(入社時)
正社員や契約社員、パート・アルバイトを採用した場合、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を提出する義務があります。
この届出によって厚生労働省は外国人労働者の人数を把握し、今後の制度設計に役立てています。また、就労状況を可視化することで、不法就労の防止にもつながる制度となっています。
届出書類は、雇用保険の被保険者であるかどうかによって異なります。次のいずれかの方法で、状況に合った届出をおこないましょう。
| 対象者 | 届出書類 | 届出期限 |
| 雇用保険被保険者の対象者 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 入社日〜翌月10日まで |
| 雇用保険被保険者の対象者以外 | 外国人雇用状況届出書 | 入社日〜翌月末まで |
参考:厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
参考:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)
所属機関・契約機関に関する各種届出
外国人を正社員などとして雇用する際には、在留資格の種類によって「所属機関」または「契約機関」に関する届出が必要になることがあります。
これは、外国人がどこで働いているのかを出入国在留管理庁に報告する制度で、原則として入社日から14日以内に本人が提出します。
ただし、本人が期限内に対応できない場合は、企業が委任を受けて代わりに提出することも可能です。
必要な届出や対象となるケースは在留資格によって異なるため、以下の表を参考に、どの書類が必要かを確認しておきましょう。
| 届出手続 | 対象となる在留資格 | 対象となるケース |
| 活動機関に関する届出手続 | ・教授 ・高度専門職1号ハ ・高度専門職2号ハ ・経営・管理 ・法律 ・会計業務 ・医療 ・教育 ・企業内転勤 ・技能実習 ・留学 ・研修 | ・活動機関の名称変更 ・活動機関の所在地変更 ・活動機関の倒産 ・活動機関の合併 ・活動機関からの離脱 ・活動機関の移籍 |
| 契約機関に関する届出手続 | ・高度専門職1号イ、ロ ・高度専門職2号イ、ロ ・研究・技術・人文知識 ・国際業務 ・介護 ・興行(日本の機関との契約で活動している場合) ・技能 ・特定技能 | ・契約機関の名称変更 ・契約機関の所在地変更 ・契約機関の倒産 ・契約機関の合併 ・契約終了 ・新規契約 |
| 配偶者に関する届出手続 | ・家族滞在 ・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等 | ・配偶者との離婚 ・配偶者との死別 |
なお「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった在留資格を持つ方については、離婚や死別など家族関係に変化が生じた際に「配偶者に関する届出」をおこなう必要があります。
この手続きは本人が出入国在留管理庁に対しておこなうもので、企業が直接関与することはありません。
ただし、家族構成の変化によっては在留資格の変更が必要になる場合もあるため、本人の状況や動向に注意を払っておくことも大切です。
在留資格更新許可申請に関する書類
外国人社員の在留期限が近づいた場合は、在留資格の更新が必要です。この申請は、在留期限の3か月前から受け付けてもらえます。
手続き自体は原則として本人が行いますが、企業側が作成する書類もあります。たとえば、仕事内容や契約の更新に関する資料などが必要となるため、前もって準備しておきましょう。
もし更新手続きを忘れてしまうと、不法就労になるおそれがあります。そのため、在留カードの有効期限を社内で定期的に確認できる仕組みを整えておくことが大切です。
最近では、在留期限を自動で管理できるシステムや、アラート通知をしてくれるツールもあります。とくに複数名の外国人を雇っている企業や、部署異動が多い職場では、こうしたツールの導入を検討するのもおすすめです。
雇用保険被保険者資格取得届・外国人雇用状況届出書(離職時)
退職の際にも、ハローワークへの届出が必要になります。入社時と同様に、雇用形態や保険の加入状況によって、提出すべき書類や期限が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
とくに、離職後の手続きが遅れると、失業給付の申請や在留資格の更新などに影響を及ぼすことがあります。
こうしたトラブルを防ぐためにも、退職が決まった段階で、必要な書類の準備に取りかかりましょう。
以下の表に、対象者ごとの提出書類と提出期限をまとめています。自社のケースに応じて確認しておくことをおすすめします。
| 対象者 | 届出書類 | 届出期限 |
| 雇用保険被保険者の対象者 | 雇用保険被保険者資格喪失届 | 離職日の翌日〜10日以内 |
| 雇用保険被保険者の対象者以外 | 外国人雇用状況届出書 | 離職日〜翌月末まで |
書類の種類や提出期限を間違えると、後々の手続きに支障をきたすおそれがあります。担当者間での情報共有を徹底し、確実な対応を心がけましょう。
【再確認!】外国人採用で書類を確認する際の注意点

ここからは、外国人を採用する際にトラブルになりやすいポイントをまとめて紹介します。
とくに気をつけたい点を一つひとつ確認していきましょう。
面接段階では在留カードやパスポートを提出させない
前のセクションでもふれたとおり、職業安定法では「社会的差別につながるおそれのある個人情報の収集は禁止」とされています。そのため、外国人の面接時に在留カードやパスポートの提示を求めると、「国籍による差別」と受け取られてしまうケースがあります。
在留資格を確認したい場合は、履歴書や職務経歴書に記載してもらうか、面接の中で口頭で確認するようにしましょう。
在留カードやパスポートは企業で預からない
厚生労働省は「外国人労働者の旅券などを補完(預かること)はしないように」と通知しています。たとえ更新手続きや航空券の手配が理由であっても、企業が原本を一時的に預かることは認められていません。
もし確認が必要な場合は、本人に対応を依頼するか、コピーをとって保管するなど、適切な方法をとりましょう。
特別永住者は各種届出が不要
「特別永住者」は、永住者と同じく就労制限がありません。大きな違いは、在留カードの代わりに「特別永住者証明書」を所持している点です。
この証明書は常に持ち歩く必要はなく、採用の際にも提示は求められません。また「外国人雇用状況の届出」も不要となっています。
特別永住者は、多くの場合「通称名」を役所で登録しており、手続きもその名前で進めることが可能です。つまり、採用時の対応は日本人と同じと考えて問題ありません。
外国人「永住者」と「特別永住者」の違いは?在留資格の要件、雇用手続きの注意点を解説
同一労働同一賃金・最低賃金を守ること
外国人であっても、日本の労働法はすべて適用されます。そのため「同じ仕事には同じ賃金を支払う」という原則や、地域ごとの最低賃金を守ることが義務になります。
もし言葉の壁や文化の違いを理由に、賃金を低く設定すると、法令違反とみなされる可能性があります。とくに「技能実習」や「特定技能」といった在留資格で働く方は、労働条件が原因で在留資格の更新ができなくなることもあるため注意が必要です。
なお、外国人社員の定着を支援するには、日本特有の職場のルールや習慣についても伝えておくことが大切です。たとえば、ビジネスマナーや健康診断の受け方などを事前に説明しておくと、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
その際は「やさしい日本語」や図を使った説明資料があると理解しやすくなり、本人の安心にもつながります。
外国人採用の手続きをサポートする外部機関・専門家
外国人を採用するには、在留資格の確認や書類の準備、各種の届出など、専門的な知識が必要になる場面もあります。
すべてを自社だけで対応するのが難しいと感じたときは、外部の専門家や支援機関の力を借りるのもひとつの方法です。
外国人雇用管理アドバイザー制度
厚生労働省では、外国人雇用の実務経験を持つ社会保険労務士などを「外国人雇用管理アドバイザー」として登録しています。
この制度では、外国人雇用に関する相談や支援を受けることができ、利用料はかかりません。
全国のハローワークで相談が可能なため、制度や手続きに不安がある企業にとっては心強いサポートになります。
申請取次行政書士
在留資格の変更や更新など、出入国在留管理庁への申請を代行できる行政書士もいます。
とくに「申請取次」の資格を持つ行政書士であれば、外国人本人の出頭が不要になる場合もあり、企業側の負担を減らすことができます。
費用は案件によって異なりますが、たとえば在留資格の変更手続きでは、おおよそ10万円前後が目安とされています。
登録支援機関や信頼できる人材紹介会社
「特定技能」の受け入れでは、登録支援機関が生活支援や書類手続きの代行を行うこともできます。受け入れ後のサポート体制が整っている支援機関を選べば、入社後の定着にもつながります。
また、信頼できる人材紹介会社を利用することで、求人募集から面接、ビザ申請に関するアドバイスまで、幅広い支援を受けることができます。
▼Guidable Jobs for 特定技能について詳しくはこちら▼
さいごに
外国人を採用するには、日本人の場合とは異なる視点や書類の管理が求められます。
とくに在留資格や法令に関わる手続きは、タイミングを逃すと大きなトラブルにつながることもあるため「いつ・何を・誰が確認するのか」をあらかじめ決めておくことが大切です。
社内だけでの対応が難しいときは、行政書士や登録支援機関、外国人雇用管理アドバイザーなど、外部の専門家に相談する方法もあります。
今回の内容が、自社の採用フローを見直すきっかけになれば幸いです。
外国人採用の準備に迷ったら、成功企業の事例を参考にしてみませんか?
外国人材の採用では、書類や法令の対応だけでなく、受け入れ体制やコミュニケーション面にも工夫が求められます。
「どんなサポートがあれば早期離職を防げるのか」「在留資格に合わせた手続きをどう進めるべきか」など、はじめての採用では不安を感じる場面もあるかもしれません。
そうした悩みに応えるのが、外国人採用に成功した企業の事例をまとめた無料資料です。
実際の現場で行われている工夫や、入社後に活躍してもらうためのポイントが具体的に紹介されており、中小企業から大手企業まで、さまざまな業種に役立つ内容となっています。
これから採用を考えている方は、ぜひご活用ください。














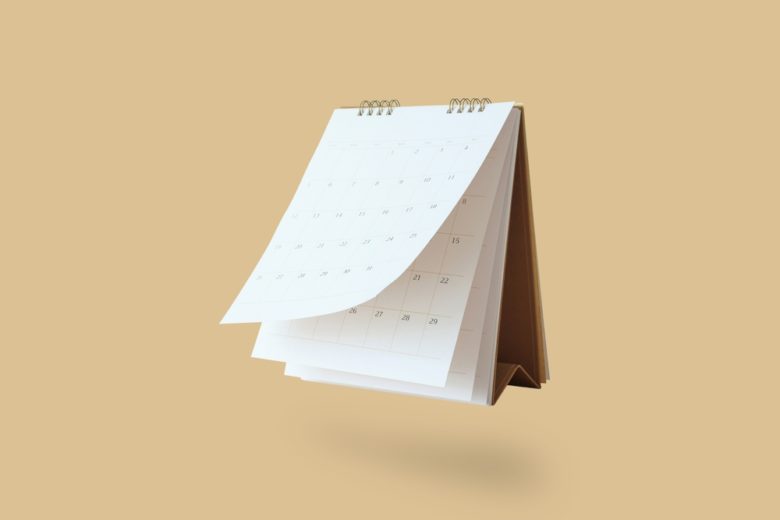



-2-780x520.png)